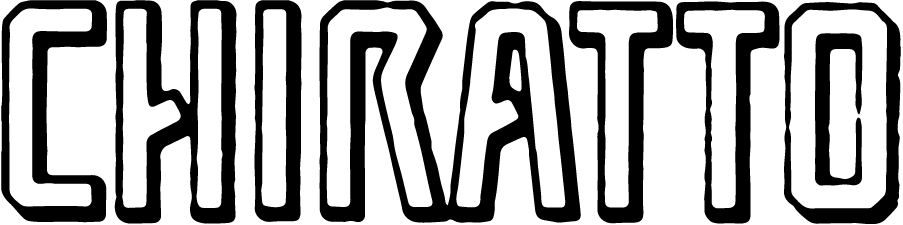第四回特別対談 加藤隆志(ミュージシャン)×川瀬陽太(俳優)

ひと際異彩を放った人
加藤 なんだか照れるね(笑)でもこんなタイミングじゃないと会えないもんね。
川瀬 加藤に初めて会ってから、もう25年…どころじゃないか、下手すりゃ30年くらいか。
加藤 俺、川ちゃんに出会った時19歳くらいじゃないかな。ちょうど30年前。今年の9月でちょうど49なんで。
川瀬 あんたも49!俺も去年で50になった。出会いのきっかけってなんだ?
加藤 たぶん、僕が前にやってたlost CANDIってバンドがあって。そのバンドのデビュー前かな。18歳くらいで田舎の友達とバンド頑張るぞって上京して。そのバンドに川ちゃんと同じ桑沢デザイン研究所に通っているメンバーがいて。それで桑沢でもう一人バンドに引き入れたいメンバーと知り合ったんですね。吉岡たくっていう。バンドを解散してからは、有名グループのアレンジャーとかをやるようなるんですけど。それで「桑沢はおもしろいからちょっと学校に遊びに来ないか」みたいな話があって。
川瀬 そうだそうだ。
加藤 僕は語学の学校に通ってたんですけど、ちょっとおもしろそうだからって渋谷のNHKホールの前の桑沢に遊びに行ったんですね。みんな個性的な人ばっかりで、その中でひと際異彩を放ちまくっていたのが、川瀬陽太っていう。
川瀬 あはは(笑)嘘つけよ。
加藤 音楽も詳しいし、映画も詳しいし、どうやらバンドもやりたいらしいと。
川瀬 まあ、そうだったね。
加藤 で、僕その時、ザ・スミスっていうバンドにハマってて、今でも好きなんですけど。で、スミスをやりたいと。川ちゃんが歌ってモリッシーの役をやって。
川瀬 役をやらされて、ね。その当時のバンドのヴォーカルが病気だかでライブハウスの対バンを穴空けそうだったの。池袋のなんだかしょうもないライブハウスで。
加藤 客が1人しかいないみたいな(笑)
川瀬 そんなところに「川ちゃんやろうよ!」って話になって。じゃあスミスのコピーでもやるか、なんつって。これ、罰ゲームみたいな話だな!
加藤 いやいやいや、全然!もっと俺の方が罰ゲームあるから!そんで、もう一人ギターがいたんだけど、たぶん俺の方がうまいなと思って、「俺がやるんで」って言ってその川ちゃんバンドのギターの座を奪った。自分のバンドと掛け持ちみたいな形でけっこうバンドをやってた時期があったっていう。
川瀬 その時なんて俺も加藤も全然お金がない、無い時にこいつ、まぁ頑張って(ジョニー・マーと同じ)リッケンバッカー買って。
加藤 そう!本当に本当に。本物のリッケンバッカーを初めて買った。
川瀬 あの時、4、50万円しただろ?
加藤 まあ30万円くらいかな。
川瀬 加藤はあの頃、それはまあひどい、床が抜けそうなところに住んでて。ある時、寝てたら布団がストーブで焼けて焦げてた。もしかしたらあの時、俺下手したら死んでたかもしれねえなと思って。
加藤 そんなことあったっけ(笑)。
川瀬 あったあった。
加藤 その当時は下北沢に住んでたんですけど、よく泊まってたよね。
川瀬 よく泊まってたよ。カーネーションの・・。
加藤 大田(譲)さんもね。あとGRANDFATHERSっていうバンドをやってる青山陽一さんっていう、大好きなんですけど、そのかたとも大田さんが鳥取出身で僕らと繋がってたりして。下北沢に友達が集結してたんですね。僕は学校が千葉だったんですけど、頑張って下北沢に住んで。川ちゃんはその時はまだ実家だったでしょ?
川瀬 実家でもあったし、いろんな所を転々としてた。そんなような感じでうじゃうじゃやってて。それこそ「スミスだ!そしたらモリッシーだろ」って。なりきって♪ファ〜〜とかって。あれ、花も?
加藤 持ってましたね。
川瀬 持ってたっけ(笑)。
加藤 僕は腰にセーター巻いて(笑)。
川瀬 やっぱりジョニー・マーって言ったら、ジーパンにジャケットだろ、ダサい感じでいけ、って。腕捲ってね。
加藤 元々そういうカッコでしたけどね。鳥取から上京して2年目くらいでしたからね。でもほんと楽しかった。
川瀬 その頃を前後して僕は学校出てからはもう、ピンク映画ですよ。成人映画ですよ。もう前貼り人生だったんですよ。とにかくおっぱい揉んでお金貰ってたような感じだったんですけど。加藤は加藤でバンドを解散して、いろんな人のバックをやってて、テレビでたまに見かけたりとかして。その頃はお互い大変だったんじゃないかなって感じだよね。
加藤 僕はけっこうデビューまでが長かったんですよね。なかなかデビューできなくて。22で大学卒業してから4年間くらいバイトだけでやってたんですけど。その頃、川ちゃんは助監督でしょ?
川瀬 そうだね。でも25くらいの時になんとなく自主映画の主役やれ、みたいなこと言われて。
加藤 とにかく川ちゃんの周りはおもしろい人が多くて。やっぱり映画の世界の人と普段交流持てないじゃないですか。自主映画も本当おもしろかったし。福居ショウジンさんとも一回お会いしたことがある。鈴木はぢさんともね。ハードコアな人ばっかり集まっているような感じだったから。音楽もいっぱい教えてもらったし。俺たぶん、ブランキー・ジェット・シティも川ちゃんから教えてもらってる。
川瀬 そうだっけ?
加藤 2ndアルバムの『Bang!』が出て、その時、川ちゃんちに遊びに行ったら「コレ、いいんだよ」って言ってて。なんか入れ墨のゴツい人が写ってるジャケットの。
川瀬 まさかその後、(中村)達也さんとやるとは思わなかったな。まだ一緒に遊びでバンドみたいなことしてる頃に、こいつアホみたいなこと言い始めて。「今日スタジオ取ってるんだけど、達也さんと一緒に入ろうよ」って。バカじゃねえの、そんなことできるわけねえじゃねえかって(笑)
加藤 あったあった。達也さんとスミスやろうよって。
川瀬 できるかそんなもの!叱られるわ!(笑)
お互いに「見える」という存在
川瀬 でもさ、加藤がバンド解散した時も個人的にはちょっと心配はしてたんだけど。俺の主観でだけど、こういうバンドの人たちが契約切られるときのご無体な感じ、なんか血も涙もねえな、ってすら思ってたくらい。
加藤 メジャーのね。ちょうど僕らは平井堅くんとかTRICERATOPSとかと同期で。
川瀬 まあCD売れてた頃だもんね。
加藤 めちゃ売れてた。僕はlost CANDIってバンドで一回デビューしたんですけど、やっぱり2枚、3枚と結果出ないと早いですよね。その頃にスカパラと出会って1年サポートとかやらせてもらって、まあこれは全然違う世界だぞ、っていうのがありながら。
川瀬 僕なんか音楽ファンの観点で見てるから、スカパラさんってそれまでギターが定着していないイメージなのね。加藤お前いついなくなるんだ!ってけっこうドキドキして見てた。そしたら、歌モノで(奥田)民生さんのがあったりして、「おお、加藤が上昇気流にのった!」と。
加藤 でも転換期はあって。スカパラのサポート時代に正式メンバーになるか、バンドが解散するからいろんなバンドのサポートをしていくか、みたいな。スカはそれまで自分が聴いてきた音楽と違うわけじゃないですか。悩んでいた時期があって、ドラムの青木(達之)さんに夜な夜な相談してたんですね。そうしてるうちに青木さんが1999年に突然亡くなってしまって、その時にもうそんなこと言ってらんねえな、と。そんな感じになったのも後押しじゃないけど。青木さんはずっと「早く入れ」って言ってくれてたんですよね。
川瀬 けっこう躊躇してたんだ?
加藤 自分のバンドを解散するまでにやり残したことがないようにとりあえず一生懸命やりたかったっていうのもあって。2年くらいはスカパラの正式メンバーをずっと断わりながらライブをやったり、もう1枚アルバムを作ったりしてたんですよね。ただ、やっぱりけっこう限界があって。デビューまでがけっこう長かったので、メンバーとの関係性もあるし。バンドって一人のものじゃないので。そこは川ちゃんのやってる俳優さんとも違うところで。
川瀬 いやあ、一人はつらいよ。俺も最悪の沈みの時があるしさ。要するに未だに俺はフリーランスだもん。携帯電話が鳴らなかったら俺はいないも同然。加藤がそうやってスカパラでわーってやってるのをメディアで見るようになって。全然職種も違うんだけど、「しょうがない、耐えるしかないんだなあ」って時がけっこうあって。それはなかなか厳しい時があったよ。膝舐めることくらいしかできなかった。
加藤 スカパラ入って民生さんのフューチャリングとかがブレイクして、その頃がちょうどいちばん会ってなかった時期ですね。
川瀬 そうだね。物理的にキミは忙しいわけだし、それは会ってないよね。
加藤 2003年くらい。そっからたぶん10年とまでいかないか、5年くらい?
川瀬 けっこう没交渉だったよね。
加藤 僕はどっちかっていうと、川ちゃんは、裏方さんというか、助監督とか監督のほうにいくと思ってた。
川瀬 俺も、そのつもりだった。
加藤 だから、俳優さんの道なんだ、って思って。そっからまた連絡を取り始めたりして。2年に1回とか3年に1回か分かんないけど。それくらいの間隔で。ね。
川瀬 それで一時期は年賀状のやりとりだけになったり。こいつに子供ができたり時候のあいさつくらいだったんだけど、やっぱりそれまで何もなかった時にお付き合いしてたから。勝手に親近感が、まあどこかで何かやってるっていうか。今はどっちかが目にする機会も互いにあるんで。あえて連絡しなくても元気にやってるんだろうし。
加藤 見える。
川瀬 そうそう。見える感じ。そんな感じではあったんですよ。
加藤 自分の中では、20代の青春、30代の青春、40代の青春の中で大事な人がいて、20代はバンドのメンバーもそうなんだけど、確実に川ちゃんなんですね。そういう存在の人は30代に入った時は中村達也さんって感じだったんですね。達也さんも川ちゃんと遊んでた頃のように本当に毎日一緒に居たし。ちょっと上なんですよね。僕が好きな先輩は。いろんなことを教えてもらえるし、楽しいっていうのが。僕にとっての川ちゃんはそういう存在ですね。


「音楽界はもうクロスオーバーになったというか。」(加藤)
川瀬 やっぱりバンドが流行ってたじゃないですか。今って気の利いた若い子だとターンテーブルの世界になってくるし。友達も映画を介して出会う奴ってラッパーとかが多いっていうか。田我流とかそこら辺のやつらと会って。まあみんな衒いがないっていうか、バンドだろうがヒップホップだろうが、普通にどんどんクロスオーバーしていくっていう感じだから。
加藤 ミックスしちゃう。今、パンクもそうですもんね。
川瀬 俺ら、あの頃って日本のラップのところをなんとなく無視と言うか素通りしちゃってきてたからね。
加藤 ジャンルでバツンと完全に聴くものが分かれていた時代だったから。交わることがあんまりなかったというか。ロックの中でも細分化されてて。それこそHi-STANDARD聴いてる人はブランキー・ジェット・シティやミッシェル・ガン・エレファント聴いてない、みたいな。それくらい細分化されてて、もう自分の思うものがロックみたいな感じだったから。
川瀬 そこの断絶すごかったよね。映画を介して後にRHYMESTERの宇多丸さんとか会ったりとかしても、「そっか」っていう感じで90年代の答え合わせみたいな。
加藤 スカ界隈の中でも派閥みたいなのがあった時代もあったし、ただ、もうクロスオーバーしてておもしろいものは交流していくみたいな感じになってきた。2010年以降だと思いますよ、たぶん。特に震災後。2011年からは音楽界はもうクロスオーバーになったというか。
川瀬 おもしろいのは、時を同じくして、わしらも自主映画みたいなものに立ち戻った。デジタルで撮るようになってから今風の言葉でいうならバズったりしちゃったり。そうすると、有名人というかスターさんみたいな人と自分らで交流が始まって。たとえば染谷(将太)が急に自主映画撮ったり。昨日も染谷と共演した、COMBOPIANOや映画音楽やってる渡邊琢磨が初監督の『ECTO』の特別上映があったり。そういうクロスオーバーもあったりして。
加藤 俺、今日ここに来るのがすごい楽しみだったのは、そこら辺の話をすごく聞きたくて。川ちゃんと会ってなかった時期があるじゃん。2003年、04年くらいから2010年くらいまでの間。その辺で川ちゃんがどういう活動してたとか。
川瀬 でも本当、震災挟んだくらいからすごい変わった気がする。みんなの感覚というか。若い子の感覚も変わってきてるから。それこそFacebookでは繋がってたんだけど、斎藤工さんが自分の出演映画を観ててくれたりてて、ある時メッセンジャーで「今度、監督するんで出ませんか」って。SNSでだよ。
加藤 すごいね。
川瀬 それくらいもう衒いがないっていうか。僕らの頃ってバンドだろうが映画だろうがヒエラルキーがあったんだけど。
加藤 一回その土壌に上がらないと、というのが取っ払われちゃった。
川瀬 有名も無名もねえな、って。風通しがいいっていうか、どこで何が起きてもおかしくない。音楽で言ったらフェスがいっぱい開催されているように、みんな自分からシャッフルされに来ているというか。今いるところに危機感がある人たち。このままでいいんだろうか、っていう。
加藤 正直、広瀬すずさん主演の『anone』に川ちゃんがガツーンって出てきた時、ちょっとびびりましたもんね。マジか!やった!って。
川瀬 あれも脚本の坂元裕二さんがおそらく映画観てくれてるんだよね、いっぱい。それで声かけてきてくれて。だけどこっちはやることは変わらないから。
年齢を重ねて思うこと
加藤 今って野望ないんすか?
川瀬 ないかな。元々、ほら、野望を持ってやってたわけじゃないから。役者をやりたくて始めたわけじゃないし。なりたい自分ってのがなかったから。
加藤 僕とかはけっこうあからさまっていうわけじゃないけど、「売れてやろう」とか「他のバンドに負けたくない」とかあって。
川瀬 けっこうカリカリしてた時あったもんね。
加藤 今もそうなんですよ。やっぱり野望というか、「絶対こうなってやる」みたいなことがありながら音楽をやってる人間だと思うんですよ。
川瀬 思い出した。一度ケンカしたことあるんですよ、そのようなことで。こいつは「今しかねえ」って、がーってなってる時があって。俺は「まあまあまあ。現実はさ」って知ったようなこと言ったと思うんだけど、加藤は普段そんなことしないんだけど、激高したことがあって。
加藤 そんなことあったっけ。
川瀬 今やらないと、みたいな時だったと思うんだけど。
加藤 逆に川ちゃんがすごく羨ましいっていうか、俺は田舎から出てきてるってのもあると思うんだよね。
川瀬 そうそうそう。
加藤 やるか、帰るか、みたいな。都会の人の余裕感というか、すごく好きな作品とか、敢えていうならアーティスト目線で好きなことをやるのがいちばんいいんだっていうのを崩さないスタンスっていうか。俺から見るとすごく憧れもあるし、でも「こっち側の視点持ったらもっとすげえところに行くんじゃね?」って気持ちもすごくある。
川瀬 あはは(笑)。売れたくないわけじゃないけど、責任ないところがいいんだよな。
加藤 周りからどんどん声がかかるってことはそれだけ良さが認められているってことだと思うんだけど、自分からもっとガツガツ行く人だったらたぶんもう地上波のそれこそ『バイプレイヤーズ』とかに出るようになるんじゃないかって。
川瀬 でもあの人たちをバイプレイヤーズって言ったら、僕なんか路傍の石ですよ。世間ってそれくらい浸透度が早くもあり遅くもあるんだけど、1コなんかあったらその人のバックグランドなんか関係なくコロコロコロって行っちゃうんで。逆にいうと、俳優部やって20代とかにピーク来なくてよかったなって思う。要するに、自分がイイ歳になって劣化して、劣化って元がどれだけ良かったって話なんだけどさ(笑)
加藤 いやあ、良かったですよ(笑)
川瀬 そうなってヤレてきてから夢とか希望とかそういうこと言わないで。俳優仲間の渋川(清彦)君とかと飲んでても、保険の話とかさ、そういうことできるようになった時に、「なんか今、俺、職業になってる」って思えるようになった。
加藤 やべ。俺、最近なんか涙もろくなってるから。たぶんそういうタームなんだよね。
川瀬 たぶん更年期なんだと思うんだけど(笑)。でもこういうトークするなんてさ、昔じゃ考えられなかったもんね。
スカという音楽
加藤 映画ってヒットするしないとか作品の収益がメインじゃないですか。ミュージシャンはコンサートというか興行があるんで。プロレス団体や昔で言ったらサーカスとか、そういう文化なんですよね。地元を回ったりして直接お客さんに届けるみたいな。それはヒットチャートとは違う文化というか。でもヒットしてたらそっちにもつながってくるから嬉しいんだけど。今はどっちかって言うと、ミュージシャンはヒット曲云々というのもすごく大事なんだけど、自分たちを見に来てくれてるお客さんをどれだけ楽しませられるかとか。直接会うコンサートの延長線上にフェスがあるっていう風に思うから、ヒットの在り方にしても。
川瀬 バンドのジャンルで言っても、ヘヴィメタルも海外でもツアーできるわけじゃん。小難しいプログレにしても、そのコミュニティが各世界にあるからそれでメシが食えるわけだから。
加藤 スカもそうですよね。
川瀬 そうそうそう。ノイズとかもそうだし。
加藤 スカは今、メキシコが世界的にすごく聖地なんですよ。
川瀬 あ、そうなの、へええ。
加藤 だから毎年のようにメキシコに行ってるんですよ。8年連続で行ってて。で、去年、実はメキシコのグラミーみたいなのを獲ったんですよ。
川瀬 うわ、すごい!
加藤 アジア人では初で。ベストパフォーマンス賞にノミネートされて大賞をいただいて、レッドカーペットを歩いて。2000年代に僕らはヨーロッパを回ってて、十年くらい経った時にスペインで火が点いて、そしたらメキシコに来てくれ来てくれってずっと言われてて。同じスペイン語圏だから。「いやいやいや、メキシコに行って何があるの?」って思いながら2011年に初めて行ったら、何万人のお客さんがドーンっと。
川瀬 いいね、プロレスに似てるね。ルチャ・リブレ見に行ったらエラい盛り上がってるみたいな。
加藤 まさにそう。ミル・マスカラスが日本ですごく有名みたいな。
川瀬 グラン浜田だよ!
加藤 そうだね。長くなりそうなんでやめとこう(笑)。スカの聖地はかつてはロンドンだったり、ジャマイカだったり。
川瀬 スペシャルズとかな。スカタライツとかTrojansとか。
加藤 そうそうそう。とにかく今、スカのバンドがメキシコに集まってるんですよ。それがSpotifyとかで対等に聴けるじゃないですか、日本だけじゃなくて。そういう意味ではCDが売れないって言うけど、すごく夢のある世界と言うか。絶対数が日本列島だけじゃない、世界に広がっているっていうのは夢のあることだし。たまたまだけど、僕が加入した東京スカパラダイスオーケストラっていうのは、パフォーマンスを売りにするバンドだったっていうのがすごく大きくて。僕もライブはやっぱり大好きなので、そこは音楽の売れ方にいくつか通り道がある中で、ひとつ刺さっていくものがあるんだろうなって。
川瀬 変な話だけどさ、スカってなくならないじゃん。レゲエがなくならないように。アイルランドでチーフタンズがおじいちゃんになってもやってるわけじゃん。俺も一度はさ、音楽の才能あったらザ・ポーグスみたいなバンドでダラダラ一生送りてえなって思ったもんだよ。要するに好きなことをやって生きていくってことなんだけど。それはヘヴィメタルでもなんでもいいんだけど。


ずっと挑発していたい
加藤 音楽もねえ、ロックとは言ってるけど、僕らが聞いてたロックとはまったく違うから。ロックって昔、ワルかったんですよね。そのワルさも必要としていない、今の若者がね。
川瀬 今の世の中って、たとえば渥美清さんが生きてたら、絶対、渥美清さんの私生活を掘ろうとする。それくらい無粋なことが起きてる気がする。
加藤 たぶん、川ちゃんが担っている役者さんの中の立ち位置っていうのは、どっちかっていうと「清く正しく美しい」とは違うわけじゃないですか。
川瀬 分からないけど、どっか野蛮なところが残っててほしいっていうか。映画でも音楽でも。
加藤 ね!
川瀬 別に、誰かを傷つけるとかそういうことじゃなくて。挑発はしたいじゃん。
加藤 それはおもしろいね。
川瀬 挑発はしたいのよ。決して法に触れないように。
加藤 おもしろい。これはちょっと聞きたかったですね。
川瀬 一休さんのとんちみたいな。その手のことをやって「ぎゃふん」ってやれたらちょっと楽しいかなってのはある。
加藤 挑発したい、っておもしろいですね。
川瀬 俺らがやれることは挑発くらいで、ジョン・レノンさんみたいにアジテートして世の中を変えるっていうのは器が大きすぎるんだけど。ニール・ヤングみたいにただただガシガシやってるおじさんとかそういう人はいてくれなきゃ困るけど、俺の役目はたぶん挑発することだと思う。
加藤 ジョンはやり切ったあとですからね。すべての人間の欲をやりつくしてイマジン、みたいなことになってるわけですから。おもしろいね。ここにもう一人、20代くらいの役者さんなのかミュージシャンなのか、を入れて喋ってみたいですね。
川瀬 そしたらきっとおじさんの説教みたいになってめんどくせえなこいつら、って思われるんだよ(笑)
加藤 上からいくんじゃなくて、20代の子が思うワルっていうのが、俺らが思ってるワルとは違うだろうから。
川瀬 全然違うだろうね。
加藤 人間の悪い部分みたいなものを、「うわ、これはダメだけど分かる分かる。じゃあどうすればいいの」みたいなところを知りたくて映画を観に行ってるはずなんですよ。
川瀬 そうね。
加藤 そこがないと僕はやっぱり感動できないところがあるというか。小説でも何でもそうなんだけど。ただいいことばっかり言われてもそれは想像できるけど、なんでそうなったか、その裏側というかね、そこが描かれるほうがやっぱり感動が増すよね。
川瀬 そうそうそう。
自意識と表現の解体
加藤 スカパラはバンドの在り方自体が、メンバーが亡くなったり脱退したりとか紆余曲折があって。
川瀬 もうグレイトフル・デッドみたいなもんだよ。デッドヘッズもいてさ。
加藤 そんな感じそんな感じ。だから最近は歌詞とかも前向きなものが多いんですけど、もう歌詞でそこをえぐる必要もなくなってきたのかなって。30年やってる時点でそこは言わんでも分かるだろって話もあるから。でも20代の頃はみんなワルを演じるわけじゃないですか。
川瀬 それはそう見られたい自分っていうのがいるからだよ。
加藤 ホント、そこっすよ。
川瀬 そうやって昔のことを思い出して布団被って「ひゃー」ってしてないヤツって信用できないから。自分の美意識に超酔ったりとかしてる時間がないと信用できないなって気がしてて。自意識過剰な時が最高じゃん。痛々しいし恥ずかしいことを本気でやれてるのはミュージシャンだろうがなんだろうが、いいもん。
加藤 たしかになあ。カメラが並んでる中で演技するって、相当自意識を超えないとできないよね。
川瀬 それを会社レベルにしたのは永ちゃん(矢沢永吉)だからね。だって、ハングリーな自分で売ってきた人なのに、大成功して、アメリカにも家あるのかな、そこでインタビューしててさ。「俺、カネ好きよ」って。カッコいい〜。俺はまだハングリーなんだぜ、ってことなわけですよ。すげえなと思って。
加藤 かっこいいね(笑)
川瀬 永ちゃんが指針やなあと思って。日本のロックの中にはまあ近田春夫さんみたいな人もいるけど、あの人は要するにロックを解体する作業をしているけど、永ちゃんとか(内田)裕也さんとかいわゆる芸能の世界の中でやってる人って本当おもしろい生き物だなあって思う。
加藤 スカパラのメンバーは近田さんに近い人が多いのかも。解体っていうか。
川瀬 それはピチカート(・ファイヴ)とか出てきた時にやっぱ解体じゃん。
加藤 あの時点でレゲエとかスカを選ぶって、川上(つよし)さんとか青木さんはパンクが好きすぎてパンクをやるのが嫌だっていう。全身セディショナリーズなくらいパンク大好きすぎる中でパンクをやるのはパンクじゃないと。そこで何か他の音楽がないのか、っていうのがスカとの出会いだから。近田さんじゃないけど解体ですよね。ただ、逆に言うと今、ロックカリスマがスカパラにはいなくて。ロックカリスマっていうのは「自分、好き」で、自意識にどれだけ過剰になれるかみたいな。僕らがフューチャリングでゲストヴォーカリスト呼ぶじゃないですか。ヴォーカリストで成功してる人ってそれの極みというか。深い話になっちゃうけど、本当はもっと自意識過剰じゃなきゃ、って思うことってありますよ。
川瀬 ツッコまれる存在になることはいいことだよ。
加藤 ステージに立ってると、自意識度があの人が100だとしたら自分はまだ20くらいなんだろうな、みたいに思うことが。自分はけっこう強い方だとは思うんだけど。でも今、世の中に出てる人、テレビとかにガンガン出て、「私を見てください」っていう人はやっぱりそうなわけだから、生まれ持ったというわけじゃないけど、生い立ちとかで変わってくるんだよね。
「ズレたところに新しい自分ができるから。」(川瀬)
加藤 若いバンドがどんどん出始めてくる中でスカパラの立ち位置も今までとは変わってくるわけですよ。俺たちがもう創造もできないような音楽を20代30代がどんどん作り出していく。その中で、スカパラの一員として自分を俯瞰で見たときに、ギター弾いたり、作曲をする以外に何ができるのかなって考えると、バンドが前に進んでいくために転がしていく。「こんなことをしたらおもしろいんじゃない?」みたいな提案をする。そうすると、「それおもしろいね」「それおもしろいね」って9倍の大きさになっていく。それを自分にフィードバックするのが楽しいっていうのがすごくあって。今の僕の役割として与えられているのはそういう立場なのかな、と。若い頃は自分がどうなのかなんて分からないから、永ちゃんみたいにならなきゃいけないんじゃないかと思ってサングラスかけてた頃もあったけど(笑)。
川瀬 それでいうとさ、俺も“個性”っていう言葉にけっこう疑いがあって。要するに、昔は自分っていうオリジナルな存在を主張したいんだけど、9人体制のバンドに入ったらいわゆる一家になるわけじゃん。その時に機能しなきゃいけないタスクもあるし。増してやこれは勝手に言うけど、サポートで入ったら既存の曲をやる、誰かが弾いてた曲をやることがスタートじゃん。これって大事なことなような気がして。俺もなりたい自分がなかったから。だから若い子にお悩み相談された時に言うのは、「大丈夫、続けていれば絶対なんとかなる。だけど自分の思ってたそれじゃないかもしれないよ」って。
加藤 ああ、今すごいキーワード出た。僕らが今やってるツアータイトルが「ズレたままハジキ飛ばしていこう」っていうんですけど。
川瀬 なるほどなるほど。
加藤 「ツギハギカラフル」って曲の谷中(敦)さんの歌詞の一節からとってるんだけど。説明すると、渋谷ってずっと工事してるじゃないですか。汚いじゃないですか。新宿もそうなんだけど、こういう昔からの飲み屋街もあれば、近代ビルも建ち並んでっていう。ちょっとずつ継ぎ接いでできた東京っていう街があって。いちばん最初に夢を見てた人が思っていた街とは違うはずなんだけど、その夢を世代が受け継いで継ぎ接ぎの街を作っていく。誰かの夢を引き継いで次の人が継ぎ接いで夢になっていく。“ハジキ飛ばしていこう”っていうのはとりあえず頑張って漕いでたら違う未来かもしれないけど。
川瀬 それがまさにロックンロールなわけじゃん。ロックしてロールする。
加藤 つい先日のなんですけど、地元、鳥取での公演で2千人を完売したんですね。
川瀬 加藤が鳥取のヤツらとバンド組んでた頃は「東京で鳥取出身のヤツは顔分かる」って言ってたよね(笑)。そんなワケねーだろって言って!
加藤 でもホントそうなの、そんなレベルなの!鳥取の2千人って東京の4万人と同じレベルだと思ってて。で、デビュー30年目で初めてソールドアウト、ってなるじゃないですか。でも自分が昔思い描いてたギター像っていうのはスカじゃなかったから、やっぱズレちゃってるんだけど、川ちゃんが若い俳優さんに言ってる話と同じで、ずっとやってたらなにかしら正解が、光が見えてくるよみたいな。
川瀬 ホントにね、自分ひとりじゃできないんだよね、たぶん。
加藤 関わる人が変わってくるとまたズレてくるから。
川瀬 そうそう。ズレたところに新しい自分ができるから。畑引っくり返すじゃないけど。ある種さ、俺は俺に飽きてるんだよ。リフだって自分の中に出てくるものって限界がある。だから人からの強制じゃないけど、時代の流れもそうだし、人によって新しいものに出会うから。
加藤 川ちゃんだって元々は助監督やってたのが、「役者やってみない?」って一言でそっち側に行ったんだもんね。
川瀬 長渕剛のCD持って東京出てきたような人のほうがよっぽど気持ちは強いのよ。
加藤 僕もそのひとりですけどね(笑)
川瀬 気持ちは強いんだけど、役者でも音楽家でもそうなんだけど、それこそ今も高円寺にいっぱいひしめき合ってると思うんだけど、それは自己実現なんだよ。俺は映画が好きだから続けてられる。自己実現ってある時折れるんですよ。「あんな奴が主役やって。俺がやったらもっとすげえ」とか、そういうことを言って20代を暮らし、30代になってきた時に自分がどうも“the One”じゃないことを外的に知らされるわけですよ。がっちりした芯を持ってたヤツってぽっきり折れるんですよ。俳優がいなくなる時っていうのがあって、すげえガンガンいってたヤツがある時音信不通になるんです。俳優事務所にはまだ所属の写真が残ってるんだけど、結局仕事らしい仕事はしていない。その間には一時期、劇団を立ち上げたり、自分ができるところでっていう悪あがきをする。で、ある時に音信不通の3、4年がある。で、ある時にFacebookに友達申請が来る。その肩書きがなんとか株式会社のなんとかって役職になってて。その時に俺は「ざまあみろ」とは思わない。「なんだ、お前一緒に遊んでたのに、やめちゃったのかよ」と。他には、地上波ドラマとかに出たりしたらLINEに突然、昔一緒のお仕事した女優さんから「静岡で見てます」って来たり。泣けてくるのよ。『北の国から』みたいな。そうやって討ち死にしたり、場合には物理的に死んじゃったりしたヤツらがいっぱいいるから、その人たちのためにもやめられないっていうのは自分の原動力の中にある。
加藤 あるある。それで言ったら、最初のlost CANDIのメンバーもいるし。それの繰り返しっすよね。
川瀬 続けられる人が続けていけばいい。俺はそう思うよ。


■川瀬陽太
1969年神奈川県出身。
自主映画の助監督からキャリアをスタートさせ、1995年の映画『RUBBER‘S LOVER』(福居ショウジン監督)で主演デビュー。その後瀬々敬久監督をはじめ膨大な量のピンク映画に出演、そこから現在に至るまで自主映画から大作までボーダーレスに活動している。主な出演作に『ローリング』(15)、『シン・ゴジラ』(16)、『バンコクナイツ』(16)、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(17)、『羊の木』(17)、『月夜釜合戦』(17)、『菊とギロチン』(18)、『blank13』、『天然☆生活』、『ゴーストマスター』、『AI崩壊』(20)TVドラマ「anone」(18・NTV)、「ひとりキャンプで食って寝る」(TX・19)など。
■加藤隆志
1971年鳥取県出身。
日本だけでなく世界各国で活動する、大所帯スカバンド、東京スカパラダイスオーケストラのギター担当。
サポートギターを経て、2000年に東京スカパラダイスオーケストラに正式加入。
スカパラの他にもドラマー中村達也とのセッションや、フィッシュマンズ茂木欣一、柏原譲とのバンドSo many tearsとしても活動。
熱い演奏スタイルに定評があり、激しいライブパフォーマンスで世界中のオーディエンスを魅了している。