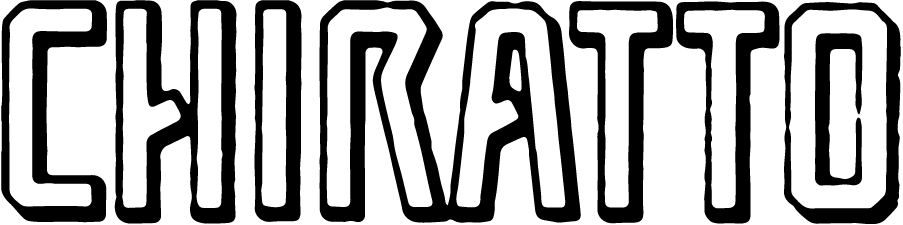第十七回特別インタビュー 長久允(映画監督)×湯川ひな(俳優)

CHIRATTO第十七回特別インタビューのゲストは、映画監督の長久允さんと女優の湯川ひなさん。
2016年に短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』で出会い、3月29日より放送が開始したWOWOWオリジナルドラマ「FM999 999WOMEN’S SONGS」で再び「監督と主演女優」としてともに作品づくりに携わったおふたり。
2020年のコロナ禍で改めて考えることになった「演技をすること」「物語を書くこと」についてなど、たっぷりとお話を伺いました。
不機嫌な表情、ふたつの世界

──おふたりの出会いからお聞きしてもいいですか。
長久允(以下、長久):あれは何年だろう、2016年とかだよね。『そうして私たちはプールに金魚を、』(以下、『プー金』)という短編映画をつくろうと思って、シナリオが書きあがった段階で主演を探してたんですけど。僕はもともと監督じゃないので、役者を知らないし事務所とのつながりもなかった。それで各事務所のホームページを見て探してたら、ひとりだけ異様に不機嫌な顔をしてるアー写があって。ぜんぜん笑ってないのがいいなと思ったんです。もう会う前からこの人はあかね役だと思って、「あかね役をお願いしたいんですけど会えますか」みたいな感じで事務所の方に頼んで会わせてもらって。でも会ったときすごいだんまりしてたよね?
湯川ひな(以下、湯川):ははは。
長久:でもだんまりしてるのもいいなと思ったからそのままお願いして、『プー金』を撮影したっていう感じですね。だからオーディションすらしてなかったです。どんな気持ちでした?
湯川:そのときは「演技をしたい」とか、そういうことを深くは考えてなくて。学校がちょっとあんまりうまくいってなかったので、新しい大人と出会えたことが本当にありがたかったですね。見つけてくれてありがとうございます、という思いでした。
──学校とは別の居場所ができて。
湯川:ふたつの世界があったほうがよかったんだと思います。学校だけだったときは、どうやって人とのつながりを生み出していいかわからなくて、それからすごく人間不信みたいになっていたので。だけど仕事の世界は大人しかいないから、大人はあんまり小さいことを気にしないし。「自分らしくいられた」っていうよりは、「ふたつの世界があることで自分を保てていた」っていう感じだったんですよね。
長久:大人は干渉してこないもんね、深くは。
湯川:中学校でみんながギラギラしはじめるときに自分はちょっと追いつかなくて、ほんと干渉してくるっていうか。それが大人にはなかったから。『プー金』のスタッフの方々が面白いと思うことを私も面白いと思えたりして、いろんな外の刺激を受けられたのがよかったですね。10日間だけでしたけどすごく楽しい撮影でした。
──不機嫌な表情をしたアー写が長久さんの興味を惹いたというのはご存知でしたか?
湯川:そうですね、聞いてはいました(笑)。でもそのときはほんとにカメラの前で笑ったりとかがぜんぜんできなかったので。
長久:ぜんぜん笑わなくたっていいですからね。日常でキラキラと笑うことなんてあんまりないと思うし、そういうものが現実として比較的苦手でもあったので。普段から演技をやっている人より役に合ってると思ったし、人としてなんかすごく気になったんですよね。別に機嫌はいつもいいと思うんですけど、不機嫌な表情のなかにもひなちゃんにはチャーミングさがあって。そこには才能とか魅力が必要になると思うから、それができるっていう人はあんまりいないよなと。今回の「FM999 999WOMEN’S SONGS」(以下、「FM999」)はちゃんとオーディションをしてたくさんの人に会ったんですけど、それでも最終的に主演がひなちゃんになったっていうのは、そういう魅力に惹かれた部分があったからでした。
──『プー金』の撮影当時のことってはっきり覚えていたりしますか?
湯川:仲良くなるために(女子中学生役の)4人で合宿をしたんですけど。あれは監督のご実家でしたよね?
長久:あー、そうそう実家実家。4人バラバラの人たちをキャスティングしてたから、現場の期間だけでは友だちに見えないかもなと思ってね。一泊してもらって焼肉行ったり、カラオケ行ってみたりして。
湯川:あれは今考えるとすごく面白いことをやってたなって思います(笑)。でも監督とこんなに長く関わっていくと思ってなかったので、もうちょっと家の中を見たりすればよかったなって…。
長久:手応えとしては1日ではやっぱり短くて。もしかしたら監督の僕だけがはしゃいでてみんなにはマジ気持ち悪い大人だと思われてたかもしれないけど。
湯川:ははは(笑)。
言語感覚と身体感覚とギャグセンの的確さ

──先ほどの、「スタッフの方々が面白いと思うものを自分も面白いと思えた」というと、たとえばどういったものだったのでしょう。
湯川:私はけっこうそれまで理性的に生きていて、そういう理性とは反するものをちょっと恥ずかしいと思っていたんです。でも一方で心のなかには「こんなことを人前でやっちゃいけない」っていうことをやりたくなる衝動みたいなものもあって。それを発散していくことが芸術にはできるので、芸術にもただ美しいものや理性的なものを求めているものもありますけど、そうじゃない表現をしている人たちの存在を大人のみなさんが教えてくれたというか。たとえばNATURE DANGER GANGとかも、私が普通に生きてたら出会えなかったと思うんですけど、長久さんが教えてくださったことによって出会うことができたり。
長久:すごい極端な教育をしてるかもね(笑)。『プー金』のテーマ曲を歌ったり出てもらったりしてたんで、撮影中にライブに連れていったりしたんですよね。4人がみんなポカンとしてたんで、またキモがられてんなって思ってたけど。
湯川:あのときはどう体を動かしたらいいかとかもわからなくて、興味深く見てたって感じでした。監督が(ライブハウスの)前のほうで揉みくちゃにされてて。
長久:汗だくで戻ってきたあとに「どう?」なんて聞いたりして、「いや、どうとかじゃないし」みたいな顔されてたと思う。
──怖いですね(笑)。
長久:怖いですよね。15歳とかに見せるものではないですからね、普通。
湯川:でもそういう新しいものを教えてくださって、その表現のあり方を私もいいなと思って。現実に響くことを伝えてくれるんだけど、でも非日常にも連れていってくれるような。そういうものをつくっている人たちとか文化を知れたっていうのは、すごく大きなことだったと思ってます。
──完成した『プー金』をご覧になったときはどう思いましたか?
湯川:学校で私が感じてることと近すぎて、「知ってるし」って、「別にこの気持ち珍しくないし」ってちょっと反発して思っちゃったんですけど。それを女子中学生じゃない長久さんが描けるのは今思うとすごいことだなって。しかもあれだけリアルに見せられるってすごいなって、今は思いますね。でもそのときはほんと当事者すぎて「知ってるし」って。懐かしい気持ちにもならないし。
長久:あははは(笑)。そうですよね。青春映画って当事者にとってはそういうものなんだよね。
湯川:大人が観て感じるものがあるのかなって。
──それくらい自身の学生生活に切迫するものがあったんですね。
湯川:そうですね。友だちに対しての思いとか、自分が普通であることに悩むとか、その感じはすごく共感しました。
──長久監督にとって、湯川さんの演技の魅力はどんなところにあったのでしょう。
長久:ふたつあるんですけど、まずは声がいいです。ぜんぜん乗っけてこない声というか、盛らない感じで喋り続けたりとか、あとテンポ感がよかったり。キーとテンポ感が僕のシナリオのセリフとマッチするから、そこがすごく好きなのと。あとは「こういうポーズして」みたいな指示をしたときに一発で理想形の10%増しみたいなのをやってくれるんですよね。ポージングってすごく難しいと思ってて、「ここで棒立ちでマイクを見て」とか指示しても「その見方いいね!」ってなることはあんまりないと思うんです。ドンピシャで感覚が合うっていうのは十何年CMプランナーをやってきてもまったくなかったのが、それをひなちゃんはできるから。だから言語感覚と身体感覚とギャグセンみたいなものが一致する感じがして、そこがすごく大好きですね。
──ミニシアターエイド基金のリターンとして制作された短編の『心臓2つ/父と歴史』とかは、まさしく湯川さんのその特異さが堪能できる映画だったと思います…。
長久:ああ、珍しいですねそれ観てるの(笑)。iPhoneで連絡しあって、動画を送ってもらってみたいなだけでつくった。ああいうことを100本ぐらいやりたいですけどね。
演技をすることは「生きる」ってことと限りなく近いのかもしれない

──その短編もそうですけど、『プー金』から「FM999」に至るまでも定期的に何度かご一緒されてるんですよね。
長久:この5年間、大きい作品はやってないというか、『WE ARE LITTLE ZOMBIES』にも出てもらったりしたけど2シーンとかだったんで。僕はひなちゃんがハイバイの演劇に出演したりして活躍してるのをずっと遠くで見てたっていう感じなんですけど。なんか面白いですよね、芝居に興味ないと思ってたから。
湯川:なかったです、ほんとに。
長久:そうだよね。だから興味の出し方がちゃんと舞台や演劇の方向に向いていくということが興味深くて。自然な流れだったのかもしれないけど、演技に対してどう思いながら稽古とかやっているのかなーとは思ってましたね。お芝居への思いが変わることってあったんですか?
湯川:すごく大きく変わったのが去年、やっぱりコロナ禍になってからだったんですけど。私はそれまで演技はちょっと恥ずかしいものだと思っていたりして、あと人前に出ることがほんとにしんどくて。でも大人や好きなものに出会えるのはいいことだから、そのいいことと嫌なことの間でずっと葛藤があって、やりたいことがいまいちわかってなかったんですよね。そんななかコロナウイルスが流行って、自分が出ようとしてた舞台も2本とも中止になって、2020年はまったく演技を実践的にやらなくていい年になったんです。それが自分のなかで久しぶりだったこともあって、遠くから客観的に演技について考えられるようになった期間でした。同時に、これまではちゃんと考えたことがなかったけど、政治を含め社会には問題がたくさんあって「このままでいいのか」って思うことがコロナ禍で特に浮き彫りになっていくのを知るようになりました。自分が生きていくうえでどうしたいかって考えたときに、別に当たり障りなく生きていくこともできると思うんですけど、そうではなくしっかりと問題に向き合って、「自分はこう思ってる」ってことを人前で言える人間でありたいなとそのとき思って。そう思ったときに、俳優をやってることはひとつのきっかけになるなって。だからどうしても演技がしたいから俳優をやるっていうよりは、いずれはそういうことも伝えられる人間になりたいからきっかけのひとつとして今は俳優をしている、そう捉えるようにしたらちょっと楽になって。そこからは大学で演技論の授業を取ってみたり、2020年は演技についてしっかり勉強し直す年になったんです。そしたら、演技をするということはなんだか生きるっていうことと限りなく近いんじゃないかって気づいたりして。
長久:めちゃくちゃ聞きたいな、その演技論(笑)。
湯川:自分の中にある衝動とかをどう扱っていくかとか、自分をどう見せたいかとかが「演技」につながるのかなと思ってたんですけど、もっとなんというか、人は常に演じているんだよな、とか思ったり。……それからいろいろな考えを経て戯曲というもののあり方にすごく興味を持って。私はよく言葉が詰まってしまって思ってることが言えないことがあるんですけど、それって言葉に囚われすぎてるんじゃないかって気づいたんです。言葉はただの記号でしかないのに、それに自分がすごく支配されている気がして。そこから言葉とか戯曲っていうものに興味を持ちはじめて、戯曲は演技とも近いものになっていくから、もしかしたら演技をすることによって自分の生きづらさが解消されるんじゃないかっていう希望が見えたり。なんかいろいろ本を読んだりしていると、やっぱり演技をすることは生きるってことと近いんじゃないかなって……。うまく言えなくてごめんなさい(笑)。
長久:ぜんぜん。なんか戯曲書いてみてほしいですけどね。ひなちゃんが何を思っているのか、それを自らの演技として表現してみてほしい。演技って知れば知るほど考えるノズルが増えまくるからさ、『プー金』のときはただセリフを言わされていただけだったのが、一歩踏み出すと限りない荒野を進むことになると思うんだけど。すごく大変だよね(笑)?
湯川:そうですね。言わされてたときには戻れなくなっちゃうから。
長久:そうそう。一歩踏み出したらもうぜんぶ完璧にできなきゃいけないとすると、「キリがない旅を始めだしたんだな」って思って、大変だなぁって(笑)。
湯川:でもその、答えがないのがやっぱりいいなって思ってます。
長久:そうなんだよね。技術を追い求めるともうこっちには引き戻れなくなるから、たとえばギターうまくなったうえでジミヘンにどういくかとか、ジャズミュージシャンとしてマイルス・デイビスにどういくかとかまで考えないといけないから始めるとまじで道が長くて。かつて子どものようにやっていたことに技術を身につけたあとに再び到達することってすごく難しいから、でもそれを追い求めたほうが人生は楽しいし。なかなかゴールはなくて、ゴールはスタート地点にあったりもすると思ってるんだけど。そうですね、旅をはじめたんだなって、感慨深いです。
役者に身を委ねてみること

湯川:長久さんはずっとこれからも書き続けるんですか?
長久:うん、書き続けますね。書くのが一番好きなんだよね、シナリオを書く行為が。でもなんか、ひなちゃんがその旅を始めてから僕も変わってきてる気がしてて。
湯川:だと思いました。
長久:え? 変わったと思った?
湯川:はい。
長久:そうか。一緒に変わっていこうかなって思ってるんですけど。
──湯川さんは「FM999」の撮影中に「長久さん変わったな」って思われたんですか?
湯川:そうですね。人物の描き方が変わったなって思ったりとか。それこそ「セリフを言わせる」っていうのが長久さんは巧いなって思うんですけど、なんにもその子に技術がなくても成り立たせることができる人だなって思うんですよ。だから私も『プー金』に出られたと思うんですけど、でも今回はもうちょっと役者の演技に委ねるというか、演出してくれたのがあって。いわゆる「ドラマっぽい」というか、そういうものを描いていたのはもしかしたらちょっと変わったところなのかなって。
長久:そうだよね。そう思う。言葉でかなり強くしてあるから、緻密な設計がなくても成立するつもりでは書いてるんですよね。逆に、緻密な設計をすると強すぎちゃうというか。それが、去年の9月に「(死なない)憂国」っていう舞台を東出(昌大)くんと(菅原)小春さんでやったんですけど。あれはもともと、セリフを淡々と早口で読むだけにしようと思ってたんです。でも1か月間ふたりと稽古を積み重ねていくと、むちゃくちゃ抑揚をつける方向に、思ってたのと真逆のほうに到達して、でもそれが正解だったなって気がしてて。その経験を経て、セリフを渡して役者が自分のものとして増幅させていく、そういうことを今後はもっとやっていこうかなと思ったんですよね。元来は役者に対して「そのままでいい」っていう信頼があったんですけど、役者という生業の方々にある程度身を委ねて人間を新たに描いてもらうことの面白さを初めて知ったというか。そういう信頼の置き方があるんだなって。それを「FM999」と4月にやるミュージカル(「消えちゃう病とタイムバンカー」)でもやろうと思ってるんですよね。どちらの作品も「演技をやったことがない人」にもたくさん参加してもらってるので、これまでどおりの演出と新しい演出をどっちも混ぜながら楽しんでやっていきたいなと思ってます。
湯川:「FM999」は歌手の方とかダンサーの方とかもたくさん参加されていて。私は毎日そのお芝居を興味深く拝見したんですけど、普段演技をしていない方たちのそれはすごく斬新でキャッチーだし、俳優が想像できないような表現をしてくるんですよね。
長久:普段演技をやってない人たちはすごく勘が動物的で、全体を通してエネルギーがすごく高くて。一方で役者さんは一文一文の意味と単語と間をロジカルに詰めてくるから、機能が違う感じがして見てて面白かったですよね。どっちもできるようになるといいけどね。
湯川:そうですね。
長久:超難しいけど。
──「FM999」では宮沢りえさんや真矢ミキさんといった大女優の方々から歌手やお笑い芸人、ダンサーといった個性あふれるキャストのみなさんと演技をされたと思うのですが、どんな刺激を受けましたか?
湯川:そうですね。一緒に映るわけではなくて、私はカメラに映らない状態でセリフのやり取りをしていたので、特等席みたいなところに座って目の前でその方が演技したり歌ったりしてるのを見るっていう時間はすごく面白かったですね。私はボケーっとしててもカメラには映らないから(笑)。もちろんちゃんと演技はしますけど、そんなに気を張らないでいい環境だったので「こうやって演技するんだ」っていう発見がいちいちあって勉強になりました。
長久:(湯川ひなさんが演じる)清美が物語上でもそうやっていろんな女の人に話しかけられ彼女たちの歌を見るっていう設定だったから、現実のひなちゃんのあり方とリンクしてる感じになってたよね。
湯川:そうでしたね。あとは、みなさんテレビでもともと見てる方たちだったので、演技をしてないときの過ごし方とかをこっそり観察してました(笑)。
長久:あんな人たち見るチャンスないもんね。なんて贅沢な時間を、って僕も思ってましたけど。
──特に印象に残っている共演者の方とかいらっしゃいますか。
湯川:印象に残ってる……。みなさん「この方はどうでしたか?」って聞かれたら全員答えられるくらい印象に残ってるんですけど。私は宝塚が好きなので真矢ミキさんとお会いしたときにドキドキして楽しかったり…。
長久:真矢さんはあんなにアグレッシブで革新を求めている人だって思ってなかったからびっくりした。
湯川:わかります。
長久:違う人用に準備して置いてたウィッグとかを「え、被りたい!」って言って被ったりして、「いいなー」とか言ってて。役では普通の真矢さんのイメージとはちょっと違うものをお願いしてたんですけど、さらにそれをもっと超えたいみたいな感じだったから、ああそういう方なんだって思って。すごい面白かったですね。それぞれみんなベクトルが違って。
マクドナルドで号泣しながらシナリオ書いてる

──「FM999」の清美の設定が「16歳を迎えたばかり」で、湯川さんご自身は「20歳を迎えたばかり」だと思うんですが、そのあたり役に対して感じることはありましたか?
湯川:もう16歳のときの混沌とした気持ちっていうのは一旦超えて、私はだいぶ落ち着いて生きてはいるんですけど。でもそのときの気持ちは結構思い出すので、今はもう自分のなかにはないけど、そういう子どもでもないし大人でもないなんと定義していいかわからない状態を想起したりしながら16歳を演じていました。
長久:それはすごいですよね。俺は16歳とか13歳のときとなんら成長していない気持ちで36歳になってるから、それが言えるのってすごいなって。
湯川:でも周りからは「允が思春期になって」みたいな感じで言われてたんじゃないですか?
長久:でももともと反抗期もないしほんとあんまり変わってないんですよね。さっき言ってた「大人でもないし子どもでもない」みたいな状態のまま保存させてもらってるような(笑)。
──それがすごいですよね(笑)。
長久:むしろやばいんですけど。だからひなちゃんが「20歳で変わった」とか言ってるから何が変わったの?って気になる(笑)。昔がやばかったの?
湯川:う〜ん。前はもっとちっちゃいことで憤慨してたっていうか。実際には表に出さないし、感情的になるのは恥ずかしいと思ってたから外ではそういことはできなかったんですけど。でもやっぱり身内とかに対してはもしかしたら出てたかもしれないし、心のなかでもすごく細かいことに「は?」って思ってたり。
長久:はは(笑)。思っても別にいいと思うけどね。
湯川:そういうことがあったなって。今はそんなことどうでもいいって思えたりするんですけどね。
長久:あーでも、僕は働いて10年くらいすごく抑圧されて過ごしたから、そのときはそうだったのかも。それを経て、ツラくても「は?」って思わないとか上手に生きるのとかがしんどくなって、そこからもう「そういう生き方やめました」ってしたから、今16歳に戻ったのかもね。のちのちツラくなるよ、それ。
湯川:あー。
長久:大人はまじでツラいから。ツラくなったらいつでも、こっちに来なよ。
湯川:あははは(笑)。そうですね。それはまた第3段階かもしれないですけど。私はまだ第2段階で。
長久:そうだね。「長久あんなこと言ってたな」って思ったらこっちに来ればいいよ。でも俺もまた40歳になったらどうなってるかわかんないからね。
──大人になっても16歳のときみたいでいられるっていうのが面白いですよね。
長久:なんですかね、シナリオをマクドナルドで号泣しながら書いてたりして、すごいやばい客なんですよ。
湯川:えー(笑)。
長久:それはもう16歳とかでもなく新たな精神段階にいってるのかもしれないけど(笑)。
表現の手段としての、「物語」「演技」

──清美が「女とは?」と問うことでいろんなゲストが登場して歌を披露しはじめるという「FM999」の世界観ですが、フェミニズムを謳う本作のテーマ設定に関しては湯川さんはどう思いましたか?
湯川:企画書を読んだときに、それこそ私も社会に対して思っていたことがいっぱいあったりしたので、こういう作品がもっと増えればいいのになと思いましたね。
長久:難しいよね、このドラマ。そもそも「女とは」みたいなものってカテゴライズするべきじゃないことはわかってるんですけど、問題定義をしないと議題にも上がらないから一段階飛ばしていて。前段階としてはもちろんそれぞれ一個人だからジェンダーで定義すべきではないってことがある。でもそれを入れるとひとつのドラマでは語りきれないから、視聴者の心のなかで前提を踏まえたうえでお届けすることになる。だから基礎となる考え方が下手したら抜け落ちたまま受け取られてしまう可能性があって、それに対してはちょっと不安はあるんですけど。ただ、やらないよりはやったほうがいいよねって感じではいますよね。
湯川:作品の社会的に伝えたいメッセージだけが前面に出てるわけではなくて、フィクションとしてもすごく面白いと思っていて。テーマは伝わる人にだけ伝わればいいし、そうじゃなくても普通に物語や音楽を楽しむことができるっていうのがいいところだと思います。
長久:そうかもしれないね。ありがとう(笑)。
湯川:あはは(笑)。
長久:そうそう、そのつもりで書いたわ。
──おふたりが今後どんなふうに物語や演技に関わっていかれるのか、とても楽しみです。
長久:やっぱり僕は物語をつくる前提に、社会や世の中のよくない状況、改善されるべき問題というものがあって。ある価値観を提示することで生きづらい人の何かが少し好転するように物語をつくりたいっていう思いがあるので、今後もそのために物語は柔らかくなきゃいけないと思っていて。「物語のために」セリフを書きたいっていう思いはないから。その意識をちゃんと忘れずにいたいと思いますね。
湯川:私はまだ先のことは考えてないんですけど、とりあえずどう生きていくかって考えたときに、社会的な問題があって苦しんでる人がいるならば手を差し伸べられる人間でありたいので、自分の行動に説得力を持たせられるようにまずは演技の勉強をしたりして。とにかくまだまだ知らないことがたくさんあるので、社会のこととか学校のこととか、いろんな方面で勉強して、それで私がまたちょっと成長したら何年後かに長久さんと。
長久:あ、けっこう先なんだね(笑)。できるといいですね。ひなちゃんは同じフランス文学科だから、なんというか同志みたいな気持ちでもいて。ひなちゃんがやりたいような、今必要だと思うようなことを発散してみてほしいっていう気持ちがあるんだよね。それは物語だったり詩だったり歌だったり身体表現だったり演技だったりしていいと思うんですけど。今取り込んでるものを、僕とかのフィルターを抜きにして素直に表現したらどうなるのかなって。
湯川:そうですね、自分が発散していく媒体として俳優にはこだわってないですけど、まずは演技のことを突き詰めて楽しんでみようと思います。

長久允(ながひさ まこと)
1984年8月2日生まれ。東京都出身。CMプランナー、映画監督、映像作家。大学卒業後、電通に入社。NTTドコモの“ドコモダケ”シリーズなどの広告を手掛け、2013年に世界最大級の広告賞と言われるカンヌ国際広告祭のヤングライオンフィルム部門で日本人初のメダリストとなる。2016年の短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』では、第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞。さらに、2019年の長編映画デビュー作『ウィーアーリトルゾンビーズ』(監督・脚本)も第35回サンダンス映画祭で日本映画として初めて審査員特別賞のオリジナリティ賞に輝いた。4月には、ミュージカル「消えちゃう病とタイムバンカー」(作・演出)の公演を控える。
湯川ひな(ゆかわ ひな)
2001年2月26日生まれ。東京都出身。2014 年、テレビCM“ミサワホーム”でデビュー。2015年には映画『あえかなる部屋-内藤礼と、光たち』で等身大の役を演じ、女優としてのスタートをきる。2016年、短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』で主演を飾り、第33回サンダンス映画祭短編部門に正式招待され、日本作品で初めてグランプリを受賞した。その他の主な出演作に、テレビドラマ「一番電車が走った」(2015)、「受験ゾンビ」(2019)や、『バースデーカード』(2016)、『ウィーアーリトルゾンビーズ』(2019)、『ショートムービー 心臓二つ/父と歴史』(2020)などがある。


■「FM999 999WOMEN‘S SONGS」
3月26日(金)より配信中
毎週金曜配信[無料トライアル実施中]【WOWOWオンデマンド】
3月29日(月)より放送中
毎週月曜よる9:30より放送【WOWOWプライム】(全10話)
※【WOWOWオンデマンド】2021年1月13日(水)にWOWOWオンデマンドがスタート。BS視聴環境が整っていなくても、インターネット環境があればWEB上で加入することが出来るようになる。これにより、放送と配信の垣根が消え、TVでもスマホでもWOWOWのサービスが気軽にご利用いただける。合わせて、放送同時配信、ライブ配信、アーカイブ配信、オンデマンド限定配信コンテンツなど多様な配信サービスを利用できる。これに伴い、オリジナルコンテンツの配信も強化。オンデマンド専用コンテンツなど充実させていく。オリジナルドラマや海外ドラマの一挙配信、スポーツ中継での複数コート同時ライブ配信や関連番組の配信などWOWOWならではの楽しみ方を提供する。さらに、配信加入ルートにおいては申し込み月内であればいつでも解約可能となる無料トライアルを開始。WOWOWのコンテンツに今まで触れたことのない方でも、気軽にWOWOWを体験できるようになる。
脚本・総監督:長久允
演出:中村剛、大熊一弘 音楽:三枝伸太郎 音楽プロデュース:愛印 制作プロダクション:ギークサイト
制作協力:電通 製作著作:WOWOW
特設サイト
https://www.wowow.co.jp/drama/original/fm999/
出演:湯川ひな 岡部たかし 倉悠貴/ TARAKO
【第1話ゲスト】宮沢りえ メイリン 菅原小春
【第2話ゲスト】塩塚モエカ 太田莉菜 八代亜紀
【第3話ゲスト】モトーラ世理奈 後藤まりこ ともさかりえ
【第4話ゲスト】アオイヤマダ 三浦透子 ゆりやんレトリィバァ