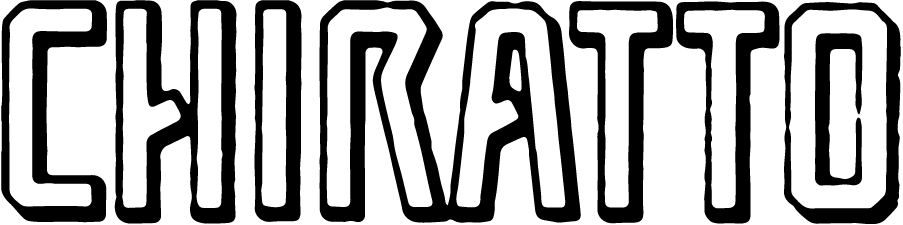第十四回特別インタビュー 温水洋一(俳優)

CHIRATTO第十四回特別インタビューのゲストは、俳優の温水洋一さん。
演劇との出会い、大人計画への入団、なぜバラエティに引っ張りだこになったのかなど、衝撃のエピソードとともに大いに語ってくださいました。
高校時代は『ガラスの仮面』のような演劇をしていました。

── 温水さんはどんな子どもだったのでしょう。
温水洋一(以下、温水):親が心配するくらい引っ込み思案な子どもでした。体もあまり丈夫ではなく、よく風邪をひいていたし、今でも細いんですけど栄養失調じゃないかっていうくらいやせ細っていて、病院で診てもらったほどでした。率先して前に出るようなタイプでもなく、野球とかドッジボールとかみんなで集まってやるようなこともあまり好きではなかったですね。
── ひとりで何かをするのが好きだった?
温水:小学校低学年の頃は、粘土遊びとか絵を描いたりすることは好きでしたけど、ひとりでというより同じような子が集まって、それぞれ黙々と遊んでいる感じでした。当時はゲーム機もなかったので、自分たちでルールを作ってビー玉とかで、ちまちま遊んでいましたね。そのうち親から、剣道の道場とか卓球教室に通わされるようになりまして。卓球は楽しかったのですが、剣道は朝練が週3回あって早起きするのが本当につらくて。父から5時半に叩き起こされて、冬は寒くて泣きながらやってましたね。おかげで大きな病気もせず、健康に育ったんですけど。中学に入った頃から、人前で何かやることが嫌いではなくなってきて。漫才ブームの頃だったので、テレビで見たお笑いに興味を持ち始め、高校生になると先生のモノマネをやるようになりました。といっても積極的に披露するわけではなく、「やれよ」と言われても「いいよいいよ」と遠慮しながら、家でしっかり練習しているタイプ。ウケるとしてやったり、みたいな。
── 演劇との出会いは、高校生のときだそうですが。
温水:高校2年生の終わりですね。同じクラスで思いを寄せていた子が美術部で、隣に演劇部の部室があったのですが、その子に「温水くんは演劇部に入ったほうがいいよ」と言われたんです。ひょっとしたら部活が終わってから、一緒に帰ることができるかもしれないっていう下心もあって、演劇部に入りました。
── 演劇に対して何かしらイメージはあったのでしょうか。
温水:『ガラスの仮面』が6巻くらいまで出ていた頃で、当時の演劇は女子がやるものというイメージだったんです。部員も女子15人くらいに対して、男子はたったの2人。3年生になる直前に入部したので活動期間も短かったのですが、男子が少なかったので大歓迎されました。演劇部に入ってみたら本当に『ガラスの仮面』の世界そのもので、エチュードで石になったり獣になったりして。発声練習や肉体訓練も初めての経験で、純粋にのめり込んでいきました。高2のとき、母親と妹と東京に遊びに行って、まだ薄っぺらかった『ぴあ』をたまたま本屋さんで手にして、記念に買って帰ったんですけど、なんとなく読み返していたら、演劇のことがたくさん載っていて。東京乾電池っていう劇団があって、そこに柄本明さんがいらっしゃることとか、竹中直人さんが青年座にいらしてとか、東京にそういう世界があることを雑誌を通して初めて知りました。それでわかりやすいんですけど、日大の芸術学部を受けようと思って、担任の先生に伝えたら「今から受かるわけがないだろう」と言われました。
── そのくらい演劇に夢中になっていたんですね。
温水:それでも受験してみたんですけど、結局ダメで。東京の予備校に通いながら、親戚のおじさんがやっている中華料理屋さんでバイトをさせてもらったのですが、新宿の河田町にあったフジテレビ旧本社ビルの目の前に、店を構えていたんです。『オレたちひょうきん族』のロケをフジテレビの近所でよくやっていたので、後々一緒にお仕事をすることになる明石家さんまさんをよくお見かけしたりして。フジテレビから出前が入ると、「僕が行ってもいいですか?」って岡持ちを担いで行くんです。それで『ドリフ大爆笑』の楽屋に行くと、志村けんさんの声が楽屋の中から聞こえてきて。上京早々、芸能の世界に触れられて、ただのミーハーでしたね。
── 勉強に身が入らなそうな環境ですね(笑)。
温水:そうなんですよ。上京した4月に、親からの仕送りで初めて観たのが、紀伊國屋ホールでやっていた東京乾電池の公演でした。今はなくなってしまった渋谷ジァン・ジァンという小劇場にもよく行きましたね。お金がなかったのでしょっちゅう芝居を観に行けたわけではないですけど、月に1、2本は行ってました。バブルで景気のいい時代で、大学に行く気もだんだんなくなっていたのですが、2浪して愛知の日本福祉大学に入学しました。いとこのお姉ちゃんが社会福祉の仕事をしていて、これからはそういう資格を取っておいたほうがいいと言われまして。そこでも演劇サークルに入って、のめり込んでしまうんですけど。
── 浪人中は観る専門だったのが、演じる楽しさもようやく味わえるようになったわけですね。
温水:4年生の6月、周りは就職活動をしているなか、自分は舞台を観たくて夜行バスに乗って上京しました。友だちのところに居候させてもらいながら、いろんな舞台を観て出会ったのが、大人計画だったんです。50人くらいしか入らない劇場でのレイトショーで、旗揚げ前のプレビュー公演でした。そのとき劇団員募集のチラシをもらい、愛知に戻って考えた末、7月に「まだ募集してますか?」と電話をしたんです。面接をするから来てほしいと松尾スズキさんに言われて、大人計画が稽古をしていた下北沢の集会所みたいなところでお会いして。そしたらこれまでの演劇経験などを聞かれて、「とりあえず明日から来て」と言われました。その頃には大学の授業もほとんどなかったので、3カ月間東京にいては愛知に戻ってという生活に。愛知にある荷物を月1万5,000円くらいの倉庫に預けて、親戚や友だちの家を転々としていました。浪人時代にお世話になった親戚の中華料理屋さんの片隅に自分のボストンバッグを置いて、毛布だけ借りて泊めさせてもらったりもしました。住み込みで働いている人もいたんですけど、今思うと迷惑だっただろうなと思います。
旗揚げする大人計画へ。福祉を学んだのに障害を持つ人の役なんて……。

── 大学を卒業したら役者としてやっていこうと思っていたのでしょうか。
温水:職業としては考えていなかったけど、とりあえず舞台に立ちたかったんです。当時の大人計画は劇団員がまだ5人くらいしかなかったんですけど、7月に入ってすぐに稽古をして、8月の終わりに旗揚げ公演がありました。たしか4ステージくらいだったのですが、それが終わったら解散して、次の公演がいつになるかもわからない。親や周りの人からも、せめて大学は卒業したほうがいいと言われて一旦愛知に戻って、3月の公演が決まったからとまた招集がかかったりして。小さい劇団はどこも似たような感じだったのでしょうが、当時は大人計画が今みたいに大きくなるとは思わなかったし、芝居ができること自体がとにかく楽しかったですね。
── 旗揚げ当時の大人計画は、どんな劇団だったのでしょう。
温水:当たり前ですけど、お金をいただいてやる芝居だから、大学のサークルのレベルとはまったく違うし、プロの照明さんや音響さんがいて、演出をちゃんとつけてもらえるのも初めての経験だったので、楽しくて。何よりも一番驚いたのは、おしゃれなにおいがしたことですね。当時の松尾さんはシティボーイズとか宮沢章夫さん、竹中直人さんなどの影響を受けていましたし、みんなで汗をかいて、「やー!」などとやったりする暑苦しい演劇ではなく、都会的でクールなところがかっこよかった。テレビでも表現の規制がかかり始めていたのですが、差別的な表現をあえてして差別している人を差別したり、差別的表現だと批判するような人に対しても理論武装されているところが、いかにも新しい演劇という感じで衝撃的でした。僕は社会福祉の大学に行ったのに、差別的な台詞を言ったり、知的障害者の役を演じたりしていいのかなっていう迷いも、正直最初はあったんです。でもこれも表現なんだと思ったら、吹っ切れました。当時の演劇って本当に熱があって、公演前に観客が外に長い行列を作るくらいだったんです。大人計画は3回目くらいの公演で、小劇場のなかでは面白い劇団として注目されるようになってきたけど、劇団員の顔までは知られていない程度の知名度でした。そんななか僕が障害者になりきって、公演前のお客さんの列に並ぶパフォーマンスをしたんです。すると劇場の支配人役でスーツ姿の松尾さんが出てきて、「なんで障害者がここに並んでんの? この芝居、障害者が観るのはダメなんだよ!」と叱責して。「な、な、なんでですかー?」と僕が言って一度はその場からいなくなるんですけど、10分後くらいに「ここは、大人計画の公演ですかー?」と戻ってきて、並んでいたお客さんも「あの人、また来たよ」みたいにざわつくんです。それで開演直前に、僕が客席の後ろから「ちょっといいですかー」とか言いながら登場して、パフォーマンスだったことがようやくお客さんにもわかるんですけど、その公演を大学の同級生がたまたま観に来て、「お前はなんて芝居をやってるんだ!」ってすっごい怒られましてね。僕も「いや、これはそういうことじゃなくて……」と説明したんですけど、「障害者のことをバカにするなんてひどい」と聞く耳を持ってくれなかった。後々、ちゃんと和解しましたけどね。
── それくらい見方によってはタブーで、リアルだったんでしょうね。
温水:その場に並んでいるお客さんも「なんであの人、また来たの?」って差別する心が芽生えるじゃないですか。そういう人を皮肉るような表現だったんですけどね。
親が初めて観に来た芝居で全裸に。

── 大人計画もその頃にはすでに人気の劇団になっていたんですね。
温水:駅前劇場とかではお客さんもいっぱいになってましたし、そのうち徐々に僕も大人計画だけでなく、外部の公演に呼ばれるようになってきました。今は同じ事務所ですけど、ワハハ本舗の村松利史さんは最初に大人計画をいろんなところで紹介してくださった人。村松さんのユニットにも呼ばれましたけど、そっちのほうがもっとひどかったですね(笑)。しかも親が初めて観に来た芝居が、それだったんですけど。僕は宮崎出身なのですが、その公演は企業がお金を出していることもあって、福岡公演もあったんですね。それで「福岡の親戚から聞いたけど、おまえ今度、福岡に来るそうじゃないか」って親から連絡が来まして。大学を卒業して就職もせず3年経っていたんですけど、自分が出演している舞台のチラシや、名前が載った『ぴあ』を送ったりしていたので、なんとかやっているもんだと思ってはいたのでしょうけど。とはいえこれは、最初に親に見せるべき芝居ではないと思ったから、来なくていいと断ったんですけど、「もうチケットを取っているから、宮崎から車で行くよ」と言われまして。演出を担当している村松さんにそのことを伝えたら、「えー、なんでこんな芝居に親を呼ぶの?」と言われました(笑)。その公演は福岡市の教育委員会が後援していて、ゲネプロを観た偉い方々が「あの場面はやめてくれ」とあれこれ変更を求めてきたんです。僕が全裸で車椅子に乗せられて、スタンガンで気絶をしたり、マヨネーズをかけられるシーンとかにもNGを出されたんですけど、村松さんは「そんなことを言うなら、最初から自分を呼ぶな」と頑として譲らず、表現者として戦っていたんです。でも僕の親が来ることに関してはちょっと気を使ってくれて、本来なら車椅子で全裸にされて、客席に向かってうわーっと局部をさらけ出すところを、「親のいるほうに車椅子を向けないから、どの辺に座る予定なの?」って(笑)。終演後、みんなは打ち上げに行ったんですけど、僕は親と食事に行ったんです。楽屋にも来て挨拶をして、「息子がお世話になってます」ってそのときはニコニコ笑っていましたが、3人になったら「おまえ、最低だな。こんな芝居をやってるのか!」って怒られて。僕も「いや、この芝居は特別で……」と説得したんですけど。でも後々母から聞いたら、「芝居はひどかったけど、ああやって舞台に立ってなんとかやってるからよかったって、お父さんが帰りの車の中で言ってたわよ」と。初めて見せる芝居では絶対になかったですけどね。
── いい話ですね(笑)。大人計画には6年いたそうですが、独立するきっかけは?
温水:大々的に独立をした感じでは全然なく、いつでも戻れるというくらいの気持ちでした。映像の仕事も増えて、Vシネにもちょくちょく出るようになっていましたし。地上波のゴールデンドラマで最初に出させてもらったのが、堤幸彦さんの作品。映画デビュー作も堤幸彦さんの『中指姫』なんですけど、本当は竹中直人さんの『119』がデビュー作になる予定だったんです。「デビュー作はプロフィールに残るから、俺の映画を一番最初にしろよ」と竹中さんに言われていて、自分もそのつもりだったのですが、撮影が半年延びちゃって。
── 竹中さんのコント番組『恋のバカンス』にも出演されていますが、竹中さんとの出会ったきっかけは?
温水:竹中さんと村松さんが仲が良くて、さっき話した村松さん演出の芝居を竹中さんも観に来てくれたんです。もちろん僕は面識がなかったですけど、青年座のあの竹中さんが観に来られると聞いて緊張しました。ストッキングにサンマを2尾入れて、頭にかぶって振り回して、駅前劇場の客席に水しぶきを飛ばして、お客さんをキャーキャー言わせている姿が目に止まったみたいで、すぐにお声をかけていただいて。最初はオリジナルのビデオドラマのコントだったんですけど、そのあとも『恋のバカンス』や「竹中直人の会」という舞台にも呼んでいただきました。
── テレビに出ることが多くなったのもその辺りから?
温水:ドラマだと、1999年に堤幸彦さんの『ケイゾク』の記念すべき第1話に出させてもらっています。だけど「あの人、ドラマに出てたよね」と街で言われる程度で、名前はまだまだ。CMも結構やらせてもらっていたのですが、所ジョージさんのゼナのCMがバンバン流れたのが大きかったみたいです。2000年に明石家さんまさんの舞台『七人ぐらいの兵士』にキャスティングされたのも、それがきっかけだったりするので。『七人ぐらいの兵士』は、さんまさんとふたりで漫才の稽古をする場面があるんですけど、さんまさんにものすごくいじられるんです。当時はまだボケとツッコミみたいな関西のお笑いがよくわからなくて、「あほかおまえ!」って言われると本当に怒られていると思って、「すいません、すいません」ってビクビクしながら謝るのを、さんまさんが面白おかしくしてくださって。日曜日に公演が終わったんですけど、翌々日の火曜日には『踊る!さんま御殿!!』の収録に呼ばれていました。そこからバラエティに出演する頻度が高くなって、世間的にも顔と名前が一致するようになったのだと思います。バラエティなんか絶対に無理だと思っていましたし、ましてやフリートークなんて。でも、3カ月に1回くらい呼んでくださるので、さんまさんが絶対に面白くしてくれるっていう思いもあって出演していたら、そのうちほかのバラエティにも呼ばれるようになってきて……。
── 今も苦手意識はあるんですか?
温水:苦手ですねえ。だけど役者だからそのくらいでいいと思うし。ダウンタウンの浜田さんに「おまえは俳優なんだから、小手先でバラエティがうまくなる必要なんかないし、そのまんまでええで」と言われたのも大きかったです。ただ、バラエティのおかげでドラマに出演する機会も増えたとは思います。今となっては役者がバラエティに出るのも当たり前になっていますけど、当時は珍しかったので先輩俳優などにいろんなことを言われました。「芸人に突っ込まれて悔しくないの?」とか「おまえは役者なんだから、役者だけやっておけばいいんだよ」「あんまりバラエティに出すぎると、自分の価値を落とすぞ」「バラエティに魂を売りやがって」みたいに。だけど今思うと、バラエティでいい経験もさせてもらいました。こういう笑かし方もあるんだと勉強になったし、芸人さんの話術は本当にすごい。さんまさんなんかは特に、落語と一緒で同じ話を何回やっても、聞く側はオチを知っているのにやっぱり面白いんですよね。役者だとさらにウケようと思ってオーバーな話し方になったり、違うオチにしたりして、何かしら変えちゃうんですけど、こういうのも必要だなと思うときがありますね。
求められていなくても、舞台ではたまに弾けたいです。

── テレビにたくさん出てキャラクターが認知されると、同じような役が来るのではないでしょうか。
温水:パブリックなイメージだと、気の弱い感じとかですよね。一時期はたしかに多かったけど、そういうイメージが定着したからこそ、人をバンバンやっちゃうような殺し屋とか、女性からモテモテみたいな真逆のイメージの役をたまにいただいたりもします。でもまあ、昔から犯人役は多いですね。いわゆる強面の凶悪犯ではなく、知能犯やオタク系の犯人。最初は人がよさそう見えて、実は犯人だったという展開も結構あったんですけど、最近は僕がそれをやるとこの人が犯人だっていうのがバレちゃうので(笑)。でも意外性のある役はやりたいですね。なかなかないですけど、観ている人を裏切るような役は演じていても楽しいです。
── コロナでお仕事に影響はありましたか?
温水:去年の1月にシアターコクーンで舞台をやって、2月後半から大阪公演だったんですけど、政府からイベント中止要請が出された日の昼公演が千秋楽だったんです。さんまさんの舞台だったので、700人くらいの客入りで満席でしたが、なんとかやり切ることができました。そのあとは、たまたま舞台が入っていなかったのですが、周りの同業者はいろいろと大変そうでしたね。
── 自粛期間中はどんなふうに過ごしていましたか?
温水:最初の頃は、ずっと気になっていた下駄箱の棚をDIYで修理しました。ビスで棚板を固定するタイプなんですけど、うちの奥さんのブーツとかが重みがあって、板がしなってすぐに外れてしまうので、なんとかならないかなと思っていたんです。それでホームセンターに行って部品を買って、1日がかりで直したりとか。台本の整理もして、3分の1くらい減らしました。奥さんと1日1、2本、Netflixで映画を観ていたんですけど、アベンジャーズシリーズを意外と観ていないことに気づいて、ネットで調べて最初から時系列で観たりとか。世間でキャンプが流行っていましたけど、リビングにテントを張ったり、お取り寄せも結構やりました。コロナでできなくなったことといえば、このまま年を取っていくのも嫌だなと思い、見聞を広めるってわけじゃないですけど、ここ数年、奥さんとふたりで海外旅行に出かけていたんです。最初は2014年にハワイに行ったんですけど、2017年2月にトランプ政権になったばかりのニューヨークが大変そうだから、どうなっているのか自分の目で確かめようと思って行ったら、すごく面白くて。映画で見たことのある場所ばかりだし、ブロードウェイは特に刺激的でした。冬だけではもの足りなくて、同じ年の夏にまたニューヨークに出かけて、セントラルパークでみんなが寝転んでいる風景とか、紙袋にアルコールの瓶を包んで飲んでいるのを見て「これこれ」と思ったり。スポーツ観戦も好きなので、全米オープンテニスの高いチケットを買って、センターコートで選手が豆粒みたいに見えるところで観戦したり、ヤンキースの試合にも行きました。芝居以外の世界を知るのって、なんか嬉しいんですよね。後々テニスの全米オープンをテレビで見て、あの辺に座ったんだって思うのも楽しいし。富士山に登ったことのある人が、飛行機の窓から富士山の頂上を見下ろして、あそこに立ったことがあるんだって思う感覚と似ている気がして。富士山の頂上に立つってそういうことらしいですよ。僕は登る気はないですけど。去年の3月は、2年連続でタイのサムイ島に行く予定だったんですけどね。一年に一回の贅沢じゃないですけど、普段行かないところに行ったり、できないような経験をして、俳優の仕事に何かしら役立てばいいなっていうのはあります。
── 奥様と仲が良くて素敵ですね。
温水:ひとり旅は、まあそれはつまらないんですよ。京都で撮影をしたとき、空き時間があったので20年ぶりくらいに清水寺にひとりで行ったんですけど、全然つまらなかった。自撮りして奥さんに送ったら「わーいいな」って言われましたけど。若い頃、電車を乗り継いで東京から宮崎までひとりで帰ったことがあるんですけど、もう暇で暇で。前に座っているおばあさんに話しかけたり、隣に座った同世代の男の人と友だちになったりしたんですけど、みんな途中で降りてしまうので。ひとりって寂しいだけで面白くないんですよね。
── 今後の活動の展望などはありますか?
温水:展望じゃないですけど、特に舞台ではたまに弾けたいんですよね。でも最近はそういう役が少なくなっているというか、弾けるのは若い子たちで、僕らは年齢的に存在感があるような役割に回りがちなんです。「温水さんは弾けなくていいです」と言われると、求められてるのはそこかあって思いますね。演技についても直接何かを言われることが少なくなったから、これでよかったのか不安になります。だけど、このあいだケラ(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)さんに「若手にはいちいち伝えるけど、何も言われないのはよかったってことなんだよ」と言われました。ダイレクトに言ってくれなくても、最近はSNSでつぶやく人もいますしね。自分に自信を持てればいいんでしょうけど、演じるのは今でもやっぱり難しいことです。職業にしているのだから、もっと簡単にやらなければいけないのかもしれないけれど。バラエティに至ってはもっと難しいし、本当に恥ずかしい。だから自分が出演した番組を見返すことはほとんどないのですが、うまくできなくて気になったところだけ、恐る恐る見ることもあります。そしたら大抵、カットされているんですけどね(笑)。

■プロフィール
温水洋一(ぬくみず・よういち)
1964年(昭和39年)6月19日生まれ。宮崎県出身。
1988年より大人計画に在籍し、遊園地再生事業団、竹中直人の会などに出演。
1998年、新たなる活動拠点として「オフィス ワン・ツゥ・スリー」を安齋肇、村松利史らと設立、所属。
舞台では、明石家さんま主演のカンパニーに「七人ぐらいの兵士」から参加、以降全作品に出演。また三谷幸喜作・演出「オケピ!」、「12人の優しい日本人」などに出演。
2017年には紀伊國屋演劇賞・個人賞を受賞。
映画はこれまで80本以上出演。
2021年4月からWOWOW連続ドラマ「華麗なる一族」、同じく4月からNHK土曜ドラマ「今ここにある危機とぼくの好感度について」にレギュラー出演。映画「元メンに呼び出されたら、そこは異次元空間だった」、「祈り―幻に長崎を想う刻―」が今年公開待機中。フジテレビ「ぶらぶらサタデー タカトシ温水の路線バスの旅」にレギュラー出演中。
映画やドラマで唯一無二の個性派俳優として広く知られ、バラエティ番組でも独特のキャラクターで人気を博す。