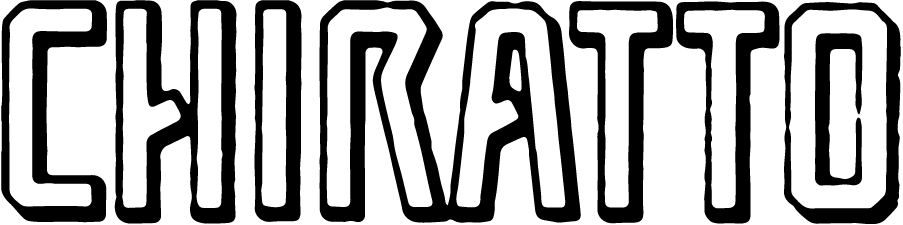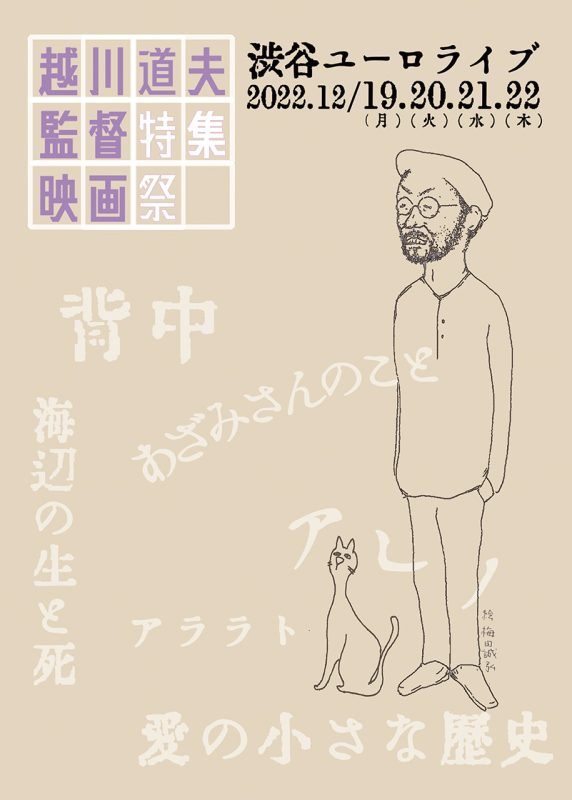第三十七回特別インタビュー 越川道夫(映画監督・脚本家)

映画プロデューサーとして活躍してきた越川道夫さん。2015年の監督デビュー以降は、ハイペースで作品を生み出し続けてきました。『越川道夫監督特集映画祭』が開催されるタイミングで、映画監督という仕事について、映画を撮るということについて、現在の心境についてお話をうかがいました。

――越川さんといえば、『青い車』『かぞくのくに』などでプロデューサーとして活躍されていましたが、2015年に『アレノ』で映画監督デビューされてからは、ハイペースで監督としての活動を進めていらっしゃいますね。
越川 いやもう、一度監督をやってしまうと、他の仕事はあんまり来ないんですよ。あるデザイナーの方とも話すんですけど、彼も一度絵を描いて展覧会をしたら画家として見られてデザインの仕事がこなくなったって。僕も監督以外やらないと言ったわけじゃないですけど、なかなか他の仕事がやりづらいです。中途半端になってもいけないし。
――では、越川さんご自身は監督に専念したいと思ったわけではなく……。
越川 僕は大学を出て、東映のスタジオで助監督をやったあと、映画に関わる仕事はほぼぜんぶしたんです。映画館勤務、映写技師、配給、宣伝、プロデューサー、そして監督……。50歳で監督デビューしましたが、映画監督になりたくてたまらないというタイプではなかった。どれも映画にまつわる仕事のひとつであって、監督であろうと他の仕事であろうと、根本的なスタンスに変わりはありません。たとえば、配給をやっているときにデザイナーの人たちと仕事をするやり方と、いま監督としてスタッフや俳優たちと関わるときの仕事のやり方とは、基本的には同じだと思います。
――監督であろうと、他の仕事であろうと、映画と関わるという点では同じということですね。監督として、とくに今年は多作だとうかがいました。
越川 ことしは4本長編映画を撮りましたが、さすがにこのペースは無理がありました(笑)。1作1作、僕なりに低予算で映画を撮る意味を模索し続けながら撮っています。ともすると低予算映画は、大予算の映画の縮小版になってしまいがちです。でもそれでは貧しいということにしかならない。低予算という状況を逆手にとって、それを豊かなものにするためには、通常の映画づくりとは考え方を大きく変える必要があるのではないかと思っています。
――はい。
越川 例えばヨーロッパならばヌーヴェルヴァーグに代表されるインディペンデント映画の歴史があって、エリック・ロメールやカサヴェテスといった、独自の発想で映画を撮った人がいると思います。通常の映画づくりとは違った発想をもったスタッフワーク、キャストとの関係、発想。日本にはまだなかなか根付いていないと思っています。でも僕はそういう作品を好きで見てきたから、自分なりにやり方を模索したいというのはあったかもしれません。
『水いらずの星』でチャレンジしたこと
――来年公開予定の『水いらずの星』では、劇作家である松田正隆さんの戯曲が原作だとか。
越川 『海と日傘』とか『月の岬』とか、松田さんの戯曲が元々好きだったんです。2016年に、『アレノ』で母親役をやってくれた内田淳子さんが、金替康博さんと二人芝居で『水いらずの星』を上演していたのを観ました。16年ぶりの再演だったそうです。それを観て「これはいい戯曲だな」と思って。内田さんに「この戯曲、なんとか読めませんか」とねだったんです。そしたら後々戯曲を送ってくれた。それで、河野知美さんから『映画を撮りたい』というお声がけがあったときに、いろいろ考えて「この戯曲がいいんじゃないかな」と伝えました。
――原作となった戯曲をそのまま、忠実に再現されたそうですね。それもひとつの挑戦のように思いますが。
越川 プロデューサー時代から原作を変えないほうなんですよ。『白河夜船』のとき、原作者の吉本ばななさんに「本当にこのままでいいの?」と聞かれました。だって原作が好きで、それに惚れ込んでやるわけですから。
――原作を尊重するのは、プロデューサー時代からの変わらぬ姿勢?
越川 そうですね。そうしたいと思っています。溝口健二監督が『元禄忠臣蔵』を撮ったとき、真山青果による戯曲の本読みからはじめたというんです。すごく長い戯曲ですから、映画にするにあたってどこをカットできるかという意味も含めてやったんだと思うんです。でも、周りがカットしようとすると溝口さんが怒るんだそうです。それは、溝口さんなりの原作に対する敬意の持ち方だと思うんですよ。
――敬意。
越川 松田さんの元々舞台のために書かれた松田さんの戯曲をできるだけそのまま撮って、舞台中継ではなく映画にしていくのはチャレンジだと思いました。でも、映画にしやすくするために変える気はなかった。無謀でもチャレンジはしてみてもいいんじゃないかと。ヒッチコックの『ロープ』だって、舞台ですもんね。実際にはカットが割ってありますけど、まるでワンショットのようにつないで、そもそも舞台のようにリアルタイムで映画が進んでいく。自分にヒッチコックと同じことができるはずないしできっこないですが。では、どうするのか、と。
俳優がどう見えるか、それだけ

――越川さんが作品づくりをするときのいちばん最初の動機は?
越川 そもそも、僕には自己表現欲はないんです。僕の師匠は澤井信一郎監督(『野菊の墓』『Wの悲劇』等)ですが、スターシステムの中で映画を撮っていた人です。たとえば薬師丸ひろ子さん主演で、原作はこれで行くとか、そういうことが初めから決まっていたなかで撮ることが多かった監督です。それをどうするかというところに、職人としての倫理と凄みや気概があった監督だと思っています。
――職人として。
越川 じつは相米慎二監督も職人的な監督だと考えています。市川準監督だってそうだと思う。市川準さんの作品も、彼が企画したのは数本で。ほとんどが依頼された企画だと聞いています。依頼されて、それをどう撮るかを考えてつくった。でも、全部が市川準作品になっているのがすごいですね。僕は、作家というよりも職人と呼ぶにふさわい監督たちの後ろ姿を見てきたと思いますし、尊敬もしています。映画は俳優のものという考えが身についているんです。だから『海辺の生と死』でも「満島ひかりさんでどういう作品を撮るか」だし、『アレノ』も山田真歩さんに何をやってもらったらいいか、だし……。あてがきはしませんが、この役者に何をしてもらうか、何をやったら面白いか、そう考えることが僕にとっての映画を作ること。プロデューサーをしていてもそうです。自分がこの作品をやりたいから、これに合う役者を集める、という感じではないんです。
――映画監督=表現欲、というイメージをどうしても持ってしまいがちですが、そう言われると納得します。
越川 僕は何をやっても、プログラムピクチャーを作っているつもりなんです。かつては「アイドル映画を作っているつもりだ」とよく言っていましたけど。澤井さんの『Wの悲劇』は、薬師丸ひろ子という一人の女優の、新たな出発を祝福するためにつくられた映画ということが、画面からひしひしと伝わってきます。ラストで薬師丸さんがぐっとアップになるんですが、現場ではズームアップしていないんです。編集のときにオプチカルで顔に寄ってる。そうすると画面が荒れてしまうのですが、それでも澤井さんはこのアップが映画に必要だ、と思ったんでしょう。ここで彼女の女優としての新たな出発を、観客と一緒に祝福するためにはこのズームアップが必要だ、と。それが彼の映画の倫理なのかもしれません。だから、あのシーンを見るといつも背筋が伸びるんです。
――なるほど。そこが越川さんの原点なんですね。
越川 薬師丸さんの話ばかりになっちゃうけれど、『セーラー服と機関銃』について、脚本の田中陽造さんが語っていたものを読んだんです。その中で、ラストの「わたくし、愚かな女になりそうです、マル」というセリフは、薬師丸ひろ子さんにそういう女になって欲しいと思って書いた、と陽造さんがおっしゃっていたのが印象的でした。俳優のために映画を撮るということは、その俳優にどうなってほしいかという思いも寄せて撮る。それがアイドル映画、プログラムピクチャーの倫理なんだと思うんです。僕も、いつもそのようにに撮っているつもりです。
――俳優を撮る、ということですね。
越川 結局、僕が『アレノ』で監督をやるようになったのは、山田真歩という俳優に対する愛情以外の何者でもない。もし山田さんという俳優に対する期待がなければ、監督をやることはなかった。瀬戸(かほ)さんに対しても、三浦透子さんに対しても、出演する誰に対してもその気持ちは同じようにあるわけです。それが僕に監督をやらせている。そのスタンスは、今に至るまで崩すつもりはない。だから、僕自身がほめられたいと思ったことはないです。スクリーンに映っているのは俳優だから、俳優がほめられてほしい。僕が褒められたって仕方がない。そのためにいろいろ考えて撮るわけです。
――スクリーンに映っている俳優がよく見えるように。
越川 そう。客は俳優を見にくるんだと思います。その俳優が見たい、その俳優いいと思えるというのが僕にとっての映画です。俳優の、「こういう顔は見たことなかったよね」という部分を常に見たい。宇野祥平さんや斉藤陽一郎さんと仕事をしても、先入観を持たず「次どんなことをしようか」という相談をして、つねにみんなの新しい顔を見せたいんと思います。
――得意なことじゃなくて、新しいこと。
『二十六夜待ち』を撮ったとき、諏訪太朗さんに出ていただいたんです。諏訪さんが「どこかエキセントリックな役をやることが多いから、こういうやわらかな役をやりたかった」と言ってくださって、あるセリフを「僕はこのセリフを言うためにここに来てるんです」と言って演じてくださった。俳優がそう思ってくれた、それは僕の勲章みたいなものです。同じようなキャラクターを演じることが続くって、俳優にとって「売れる」ということでもあるから大事なことだけど、同時に苦しさもあるのではないでしょうか。小さな映画だからこそ、俳優に対してできることがあるんじゃないかと思っています。
周りの人々を喪って

――今後はどんな展望を?
越川 先日、稲川方人さん(詩人、映画監督)とメールでやりとりをしていて、「越川さんは今後何を画策してるんですか」と問われて「何も画策してないです。画策するには、僕の周りで人が死にすぎました」と返信したんです。……去年目の手術をしたんです。元々白内障があったんですが、2月に病院に行ったらちょっと厄介な病気になっていて「このまま放っておくと1年で失明します」と言われました。
――えっ!
越川 僕も、そんなに自分が悪いとは思ってもなかったんです。ちょっと見えづらくなったから、今後のために行っておくか、くらいの感覚だった。でも医者に「右目は色も形も見えていないはずです」と言われて「いやいや、見えてますよ」と答えたら「脳が補正してるんです」と。それで、4月に手術をしたんですね。人工のレンズを入れました。それにまつわる不都合がいろいろあって、自分の中ではすべてが解消されているわけではない。だから、『背中』以降の監督作は手術後の作品になるわけですけど、感覚がまだしっくりこないままやっています。普通の生活をしている分には「見えるようになってよかった」という状況ですけど、やっぱり見ることが商売ですから。いろいろと困ることがあり、センシティブな問題がある、自分の中でしっくりきていないまま1年たって。
――しっくりきていないまま……。
越川 その時期に、周りの人が亡くなって。コロナで亡くなった人はいないんですが、親しい方が立て続けに。かわいがってくれた映画プロデューサーの成田尚哉さんが亡くなり、昨年の9月に師匠の澤井さんが亡くなって。オフィス・シロウズの佐々木史朗さんも今年……。そういう先輩たちとの関係の中で、自分が映画の仕事をしていたんだなということを、いなくなると改めて感じるんです。
――はい。
越川 年齢的なものもありますが、同世代も亡くなっていて、中でもやっぱり大学の同期である青山真治監督が亡くなったことは大きくて……。僕がたまたま失明を免れて、いま映画の仕事をまだしている。その一方で、青山真治のような監督がもういなくて、彼の映画がもうこの世に生まれない。そのバランスが、どうにも自分の中で取れないんですよ。たいせつな人を失ってしまって、自分の映画をつくる意味をどう考えたらいいのか、悩んでいる。立て続けだったので、ダメージが大きくて。
――それはしんどいですね。
越川 だから、自分がこの先どうやっていくのか、『水いらずの星』をひとつの区切りにして、ちょっと考えようと思っています。
――では、少し作品の間隔が空くことも……。
越川 まあ、何かしらやっているとは思うんですよ。だって僕は大学を出てからこの仕事しかしていないわけですから。映画以外の仕事はできない。でも、僕はなぜこの仕事をしているのか、ということをもう一度考え直す必要があるなと思っています。ま、そう思っているときに『越川さんのレトロスペクティブを』なんて話をいただくと、「あれ、俺死んだの?」っていう(笑)。そんな、特集上映をやってもらえるような監督じゃないよ、という思いも自分の中にはあるから、申し訳ないな、と思いつつ。でも、ひと区切りして立ち止まって考えようと思っているときにこういう機会があるというのは、ちょうどいいタイミングだなとは思うんです。
―― おっしゃるように、監督業をはじめられてから馬車馬のように仕事をされてきたイメージがあるので、そのなかでたいせつな人が亡くなったことを一人ずつきちんと悼むことができないということも、つらかったのではないでしょうか。
越川 そうですね。たとえば、たむらまさき(キャメラマン・映画監督)さんが亡くなって数年になりますけど、僕はまだ彼の死をちゃんと受け入れられていないんですよ。周りからは「こういうときにちゃんと悲しんでおかないと引きずっちゃうよ」と言われるんですが、悲しんでも悲しんでもどうにもならない。いま、自分が映画を撮ろうとしてスタッフィングをするとき、たむらさんに撮影を、佐藤譲さんに照明を、蓮実重臣さんに音楽をと思うのに、できない。「なんで頼めないんだろう」と思ってしまうんです。ちゃんと悲しんでさえこんな気持ちになるんだから、この最近の、周りが立て続けに亡くなったときに悲しめなかったら……。僕だけじゃなく、世の中全体が、コロナ禍の中でちゃんと向き合えていない気がします。『背中』以降の作品には、そういう気分がどれも反映されていると思います。
自分のルーツをもう一度見直したい

――ただ、今回の特集上映をきっかけに、ご自分の作品を見直して感じるものもあるのでは?
越川 僕は、自分の作品を見返せないんです。文章も書くけど、それもひとつもとっておいてない。自分が表現することに、興味がないんです。というか、映画は作る時に死ぬほど見るから。全力で見るから。いやもちろん、全力で作ったからって「完璧なものができた!」なんて思ったことは一度もないけれども。それでも二度と見たくないくらいに全力で見ますからね。
――なるほど。でも、そのひと区切りのあとでまた撮るものが変わったりするのかもしれませんね。
越川 そうですね。長くやっていると……まあ、監督としては新人みたいなものですけど、こういう時期もまあ来るでしょう、と思うんですよ。昔ね、蜷川幸雄さんが蜷川スタジオをつくるくらいの時期に、パルコの小さな会議室のようなスペースで「これまでの自分を総括する」というイベントをされたことがあるんです。清水邦夫さんと始めた最初の舞台から、全てを総括する。清水邦夫さんと石井愃一さんを呼んで、当時の舞台を録音したものを聞いて、3人で落ち込むっていう(笑)。そんなのを当時、若かった僕は観客として見に行ったんですよ。三夜連続くらいでやったんじゃなかったかな。
――そんなことがあったんですか。
越川 そう、面白かったですよ。だから、蜷川さんほどの人であっても、そういうふうに区切る時期があるんだなと思ったんです。だから自分も、年齢的にもキャリア的にも、一旦振り返ってもいいのかなと。
――そんなタイミングでお話をうかがえてよかったです。
越川 何が好きだったのかをもう一度考える時間にしたいですね。生まれ育ったのが田舎の色街の近くで、その街に出入りする人たちにかわいがってもらった。そんな記憶もあって、落語とか、江戸時代の近松門左衛門、河竹黙阿弥、鶴屋南北、そういうものが好きなんですよね。大学時代も蓮實重彦さんの授業は履修してなくて、江戸文学の松崎仁さんの授業ばかりとっていたくらいです。思えばプログラムピクチャーを撮るという意識も、子供の頃にルーツがあるのかなと思います。祖父がヘンリー・フォンダが好きで、映画を見に行く時にフォンダと言えず「ホンダさんの映画見に行く」って。当時から僕にとって映画は俳優を見に行くものだった。……そういうルーツをこの機会にもう一度、見つめ直すのもいいかなと思っています。

■プロフィール
越川道夫(こしかわみちお)
1965年生まれ。静岡県浜松市出身。助監督、劇場勤務、演劇活動、配給会社勤務を経て、1997年映画制作・配給会社 スローラーナーを設立。
ラース・フォン・トリアー監督『イディオッツ』 (98)、アレクサンドル・ソクーロフ監督『太陽』(03)などの話題作の宣伝・配給を手がけ、熊切和嘉監督『海炭市叙景』(10)、 ヤン・ヨンヒ監督『かぞくのくに』(12)などをプロデュース。更に、エミール・ ゾラの「テレーズ・ラカン」を翻案した『アレノ』(15)で劇場長編映画監督デビュー。17年には、島尾敏夫と島尾ミホの出会いを描いた 『海辺の生と死』、『月子』、佐伯一麦原作の『二十六夜待ち』 の3本が立て続けに公開。他にも、『夕陽のあと』(19)、監督・脚本を手がけた『愛の小さな歴史 誰でもない恋人たちの風景Vo l . 1』(19)『あざみさんのこと 誰でもない恋人たちの風景Vo l . 2』(20)『アララト 誰でもない恋人たちの風景Vo l . 3』(21)などがある。最新作『水いらずの星』を含む4本の映画は2023年順次公開予定。コロナ禍にもかかわらず、作品を撮り続けるその姿勢は日本映画界にとって貴重な存在である。
越川道夫監督映画特集映画祭~生と死の間で撮り続ける作品群~
日程:2022年12月19日(月)〜22日(木)
会場:渋谷ユーロライブ(http://eurolive.jp)
お問い合わせ:contact@ktproductiongroup.com
https://onl.bz/zJDGDBJ
『水いらずの星』2023年初冬公開予定
監督:越川道夫
原作:松田正隆
主演:梅田誠弘 河野知美
企画・製作: 屋号 河野知美 映画製作団体
制作協力:有限会社スローラーナー/ウッディ株式会社
配給:株式会社フルモテルモ/Ihr HERz株式会社
Twitter:https://twitter.com/Mizuirazu_movie
Instagram:https://www.instagram.com/mizuirazu_movie/