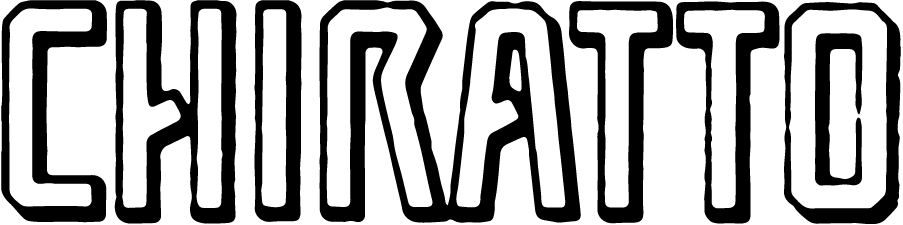第三十回特別インタビュー 劇団 範宙遊泳/山本卓卓(劇作家・演出家)

カラフルかつポップなビジュアルと、終末感漂う劇世界が交錯し「現在」を巧みに照射する作品で高く評価されている劇団範宙遊泳主宰の山本卓卓。初期から海外にも活動を展開し、軽やかに越境するイメージがある山本だが、同時に日本の現代演劇、その礎を築いた先達たちへの想いもアツく深く自身の根に持っているのだという。日本の演劇環境をより良いものにすべく明確なビジョンを持ち、エネルギッシュに創作や活動を展開していく山本の目指すところ、その原動力について訊いた。
表現者としてのルーツと高校での出会い

――山本さんが演劇に関わるのは高校の部活動からですが、それ以前に演劇を体験する機会はなかったのですか?
山本 学校を巡回する劇団公演でシェイクスピアなど観る機会はあったのですが、その時の舞台の印象が「みんなの前で大人が恥ずかしいことをやっている」という、あまり良い印象ではなくて。子どもながらに尊敬できなかった、という印象が原体験にあるんです。
一方幼い頃は身体が弱く、病院通いが日常的だったのですが、通院のご褒美に母がレンタルビデオで映画を借りてくれることが習慣化していて。仮面ライダーから古い名作映画、バスター・キートンやチャップリンまで幅広く、コメディを中心に夢中になっていきました。でもその後はスポーツにも目覚め、中学も野球部だったんです。
――それがどうして文化部に?
山本 当時まだ文科系の部活は、運動部からは軽んじられる風潮があり、「オタク」という言葉に蔑視のニュアンスが多く含まれていました。僕も高校のクラブの名称が「映画演劇部」だったので、「映画が撮れる!」と思って入部したんですが、実際には演劇しかやっていなかったんです(笑)。初めて出会った同世代の文系の人たちは、感覚が僕とは全然違いましたが、演劇だけでないカルチャーに関して色々な情報を持っているし、つき合ううち何だか愛しく思えて来る。うちの部は身体が弱かったり友達が少ないというような生徒が多かったんですが、そういう子たちはとてもピュアな心を持っていて、むしろ自分も含め体育会系の生徒のほうが非常に差別的で驕っていると気づいた。今、話しながら気づいたのですが、僕が作品の中で社会の“はじっこにいる人々”を描きたくなるのは、高校時代の経験が影響しているのかも知れません。
――山本さん自身はどんな高校生だったのでしょう。
山本 クラスメートからは相当ヘンな奴だと思われていたはずです。毎朝、教室に一番に登校し、机の回りを自分だけの空間にしてMDで音楽を聴きながらずっと本を読んでいる。みんながワイワイしている中に入るのが苦痛で、キモがられるくらいのポジションにわざとなり、イジメにも合わないようにという自己防衛ですね。
一方部活ではお互いに好きなアーティストについて語り合うとか、よくある青春映画に描かれるオタク的な交流を部員同士で深めていった。その先に、既存の演劇だけでなく自分が良いと思うものを作品としてつくれるようになった感じです。
――当時、人気が高かったのはどんな演劇ですか?
山本 僕の周囲は野田秀樹さんです。あと、部室にあった戯曲集や演劇書、演劇人のエッセイなどを読むのが大好きで、そこで出会った別役実さんの作品にはすごくハマりました。他にも「ここは知っておくべきだろう」というチェーホフなど、海外の劇作家や古典についての知識は、あの部室で一通り身に着けた感じです。でも、桜美林大学に進学してみると同級生はそんな演劇の基本を全然知らない人も多くて(笑)。
生活と作品は地続きで全ての経験が素材になる

――山本さんは幼少期から知的好奇心が旺盛だったのですね。
山本 興味のある物事はジャンル問わず、手当たり次第に摂取するタイプです。
――そうして得た知識や情報が、偏ることなく後の作品の中で有機的に結び合っているように感じます。それは意識的にされていることですか?
山本 かなり意識的ですね。「コレが好き!」と一つに絞らず、スポーツも映画も、大学在学中は落語研究会所属で落語は今も好きで、株や投資にも興味はある。
新しい世界を知るたびに自分自身が拡張され、細胞が若返る感覚になるんですよね。でも学校でよくある記憶式の勉強などはむしろ苦手で、記憶力には自信がないほうかな。同じ本を何冊も買うとか、知ったそばから忘れていくことも相当にあります(苦笑)。
――多種多様な事物に出会うところから、山本さんを創作に向かわせる初動にはどんな力が働いているのでしょうか。
山本 僕の場合、「自分の身に起きたことから今、見えている世界全てを僕自身の経験にし、そこから作品を書く」という気持ちが強く、作品をつくるために生活をしているようなところがあるかも知れません。
たとえば街中にいる“ヘンな人”に出会う確率がすごく高いんです。すれ違いざまに舌打ちされるとか(苦笑)、恐らく僕が人のそんな不可解で暗い部分にアンテナを張っているからなんでしょうけれど。そういう目に遭うたび「絶対に書いてやる!」と思います。
――生活と創作が近しく濃い関係にあると、変化もビビッドに起きますよね?
山本 ですね。僕、一時期からすると体形が大きくごつくなったと言われますが、これは筋トレの結果で。身体を変えることは、志向や思考を変えることと密接にあると感じたからなんです。ジョギングから筋トレに切り替えたんですが、この肉体改造が執筆に、自分の「筆」にどんな影響を与えるのか探りながらやっているんです。俳優さんも肉体改造や呼吸法、発声法を変えたりしますよね? そういう人たちに演出家として指示を出す以上は、僕も身体のことをある程度は知っていなければと考えてもいます。
――筋力がついて、どんな変化があったのですか?
山本 椅子に座って長時間書いていても、腰が痛くならないです(笑)。あと書いていると、やめ時がわからなくなることがあるんですが、筋トレで身体の限界を知ったことで「これ以上はオーバーワークだ」という判断がスパッとできるようになりました。頑張ってもその先が出ない時は、身体も頭も休めたほうが良い。あと夜遅くよりは朝のほうがクリアな状態で書けるなど、身体に訊きながら仕事ができるようになったのは大きいです。
国内外での共同制作から学んだこと

――大学在学中、2007年に仲間を募り劇団範宙遊泳を旗揚げします。劇作・演出家が作品ごとに人を集める、ユニット形式が若い世代の主流になりつつあった当時、劇団にこだわったのはなぜでしょうか。
山本 学部を立ち上げた平田オリザさんとは入れ違いでしたが、オリザさんや演劇評論家の故 扇田昭彦さんの著作などを読み、アングラ以降の小劇場演劇について基礎知識があった僕は、大学で教えられることの先取りをした状態。授業よりも自分がやりたい演劇をつくる場所が欲しくて、「だったら劇団つくろう」と考えた。それに周囲にはオリザさんの影響を受けた人や現代口語演劇を標ぼうする集団が多く、それは仕方のないことですが、演劇はもっと自由でオリジナリティがあって良いはずだとも思っていましたから。
――2010年からは現代美術家たかくらかずき氏が加入し、舞台美術だけでなく演出面での協働を行い、14年のTPAM(国際舞台芸術ミーティング)でのショウイングを契機にマレーシアとタイでの公演も実現。続けてインドやシンガポールの劇団と共同制作するなど、初期から幅広く、スケールの大きな活動を展開されています。
山本 ちょうどアジアがフォーカスされて海外と招聘や共同制作で結び合う環境が変わり始めた頃、若手の劇団としてはその恩恵も受けて最前線で活動させていただいた、ラッキーな境遇だと思います。でも同時に、僕でなければ我慢できなかったというか、それなりに傷つく体験もしました。もちろん結果的にはやって良かったし全て自分たちの糧になってはいますが。
たとえば僕の戯曲を使ってコラボしましょうという話で現地のスタジオに行ってみると、1行ずつ切り刻まれた戯曲の紙片があり、それらを喋ることもないダンス作品になっていたんです。しかもその作品は書いた僕自身が観ても、戯曲の片鱗も感じられなかったという(笑)。海外の共同制作ではそんな出発点から、お互いをなんとか知ろうとする作業を忍耐強く重ねるしかない。時には第二次世界大戦時に日本軍に蹂躙された歴史から、日本と日本人に良い感情だけを抱いているわけではない国もあり、それを創作に取り入れようとされたこともありました。
ただ、どんな出発点、創作の経緯を辿っても最終的には両者の間に友情を築くことができたし、それは良い作品をつくることと同じくらい大切なことだと今も思っています。
――それら共同制作の経験により、創作方法や作品への取り組みは変わりましたか?
山本 ええ、最近では昨年12月、自分は戯曲執筆に専念し、演出は川口智子さんに委ねる形で上演した『心の声など聞こえるか』という作品があるのですが、それは国も文化的な背景も異なるアーティストと協働した経験から、今の日本のアートシーンに感じる「アーティストの孤立」を打開しなければという想いが自分の中で強くなったから。ジャンルや世代に関係なく、創作に関わるアーティストはみな協働、もしくは共闘や連帯といった結びつき、共に活動する機会や場がこれからもっと大事になると僕は考えているんです。
カリスマとして孤高の地位に着くことがアーティスト然とすること、と思われた時代もありました。でもここから先はアーティスト同士が互いに繋がり、場も情報も共有して、一緒に演劇を含む芸術分野を育てて行こうというムーヴメントが重要。かつての小劇場運動やアングラ演劇の隆盛にも、ベースには演劇人たちの連帯があり、寺山修司と唐十郎が劇団員を率いて乱闘したことなども、演劇で世間にコミットし、シーンを盛り上げるためお互い了解済みでプロレスをしていたようなもの。そこまでではないにしろ、もっと柔軟に戯曲提供や演出を相互に行い、風通し良く創作に臨まなければ今の日本の舞台芸術界が陥っている閉塞感は、解消できないと思うんです。こういう感覚は、海外との共同制作を経験するほどに、僕の中で強まっています。
偉大な先人たちから受け継ぎ繋いでいく「意志」

――「共闘」や「連帯」という言葉を意志的に使い、日本の舞台芸術界に広がる孤立や分断の危険性を指摘し、その解消を訴える。山本さんは87年生まれで、この先の時代に希望を持ちにくい世代の一人だと思いますが、現状の捉え方や思考にネガティブさが感じられません。
山本 もちろん、ここまで創作を続けて来る中では、徒労感や虚無感に苛まれることもありました。一つの要因によるものではありませんが、一番しんどかったのは4、5年前、劇団を始めて10年くらいの頃でしょうか。でも、そういう時に脳裏に浮かぶのは扇田さんの本で読んだ鈴木忠志さんや別役さん、寺山さん、唐さんといった先人たちが時に命懸けで創作し、時代をつくっていった飛び切りカッコいい背中で、その背中を参考にしながら自分のメンタルを鍛えていったところはあるんです。直接教えを受けたり交流があるわけではありませんが、それら先人たちがさらに上の世代含めバトンを渡し合って来たことは、僭越ながら僕にも刷り込み・受け継がれていることで、大事にしたいと思いますし、さらに次の世代に渡せるよう頑張らなければとも思っているんです。
――30年以上遡る先達との繋がりを、そこまで強く感じられる山本さんは稀有な存在に思えます。
山本 そんな大層なことではありませんが、彼らの思想や言動は本の中に残されていて繰り返し読むことができますから。皆さん常に社会と密接に創作や活動を実践していて、それこそがアーティストの理想的なあり方だと僕は思う。僕自身、自分を社会から切り離すようなことはしたくないし、作品には常に「今」の状況や空気をしっかりすくい取って織り込まなければと考えています。
――映像や現代美術などを積極的に取り入れ、台詞だけでない戯曲の言葉を多角的に捉えて直して意味や視覚的な効果を自在に扱うスタイリッシュな作品をつくる山本さんの根の部分に、アングラなどの先人たちの影響が色濃いとは興味深いです。
山本 70年代演劇のアツさや想いが、実は自分にとって非常に大事なものなんだと思います。結局そこしかない、というか。2000年代初頭の、「優しさ、はぁ?」的に冷たい、個人が孤立に追い込まれていた時代があったじゃないですか。その冷たさには、連帯に傷ついたなど理由があるとは思いますが、そこを乗り越えて僕は「いや、やっぱ優しさでしょ」と言いたい。「LOVEだって、はぁ?」と突き放したから、本来は広いレンジの「愛」を表す「LOVE」が、特定の誰かを愛する意味だけに使われるようになり、流行歌の歌詞も平板な「あなたが好き」だけになってしまった。ビートルズが歌っていた「LOVE」や「PEACE」は、もっと大きな意味だったはずじゃないですか。その「大きな意味」から逃げずに書き、つくり、取り戻したいんです。
――大きな目標ですね。
山本 でも僕が愛してやまない王道や名作と呼ばれる創作物はみな、そんな「大きな意味」をちゃんと内包しているし、つくり手たちも相当な覚悟で表現を研ぎ澄ましている。演劇に限らず文学も美術も音楽も映像でも、自分がつくる時には同じだけの覚悟を持ち、先人たちが目指した高みを共に目指したい。もちろん、当時許されて今は許されない表現に関する倫理的な縛りは増していますが、それでも先人たちの遺してくれたものをアップデートしたい野心はあります。今の自分では、まだまだ足りないことだらけなんですが、それでも理想はしっかり掲げ、心ある仲間たちには声を大にして呼びかけ続けるつもりです。
劇団新作で描くのは「悪意との向き合い方」

――21年3月の劇団公演『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞受賞。文中先に登場した同年12月の『心の声など聞こえるか』で演出を他者に委ねて劇作家に徹する“シェア”シリーズを開始。22年5~6月は美術家・鬼頭健吾の大型インスタレーション展の関連企画として、KAAT神奈川芸術劇場アトリウムの階段や壁、椅子、柱など劇場にある“見落とされがちなモノ”たちの呟きを書き下ろしてドラマ・インスタレーションとして展示する『オブジェクト・ストーリー』を、さらにGW前半、静岡市街中心部で開催されるストリートシアターフェス・ストレンジシード静岡2022に、世代に関係なく楽しんでもらえる「シリーズ おとなもこどもも」の新作短篇『かぐや姫のつづき』で参戦という、主だった創作・上演だけでも大変な勢いと密度が感じられます。
山本 確かにこの期間、濃密な創作が続いていますね。ただ、当たり前のことですが、創作の機会を与えられた以上、一つ一つ手を抜きたくないんです。『かぐや姫~』も短編ですが創作の熱量は劇団員共々本公演と変わりませんでしたし、KAATの展示も全力投球でつくりました。なんなら岸田戯曲賞の授賞式での劇団員とのパフォーマンス、僕自身の受賞スピーチもかなり根詰めて稽古したんですよ(笑)。個々の作品と丁寧に深く向き合えているか自問しながらつくる姿勢が、ここ数年でようやく自分の身に着いた感じというか、それまでは頭の中を多くのものが飛び交うせいで視野が定まらなかったのが、ようやく落ち着いて見えるものが増えたからじゃないかと思うんですが。
そうやって一作ごとに足元と世界の両方を見つめ直しながらつくり続けるしか、自分を成長させることはできませんから。
――それ以前には映像作品をつくる機会もありましたが、演劇を創作の主体とする気持ちに変わりはなかったのですか?
山本 そうですね……最初のほうでお話しした高校で出会った仲間たち、“クラスや世間の隅っこにいる人”への愛着が、演劇に対しても強くあるのだと思います。日本の文化芸術全般の中でも、演劇の居場所は“隅っこ”ですよね?(笑)。同時にめちゃくちゃピュアだし、どの作品にも「人間」がみっしり詰まっていて、逆に何をやっても「人間」の外にはいけないのが演劇。あからさまな嘘をついていることを含め、全てが丸見えな演劇という表現は、僕にとって恐らくずっと面白く可愛く愛おしいものであり続けると思います。
――そんな山本さんと範宙遊泳の最新作は6月25日からの、20年に感染症禍のため中止となり、2年を経て生まれ変わる『ディグ・ディグ・フレイミング!~私はロボットではありません~』です。初演から、かなり手を入れられたのでしょうか?
山本 昨日から稽古が始まったのですが、そもそも19年9月からのNY短期留学中に戯曲を半分書き、公演のための稽古に合わせて後半を書こうとしていたんです。2年の間「戯曲だけでも」と思ったこともあるのですが、上演日が決まらぬままでは書き進められず、結局今回の上演に合わせて書き上げる形になりました。2年前と今とでは、日本だけ見ても社会状況や価値観が全く違うし、海外では戦争も起きている。戯曲を精査するためには良い時間だったと思っています。
――どのような作品になるのですか?
山本 取り上げるのはネット上での炎上や誹謗中傷、Me Tooムーヴメントなどで、書き始めた2年前はそれらの出来事や風潮をシニカルに描いていた。でも読み直してみると、現状ではそれら問題に関わる人を二次的に傷つける表現だと思えるところもあり、そういう部分は見直しつつ再考したのが今回の戯曲。とはいえ真面目ぶったものではなく、かなりアッパーで、登場人物全員がめちゃくちゃテンション高いドラマになるはず。SNSの炎上などの奥底には顔の見えない人々の悪意が渦巻いていますが、その「悪意に絡め取られないためにはどうすべきか」というのが今回のテーマで、僕は「悪意を笑うしかない」と思っているんです。悪意を無視せず、闘って打ち勝つための笑い。そこには狂気も見て取れるかも知れませんが、笑うことで悪意が醸す重さ・暗さを軽くすることができる気がする。漫画家でタレントの蛭子能収さん言うところの、「お葬式の重さや儀式の作為につい笑ってしまう」ような逆転現象が僕は好きなんですが、そんな負の要素に向き合うための、別の角度からのアプローチを『ディグ・ディグ~』で追求しようと思っているんです。
ただ、それを日常生活や一般社会の中で不用意にやると不謹慎と怒られてしまう。でも芸術なら人々の間の齟齬も丁寧にほぐして描けるし、観た人に悪意との向き合い方について考え、気づいてもらえるんじゃないかと思っていて。題材が題材なので、書きながらものすごく消耗したし、この後の稽古では僕も俳優の皆さんも相当なエネルギーが必要だと思うのですが、その分、観客には劇場で観た後に心がどこか軽くなるような作品を目指したい。まぁ、それでも怒られる可能性はゼロではありませんが(笑)。
――ご自身のルーツから最新作まで、語り尽くしていただきありがとうございました。新作を楽しみにしています。
■プロフィール
山本卓卓(やまもと・すぐる)
劇作家・演出家。範宙遊泳代表。1987 年山梨県生まれ。 幼少期から吸収した映画・文学・音楽・美術などを芸術的素養に、加速度的 に倫理観が変貌する現代情報社会をビビッドに反映した劇世界を構築する。オンラインをも創作の場とする「むこう側の演劇」や、子どもと一緒に楽しめる「シリーズ おとなもこどもも」、⻘少年や福祉施設に向けたワークショ ップ事業など、幅広いレパートリーを持つ。アジア諸国や北米で公演や国際共同制作、戯曲提供なども行い、活動の場を海外にも広げている。
ACC2018グランティアーティストとして、19年9月〜20年2月にニューヨーク留学。
『幼女 X』でBangkok Theatre Festival 2014 最優秀脚本賞と最優秀作品賞を受賞。
『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞を受賞。公益財団法人セゾン文化財団フェロー。
<次回公演>
範宙遊泳『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜 』
2022年6月25日(土)〜7月3日(日)
東京芸術劇場 シアターイースト
作・演出:山本卓卓
出演:埜本幸良 福原冠
⻲上空花 小濱昭博(劇団 短距離男道ミサイル) 李そじん(⻘年団/東京デスロック)
百瀬朔 村岡希美(ナイロン100°C/阿佐ヶ谷スパイダース)
特設サイトhttps://www.hanchuyuei2017.com/digdig22
お問い合わせhanchu.ticket@gmail.com
<山本卓卓さん:参考リンク>
YouTubeチャンネル(過去作など全編無料公開中)
https://www.youtube.com/user/hanchuyuei
『うまれてないからまだしねない』配信 (英・仏・露・中(繁体/簡体)・⻄・独・韓・日字幕付き)
https://youtu.be/BNRmxFX7yMM