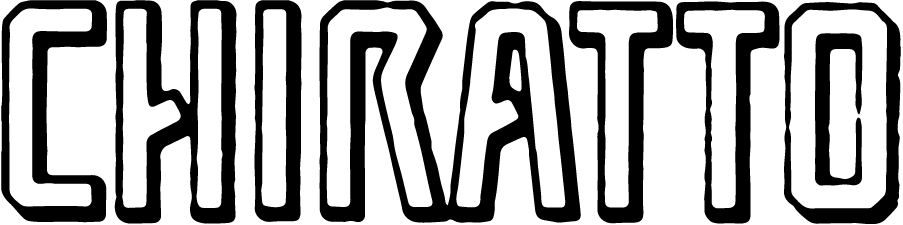ABBの「中止しますよ」 第1話 青春夕暮恋々歌

「初めて自分でお金を出して買ったレコード盤はなに」
ミュージシャンや、音楽にまつわる仕事をしている人であれば割とよく耳にする質問だ。年代によっては「レコード盤」が「CD」になるのだが、それも知らない世代の場合はこの質問の意味さえわからないだろう。
そもそもここでいう「自分でお金を出す」というのはどういうことか。親からもらったお小遣いや親戚からもらったお年玉をコツコツ貯めたお金を使うということなのか。それとも自らアルバイトして稼いだお金で買うということなのか。小学六年生の場合なら前者だろう。
五十三歳の初老の男にとってのレコード盤の最初の記憶はウルトラマンだ。この場合のウルトラマンはカラータイマーが胸についている方で、長澤まさみさんが巨大化するやつではない。そっちはそっちで大好きだが今は関係ないことなので無視しておく。
幼い頃、といってもほんの二歳くらいのことだ。父方の祖父が買ってくれたアンプつきのレコードプレイヤーで聴いていたのは、帰ってきたり、数字や日本的な名前とかアルファベットがつけられたウルトラマンや、朝焼けの光の中に立つミラーマンの主題歌が収められたレコードとソノシートだった。こう書くととても裕福な家庭のお子様のように聞こえるが決してそんなことはない。なぜ当時あのような高価だったであろうものが家にあったのか。いまだに自分史上の七不思議だ。ただしあとの六つはよくおぼえていない。
そんな祖父は私が三歳になる前に旅立ってしまった。それとともにレコード盤の記憶はぷっつりと途切れてしまう。小学校六年生の夏まで。
一九八一年。これまでの半生の中でも印象深い年だ。母が癌を患い、手術をし、長期入院。父親も兄弟も居ない私は母の姉の家に預かってもらうことになった。叔母の家はタイヤの修理工場を営んでいた。大型トラックの出張パンク修理がメインで、昼飯どきと仕事が終わったあと以外は家には誰も居ない。叔母の家は学区外にあったため、同じ年頃の友だちも居ない。居るのは番犬のマリだけ。おうち犬が当たり前の昨今では想像できないかもしれないがマリは日中、ずっと外に繋がれていた。夜はタイヤ工場の片隅の段ボールで寝ていた。ずっと外に繋がれていたせいか、マリはしょっちゅう子犬を産んだ。マリが寝ていた段ボールのすぐそばにリアルぼっとん便所があった。トイレではない。便所だ。木の引き戸になっていて、誰かが入っているとマリはその戸を開けようとする。寂しかったのかもしれない。寂しいからといってしゃがんでいる最中に戸を開けられたらたまったものではない。例えそれが人ではなく、ましてや密かに想いを寄せているクラスのあの子じゃない犬であろうが、恥ずかしいものは恥ずかしいのだから不思議なものだ。
ある日、マリが産んだ子犬のうちの一匹がぼっとんの肥溜めに落ちてしまったことがある。誰も居ない便所の戸をマリが開けてしまったがゆえの大惨事だ。なんとか子犬を助け出したのだが、果たしてどうやって救出したのかはまったくおぼえていない。ただ、便所の戸をついつい開けてしまうくらい寂しかったマリと同じくらい自分も寂しい気持ちでいたことだけはおぼえている。
昭和五十六年当時の小学六年生は、コロコロコミックをあっという間に読み終わり、あとはひたすらテレビのブラウン管を眺めるくらいしかひとりで時間をやり過ごすことができなかった。いま思えばバラ色の生活だが、その当時は心のどこかに空いてしまった穴をどうやって埋められるのかがわからずに、叔母と従兄弟のけんちゃんが帰ってくるまでただただブラウン管を眺め続けていた。それが、良くも悪くも長らく娯楽の世界で生きている自分の栄養分になっていることに気づくのはずっとあとのことだ。
視聴率一〇〇パーセント男。
欽ちゃんこと萩本欽一さんが座長の、今でいうバラエティ番組が地上波放送局を跨いで週に何本も放送されていた。自身の名を冠したいくつかの番組が一週間で叩き出す視聴率の合計が一〇〇パーセントだから「視聴率一〇〇パーセント男」。私がもしもカルロストシキならば、「君は一〇〇〇パーセント」と歌ってあげたいくらいすごいことだ。そのいくつかの番組のうちでも人気だったのが「欽ドン!良い子悪い子普通の子」だ。ヨシオが山口良一さん、ワルオが西山浩司さん、フツオが長江健次さんで、誤解を恐れずに、というか誤解されるだろうけど簡単に説明すると、茶の間に居る父親役の欽ちゃんが、襖を開けて入ってくる三人にお題を出し、それに息子役たちが即興で答えるという大喜利のようなものがメインの番組だ。ほぼ素人の人や畑違いの役者などを起用して大きな笑いの渦を巻き起こすという離れわざを毎週やっていた。欽ちゃんもすごいがそれを受ける三人もとてつもなくすごい。ということを本当の意味で理解できたのはつい最近のことかもしれない。
当時、金曜八時にTBS系列で放送されていたドラマ「三年B組金八先生」第一シーズンから「たのきんトリオ」という、一緒に活動するグループではないが凄まじい人気を誇ったトリオが誕生していた。田原俊彦さん、近藤真彦さん、野村義男さんの三人だ。どれくらいの人気かというと、四国の田舎の小学校に東京から「田原」という苗字の男子が転校してくるという話を聞いただけで、学校中の女子たちがソワソワしっ放しだったほどだ。実際の田原君もいかにも都会育ちでシュッとした感じのイケメンだった。と思う。もう顔も思い出せないけど。田原君、いろんな意味でごめん。
その「たのきんトリオ」に対抗したのかどうかは不明だが、「欽ドン!」からも男性トリオが誕生した。それがヨシオ・ワルオ・フツオの三人によるユニット「イモ欽トリオ」だ。「たのきんトリオ」はグループとして曲を出したことはない(はず)。愛を込めてあえてこう形容させてもらうが、どう考えてもパチモンでイロモノの「イモ欽トリオ」はオリジナル曲をリリースしている。その第一弾が「ハイスクールララバイ」という曲だ。作詞・松本隆、作曲・細野晴臣。「ハイスクールララバイ」誕生前夜にはYMOによるテクノブームが巻き起こっていた。もみあげのないヘアスタイルは今ではなかなかお目にかからないが、彼らのスタイルを真似して世の中の男子の九十九パーセントはテクノカットと呼ばれるもみあげをカットした髪型にしていたほどだ。
そんなテクノの手法を歌謡曲というフォーマットに持ち込んだ「ハイスクールララバイ」は、四国の片隅でボーッと過ごしていた小学六年生に「これライディーンのパクリやん!」と言わせるほどの完成度だった。ここでいう「ライディーン」はフェードインする勇者の方ではない。YMOの大ヒット曲の方だ。
「ハイスクールララバイ」はそのまがいもの感とは裏腹に大ヒットすることとなる。お茶の間を席巻したこの曲は、レコード盤を百六十万枚も売り上げた(らしい)。そのうちの一枚は私が買ったものだ。そう、私が「初めて自分でお金を出して買ったレコード盤」はイモ欽トリオの「ハイスクールララバイ」なのである。母が長期入院しているときになぜ「ハイスクールララバイ」だったのか。
はるか遠くにある記憶には真っ赤でもなく金色でもない橙色の夕陽が見える。母との帰り道で見たあの景色。もう帰って来ないかもしれない母を想いながら歩いた道で眺めたあの景色。泣かずに歩けたのは、とびきりの美少女に一〇〇パーセント片想いして告白した途端に夕陽が落ちてきた、と歌うフツオのおかげかもしれない。
その後の私のレコード盤遍歴は、同じく「欽ドン!」で「良い先生悪い先生普通の先生」に出演していた柳葉敏郎さんが所属する一世風靡セピアへと引き継がれることになる。ちなみに一世風靡での柳葉さんはジョニーと呼ばれていた。白のコンバースハイカットを履いていいのはジョニーだけだ。
というわけで、私の音楽的なバックグラウンドを作ってくれたのは他ならぬ欽ちゃんなのである。この出会いがなければ今の私はなかっただろう。欽ちゃんなんて馴れ馴れしく呼んでしまってすいません、大将。
一九九二年四月一日。南青山七丁目にあった小田急南青山ビルの一室に私は居た。アルバイトに明け暮れてろくに就職活動をしていなかった私がギリギリで滑り込んだのがフォーライフレコードというレコード会社だ。新卒社員として晴々とした気持ちで入社したフォーライフレコードこそ「ハイスクールララバイ」を世に送り出したレコード会社だと知るのはもう少しあとのことだ。
二〇二二年、冬。母は元気で八十五歳の年を越そうとしている。
「ハイスクールララバイ」
作詞:松本隆 作曲:細野晴臣
一九八一年八月五日発売
発売元:フォーライフレコード
(続く)