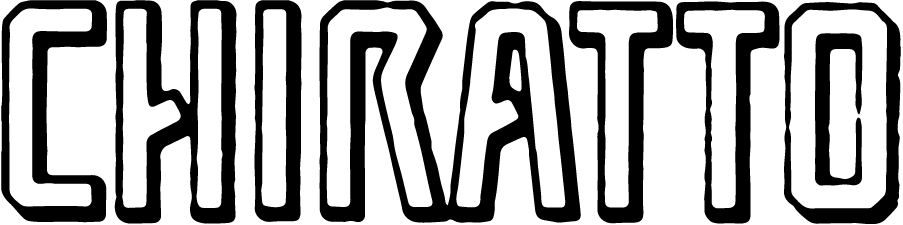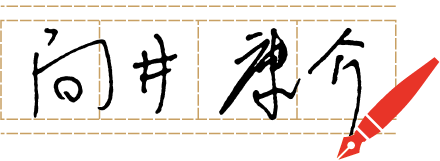青春がけおち大阪篇 第1回
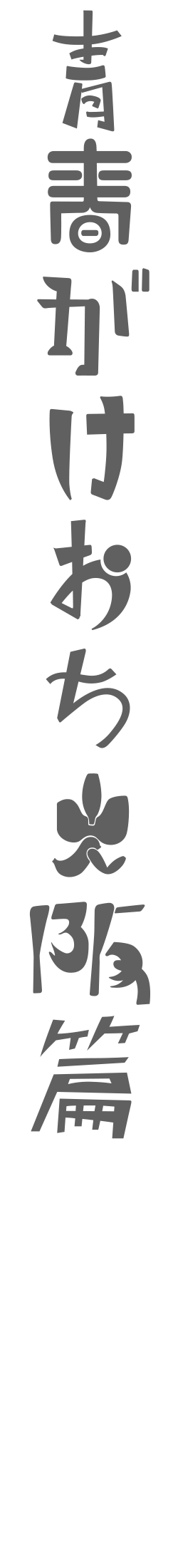
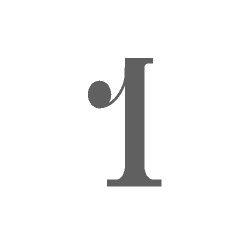
今年の夏、2019年7月に、僕は一冊の本を発表した。それは『大阪芸大 破壊者は西からやってくる』(東京書籍)といって、当初は僕が在籍した大阪芸術大学の歴史を紐解き、他の芸大美大とは違う大阪芸大の独自性を探ろうとするものだったが、書きあがってみると何のことはない、自主映画作りに身を捧げた僕の鬱屈した四年間を、だらだらと書き連ねた回想録に成り下がってしまった。
それでも同じ90年代後半を過ごした同年代や、自主映画に身を捧げたことのある人々は少なからず反応してくれたようで、その読者の一人であったこのサイトの編集者から、続きを読みたいとの申し出があった。そして今、こうしてパソコンに文字を打ち込んでいるという仕儀になっている。自らの過去を活字に起こそうとするなんて、恥ずかしい行為に違いない。恥を掻くなら、徹底的に掻いてしまえと思ったのだ。気持ちとしては自傷行為に近い。
とは言ったものの、僕には大阪芸大を卒業してからの記憶があまり残っていない。『大阪芸大破壊者は西からやってくる』を書いた時には、在学中の四年間をあんなにも克明に思い出せていたのに……。思うに、学生生活には学年の区切りがあり、一年次の時の課題、二年次の時の短編映画作り、三年次から始まる卒業制作と、いちいちの決まりごとがはっきりしていて、記憶を整理しやすかったのだ。また、18歳という若さでいろいろな思想や人間に出会った刺激の大きさもあったろう。初めて自己を形成する過程での、忘れようにも忘れられない体験がそこには確かにあったのだ。けれど、学生という肩書きがなくなると、記憶は途端に色褪せる。
僕は大阪芸大を卒業したあと、大阪に残り続け、同期だった山下敦弘くんや近藤龍人くんと共に二本の長編映画を作り、ある挫折を経験して、負けた気分で東京へ出て行った。これから書き記すのは、映画作りを言い訳のように扱い、未だ何者にもなれない自分に苛立ち、茫漠とした日々に埋没した、そんな僕の四年間の記録である。記憶はあちこちへ飛び火しながら僕の脳内をたゆたっている。事象は度々前後し、また浮き上がっては消えて行きつ戻りつを繰り返すだろう。これは僕の記憶のリハビリのようなものだ。きっと読みにくいはずだが、一人でもいいからついてきてもらいたい。
と、意気地のない前置きをしながらも、大阪芸大のあった河南町を離れ、大阪市福島区に借りた小さなマンションの一室で目覚めた初めての朝のことだけははっきりと覚えている。目を覚ますと白い天井があり、窓から明るい朝日が射していた。最初はそこがどこかもわからず、引っ越した新しい部屋だと気づくまでにしばらく時間がかかった。ベッドと小さなテーブル、机、本棚を入れるともう寝転がるスペースもないほどの狭さの中に、大量のビデオデッキと本、CDが積み重ねられている。つい昨日まで住んでいた南河内郡太子町の学生アパートより清潔ではあったが、広さは半分くらいだった。
その部屋を探してくれたのは兄の義祖母だった。兄と結婚した女性は大阪市福島区の出身で、彼女の両親は浄正橋の近くで理髪店を営んでいた。
大学時代、卒業制作として自主映画『どんてん生活』を撮った仲間や同期たちは(その辺りのことは「大阪芸大 破壊者は西からやってくる」に詳しい)、学生時代から土地勘のある阿倍野橋や天王寺界隈に新居を構えていたので、僕もなんとなくそうしようと思っていたのだが、兄の奥さんの母親である千代子さんに軽く相談したところ、
「そんなもん福島区に決まってるやろ!福島区が一番! 福島区以外は全部クソっ!ついてき!」
その足で懇意の不動産屋に連れて行かれ、
「あ、このマンションええやんかっ!ウチんとこからも近いし便利やでっ!この部屋見に行こっ!」
と不動産屋が出してくれた数枚の見取り図の中から十秒で適当なものを探し出し、またその足で内見に向かうと、
「うんもう充分やがなっ!ここにしよっ!ここでええなっ!うんっ!決まりっ!なんちゅうても福島区が一番なんやからっ!」
僕の新しい住処は相談してからものの十分で決まってしまった。とまあ首根っこを捕まえられるようにして決められた部屋だったけれど、結果的に千代子さんの選択は正しかった。
福島駅から南の周辺は、今でこそ洒落た飲食店が並ぶ小綺麗な一角になっているが、2008年に朝日放送本社が駅の北側から移転してくるまでは、大阪を代表する花街、北新地の真隣とは思えないような、物静かで素朴な下町だった。他にも阪神電車や東西線も連結していたし、近くにローカルなスーパーもあり、まだまだ昭和の景色が残っていた。
千代子さんの斡旋で借りたマンションは、『メガロコープ福島』といった。国道二号線沿いにあるホテルタイプのマンションで、ロビーにはフロントがあり、管理人が常駐していた。部屋代が三万円で、管理費が二万円という妙な家賃だった。
部屋が決まると、早速僕は兄嫁の実家に挨拶に行った。実家の理髪店は、マンションの裏路地を入ったすぐのところにあった。出迎えてくれたのは兄嫁の父・雅司さん。どんなときでも柔和な笑顔を崩さないダンディな人で、千代子さんとはまさに凸と凹。二人のボケとツッコミの関係は典型的な大阪の夫婦といった感じだ。
「メガロコープかいな。そらええわー」
雅司さんはたばこの煙りを燻らせながら丸い声を出す。
「あのマンションはなあ、コーちゃん。昔、明石家さんまが住んでたんや。縁起いいでー。コーちゃんも出世間違いなしや」
「ほら、突っ立っとらんと、晩飯作るから早よ座りっ!」
千代子さんは有無を言わさぬといった体でフライパンを握る。こうして二人は、僕が大阪を離れることになるまで、先をも知れぬ僕のフリーター暮らしの胃袋を支えてくれる恩人となる。
引っ越して初めての朝を迎えたその日、僕は近所の自転車屋へ行き、中古の自転車を買った。大阪市と聞けば広いように感じるかもしれないが、僕が棲息する中心部は思ったよりもコンパクトで、環状線の対極、梅田と天王寺を結んでも、直線距離で7キロほど。自転車だと30分もあれば行き来できる。今、東京で暮らしていて思うが、大阪という場所は本当に暮らしやすい街だと痛感する。
買ったのは、フレームの丈夫そうな、全体が真っ赤な自転車だった。僕はその硬いサドルにまたがり、自分にとっては真新しい街に繰り出す。二号線沿いに5分も走ると、北新地にたどり着いた。午後の歓楽街はひっそりしていて、生気がなく、白い顔をしている。思えば、大学進学のために河南町へやってきた日も、行き先も決めず、町内をバイクで走ったものだった。
バイトの当てはまだなかった。両親が、大学卒業祝いにと送ってくれた30万円が全財産。従って金などあろうはずはなかったが、やらなければならないこと、そしてやりたいことは無数にあった。そのことが、僕に高揚感をもたらす反面、背筋の凍るような不安に襲われもしていた……。
(続く)