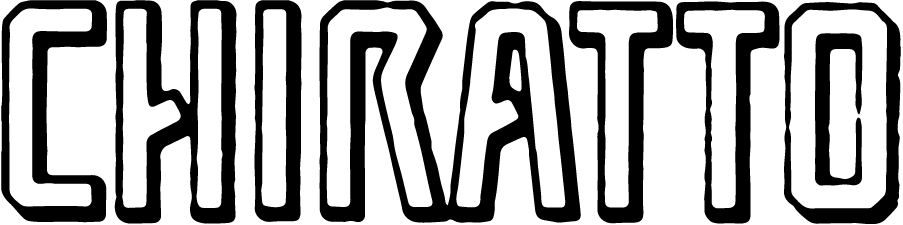第四十一回特別インタビュー 行定勲(映画監督)

監督として数々のヒット作を生み出してきた行定勲はいま、プロデューサーとして映画に取り組んでいる。なぜプロデュースを? そしてそこで生み出した、“今の日本映画の主流とはかけ離れた”映画とは?

“原液”のような映画をプロデュースして
――行定さんがプロデューサーとして携わった『ひとりぼっちじゃない』が3月に、『サイド バイ サイド 隣りにいる人』が4月14日に公開されました。いずれも、脚本・監督は長年行定作品で脚本を書いてこられた伊藤ちひろさん。
行定 公開の順番はこうなりましたが、最初に伊藤監督から「自分で撮りたいものができた」と渡されたのが『サイド バイ サイド』の脚本だったんですよ。でもコロナがあって、うまく進められなかった。この作品の主演は坂口健太郎で、というのは監督のたっての希望というか、もうあて書きのようなものだったので、キャストは変えずにいこうということで。
――それで、順番が変わったわけですね。
行定 そう。伊藤監督は、脚本は20年近く書いてきたけれど、自分で映画を撮ったことはないわけですよ。じゃあぽっかりと空いたこの期間に習作のような形で1本撮れないかと。世界の映画人たちは学生時代や新人の頃に習作をつくるわけですけど、日本にはそういう流れがあまりちゃんとなくて、インディペンデントであってもいきなり商業映画的な発想で撮ることが多い。まだその人のクリエイティビティもなにもわからないうちに、センスがあるとかないとか、売れたとか売れないとか判断されてしまう。そういう形で若い才能が晒されるのはどうかなと僕はずっと思っていたんですよ。だから今回はまず1本撮ってみようよ、ということで撮ったのが『ひとりぼっちじゃない』です。
――なるほど、そういう経緯が。
行定 自分がプロデュースに立つことで、日本映画界の考え方や制度ががらりと変わるものではないのはわかっている。実験的ではあるけれど、まあやってみようと。といっても、習作だからなんでもいいわけではなくて。そうするうちにキャスト候補に井口理(King Gnu)の名前が出てきて「それはちょっと面白いかもね」と。僕も自分の監督作である『劇場』に出てもらいましたけど、彼は俳優が本業ではないけれど、演技の仕事を本人も志向している。で、彼に出てもらって、結果的に商業映画に近いものになりました。ただ、内容は挑戦的です。普通ならまかりとおらないものをやっている。
――まかりとおらないもの。
行定 日本映画界は即戦力を求めるので、ちょっといいものを撮るとすぐお金を与えられて、わかりやすいものを作ることを求められる。『ひとりぼっちじゃない』はそれとは完全に逆を向いています。伊藤監督自身、商業映画の脚本家をずっとやってきて、わかりやすいものを求められてきたわけですよ。とくに僕との仕事では、よりたくさんの人に見てもらえるもの、ヒットを狙えるものをと。でもやっぱり心のなかでは「そんな必要ある?」と思っていたんだろうね。それが映画に現れちゃってる。やってみて、そこが面白かったですね。やっぱりこうあるべきだなと思いました。僕自身も最初はそういうものを志向していたはずなのに、いつの間にかそうじゃないところにいた。いま、自分のプロデュース作品がそういう方向に向いているのは必然だったように思います。
――いわゆる一般的なプロデューサーであれば、伊藤監督の原案をもっと商業的なものにしようとしたと思うんです。でも、そこに行定さんが立ったことによって、伊藤さんが志向したそのままのものが世に出たわけですね。
行定 そうですね。なんか、カルピスの原液みたいな(笑)。原液そのままじゃすんなりとは飲めないじゃないですか。水を足したり、何かを混ぜることでおいしくなる。世の中のプロデューサーってその、「俺がこれくらい水を足したよ」とか「これ混ぜたよ」ってことをやる存在だと思う。でも、『ひとりぼっちじゃない』は原液そのままです。だから、カルピスであることはわかるけど、ちょっと飲みづらいなとか、「これは水を足したほうが」という意見が当然あるような映画。ごくたまに、「この原液がいいんだよ、うっとなるのを我慢して喉を通っていくこの濃さが」みたいな人がいたりもするけど(笑)。『サイド バイ サイド』はちょっとだけ水を注いだけど、でもまだノーマルな飲み物ではないところにいますね。
――おっしゃるとおり、『サイド バイ サイド』は『ひとりぼっちじゃない』よりも開かれている印象を受けました。
行定 映画って、暇なときに見てほしいんですよ。配信で映画を観る人が増えたと思うのですが、そのほとんどはパソコンやテレビで観ている。そんなのじゃ何も感じられないじゃないですか。最近は「わからせる」ことが正しいとされているけど、ほんとうは簡単にわからせてはいけないと思っていて。映画は、そこにある空気とか、醸し出される、裏に映し出されたもの、それを感じ取るものだと思っているんですよ。
――はい。
行定 でもね、時々「おっ」という批評が出ることがあるんですよね。それはしびれますよ。『ひとりぼっちじゃない』を観たKing Gnuのファンの方が考察を書いていて、そこには「すごいたとえするね!」というものがいくつかあって。作り手が考えていることを凌駕するような飛躍をしてくれる。そういうものに出会うと、こちらも観た人から「自分が作ったものがどういうものであるか」を認識させられる。これはいちばんいい形ですよね。
――たしかに、それは豊かですね。
行定 でも実際はそうじゃなくて、とにかくわかりやすいものを作ってくれというプロデューサーがほとんどで。
――最近の「考察ブーム」の大半も、はっきりと答えが用意されていて、それを当てるだけの状態になっている気がします。
行定 『ひとりぼっちじゃない』の感想に、最近聞かれなかった「難解」という言葉がやたら飛び交っていて。監督にしてみたら、一人の男と一人の女、そこにもうひとりの女が加わることだけで成り立つ小さな物語を描きたかっただけで。その裏に漂う不気味さとかね。で、自分の中ではもちろん非常にいろんなものを張り巡らせているんだけど、あえてそれをわからせようとはしていないんですよ。感じてくれればいい。難解って思うのは、解こうとするからわからなくなるんですよ。だって答えがないから。もちろん監督の中にはあるかもしれないけど、聞いても答えないだろうし。
――答えはない。
行定 映画って絵画をみるようなものだと僕らは教えられてきたんです。『ひとりぼっちじゃない』も『サイド バイ サイド』も絵画を見るような映画ですよね。原作があって、もうどうなるかわかっているものを誰が演じるかだけを観る、なんてことの反対の場所にある。
――行定監督も原作ものをたくさん手がけて来られていますが……。
行定 小説を原作として映画化するという作業はずっとやってきたけども、僕はそれをやるときに答え合わせをしないんですよ。ほかの読者と同じように、僕がその原作から受けた衝撃とか、ここに作品を生み出す意味みたいなものを考えていくと、おのずと原作とは違うものになっちゃうんですよね。それを何十年とやってきた。伊藤ちひろも、僕の右腕としてその脚本を書いてきた。そこに生まれる矛盾と疑念があって、その答えがこの映画のシナリオとして上がってきたから、それが面白かったんですよ。こんなにわからせないものをマジックリアリズムのような表現でやろうとするのは非常に挑戦的でいいな、と。だからこそプロデュースの片棒をかついだんです。
他者からの要望を自分の動機に変えて

――それにしても、「わからない」ものをつくるのは勇気がいりそうです。
行定 「もうちょっとわかるようにしたら」と言っても監督は「わからせようとはしていない」「わかってもらおうとは思っていない」と。観る人を挑発したり、突き放しているわけではなく、あえてそうしている。もちろん、「意味がわからない」「中途半端だ」という感想にはちゃんと傷つくんだけど、それでもこの映画はわからせるためのものじゃないってことですよね。わかろうとする気持ちをむしろ大切にしている。
――きっとそこをもう少し表現してわかりやすいようにしたら、すごく褒める人が増えるかもしれないけど、そうはしない。
行定 おっしゃる通りで、ちょっとだけわからせるともっと広まるかもしれない。でも、監督はそれをやる必要はないと。(笑)そこに僕自身も納得したわけです。
――こうして二作品のプロデュースを行ってみて、なにかご自身に変化はありましたか?
行定 そうですね。僕はいつも音楽に例えて考えるんですけど、ひとつの曲をアコースティックにするか、ロックバンドでガンと鳴らすか、プロデューサーとかアレンジャーによって全然変わってくるじゃないですか。僕はロックミュージシャンになりたくてなれなかったから映画をやっているんだけど、プロデュースによって変わるのはすごく面白いなと思っているわけですよ。でも、結果的にはプロデュースをやってみて、映画はそんな簡単に何本も打ち出せるものでもないし、 結局自分で映画を作ることとあまり変わらないなと思いました。もちろん伊藤監督によって、僕には絶対撮れないものを2作、世に出すことができたことはよかったと思います。結果、自分自身をどうプロデュースしていくかをもう一度考え直すきっかけにはなりましたね。
――セルフプロデュースを。
行定 そう。たとえば庵野秀明さんは、セルフプロデュースの究極の形だと思うんですよ。「シン」がつけばなんだって自分の作風として表現できるよっていう。あのやり方は本当に尊敬せざるを得ないですよ。僕は庵野監督の『彼氏彼女の事情』ってすごい名作だと思うけど、あれも『シン』と同じことをやっているんですよね。水面下で原作を自分自身の持っているモチーフに置き換えている。『シン・世界の中心で、愛をさけぶ』やってくれないかな(笑)。 観てないって言われそうだけど。
――それはちょっと観てみたいですね(笑)。
行定 ちょっと話が逸れましたけど、まあ、いまの日本映画界では結局ヒットした人が世の中に残っていって、ヒットしなかった人たちは「あいつの映画作ってもヒットしないからな」となっていく。僕はたまたまヒット作に何本か恵まれたけど、これは意図したものではなくて、時代にたまたまマッチしたってことだとか、出演者の力によるものだと思います。これがちょっと変わったら、たぶん誰の目にも触れないものになっていた可能性はある。それは何が違ったんだろう、といつも考えます。ヒットメーカーだと言われてもヒットが約束されているわけじゃない。すぐに「あいつはだめになったな」と言われるんだろうとずっと思いながら、それに怯えながら20年以上やってきた。
――その、ここまで続けてこられたコツのようなものはあるんでしょうか。先ほど「セルフプロデュースについて考え直した」というお話もありましたが。
行定 僕は他者が僕に求めているもののほうを優先しちゃうんですよね。伊藤監督は自分の中から出てきたものを映画にしたけど、僕にはあれはできない。助監督からキャリアをはじめているから、インディペンデントで白紙の上に何かを作ろうという作業をほぼしたことがなくて。だから、僕はちょっとずるいというかね。僕のセルフプロデュースは、他者との融合のやり方ですよね。ぜんぶ他流試合なんです。外からきたものを優先している。でも、生活のために映画を撮っているのかといわれたらそんなことはなくて、好きなように戦っているし、これじゃないとという表現のしかたは自分なりに追求はしています。
――先ほどのお話にもありましたが、監督は原作をそのまま映画にするわけじゃないですよね? いまは原作にどれだけそっくりかということが求められることもありますが……。
行定 僕の場合は明らかに違います。そこは真面目で、真面目さゆえに面白みを欠いているなと自分でも思うときがありますよ。制作過程で、読み誤った予算繰りとかがあったりすると、監督として「それじゃやれねえよ!」と突っぱねてもいいんでしょうけど、僕は「じゃあここまでは表現を狭めるから、そのなかでのクリエイションは最大限暴れさせて」といって自分でフィールドを狭くしちゃう。その術をこの20年間で得てきたわけですよ。俳優にしても、この人をキャスティングするならこの予算でやってください、自分の想像を下回って言われたりする。そんな時は「この映画の中では何がいちばん大切か」を考えて、例えば今回は美術に力を入れたいから、もっと予算を使える、集客ができる俳優を選んだこともありました。そこで、「いつもやってる俳優で」とごり押しをするか、予算がクリアできる人気俳優を吟味して「これは俺が想像もしなかったけどいいかも」と考えを改めるか。その選択をいつもしているんです。一体誰がこの映画を作りたいのか?と、他者から提案された企画に疑念を抱くことがよくあるけど、そんな場合でも「自分が作りたい」にならなければ、映画になんかならないですよ。
――人の作りたいを自分が作りたい、に。
行定 僕はプロデューサーたちが集まっているときに「これは誰がやりたい企画なんですか?」と尋ねることがあります。そしたらだいたい、顔を見合わせて誰も手を挙げないんですよ。そういうときは「わかりました。じゃあこの映画は僕がやりたいです!」と言う。そういうことにして、自分の抱くイメージを守ってきた。
――そこがぼんやりしていたら、きっと映画って面白くならない気がします。
行定 CMを作っているわけじゃないから。「じゃあ自分がやりたいものをゼロからやればいいじゃん」と言われそうですけど、それは横において、創りたいと思っていたオリジナルからもぎとって原作ものにぶち込んでいるんですよね。その不完全になってしまった残骸がいっぱいあるから、もっと年とったらそれをかき集めてゼロからやろうなんてずるいことを思ったりもしているけど、結果やらないまま死んじゃうかもしれないな、とは思っています。
――それは、やりたいものを少しずつ入れ込むことで、「やりたいこと」が少しずつ達成されているからでしょうか。
行定 どうでしょうね。1本の映画をやると、次の課題が上がってくるんですよね。でも、たとえば『GO』を撮ったあと、不思議なことに僕のもとに『GO』のような企画は持ち込まれなかった。あれは金城一紀の原作があって、宮藤官九郎の脚本があって、同世代で作った映画だった。あのとき、宮藤くんに「マーティン・スコセッシの『グッドフェローズ』を観てくれ、そこに僕の作りたいことの答えが全部ある」とお願いしたんですよ。そしたら宮藤くんが観て「めちゃくちゃ面白かった」と言ってくれて、あの脚本ができあがってきた。
――なるほど!
行定 『GO』は民族の話でもあるから、そのへんも『グッドフェローズ』が参考になるしね。そうやって、あの映画はとても客観的につくったんですよね。あれを突破することで次が見えるはずだったんだけれども、次に青春映画の依頼はなくて、ラブストーリーに戻って……。そんな感じです。
映画を語れる場づくりを

――行定さんといえば「女優をうまく撮る監督」という印象があります。
行定 女優を撮る監督は女性を理解しているように思われがちですけど、逆じゃないですかね。僕はわかっていないから女優を撮っている。男が想像する女性であってほしい、その女性像みたいなのを追い求めてしまう。伊藤ちひろに脚本をお願いしていたのは、彼女が女性だからというのもあります。僕自身が全部やると、やっぱり男から見た女性像になりすぎる。だからそこで調和をとっていました。それと、僕は女優を“女優さん”として扱っていない。男性も女性も同じ俳優として扱っていると思います。女性が主役という状況が多いけれど、僕はいつも、主役の後ろ側から見ているイメージ。主役越しに、何かが起こっているんです。
――主役の一人称視点?
行定 一人称というか、肩越しですね。そして肝心な時に主役のアップが入る、という感覚。だから、そのほかのキャストは主役の肩越しに確実にその表情を捉えている。他の人達と対峙する存在として主役を捉えているんですよね。最新作の『リボルバー・リリー』はちょっと違います。しっかりと主役の顔を追いかけた。主演の綾瀬はるかは僕が撮った『JUSTICE』(2002)という短編でデビューしているんですが、そのときはもう本当に芝居ができない子だった(笑)。20年経って、すごくいろんなことができる人になっていました。要望したことをぜんぶクリアしてくる。最近、けっこう彼女のパーソナリティ、好感度の高い部分に頼りがちな作品が多い気がしていました。でも、彼女は別のものになれる女優さんですよ。『リボルバー・リリー』ではそれを体現できるんじゃないかな。
――それは楽しみです。
行定 女優でいったら、松岡茉優もすごいと思ったな。撮影したとき、ぜんぜんコントロールできなかった。完全に自分の想像を覆してくるんですよ。「やりすぎじゃない?」と思うような部分もあった。でも編集してみたら、じつはそこが効果的だったりして、ぜんぶ肯定できた。でも僕はたまたまですけど、同じ俳優を続けて使うことはないということで知られていて。以前も、珍しくある女優さんにラブコールを送ったんです。そしたら別の、僕が監督する予定の作品でプロデューサーがその女優さんに依頼をしていた。で、彼女は検討した結果、プロデューサーからの作品を選んだ。「両方受けていただいてもいいんですよ」と言ったら、「行定さんは1回やると次のチャンスはないから、ちゃんと考えたほうがいい」とマネージャーに言われたと(笑)。
――行定さん自身が意図しているわけじゃないのに(笑)。最後に、行定さんの今後の野望を伺っているのですが。
行定 野望というか、けっこう現実的なことなんですが、映画館をつくりたい。
――おお!
行定 できれば恵比寿あたりに。10年前くらいからやりたいと思っていて。人が集う場所をつくりたいんです。ネットサロンにすれば簡単に叶うかもしれないけれど、やっぱり実際に集いたい。ごはんを食べられる場所もあって、2スクリーンくらいあって、毎日毎日トークショーをやっている。「こんな映画って面白いでしょう」という話をしている。
――いいですね。
行定 10年前頃から、映画館に足を運ぶ人が減っていくことを感じていて。直後に、自分がつくった映画『劇場』がいきなり配信ではじまるというところに立たされたときに、これはいよいよだなと。ただ、世界配信になって、一晩で270カ国に僕の映画が広がるわけです。これまでは一生懸命映画祭に出て、広めていこうとやってきたのに、一瞬にして奇跡のようなことが起こるわけですよ。コンゴ共和国の人から、何語で書いてあるかもわからない感想が上がってくる。そういう経験をすると、「これはとんでもないことだ」と。でも、だからこそ逆に、映画を直接物語れる場所を作りたいなと。映画祭みたいなことが毎晩行われている場所。それが実現できるといいなと思っています。

■プロフィール
行定勲(ゆきさだいさお)
1968年生まれ、熊本県出身。長編第一作『ひまわり』(00)で、第 5 回釜山国際映画祭で国際批 評家連盟賞を受賞。『GO』(01)では、第 25 回日本アカデミー賞最優秀監督賞をはじめ数々の映画賞を総なめにし、一躍脚光を浴びる。また『世界の中心で、愛をさけぶ』( 04)は同年実写映画 1 位の大ヒットを記録し社会現象となった。以降、主な監督作に『北の零年』( 05)、『春の雪』(05)、『クローズド・ノート』(07)、『今度は愛妻家』(10)、『パレード』(10/第 60 回ベルリン国際映画祭パノラマ部門・国際批評家連盟賞受賞)、『真夜中の五分前』(14)、『ピンクとグレー』(16)、『ナラタージュ』(17)、『リバーズ・エッジ』(18/第 68 回ベルリン国際映画祭パノラマ部門・国際批評家連盟賞受賞)、『劇場』『窮鼠はチーズの夢を見る』(20)など多数。
23年公開の伊藤ちひろ監督作『ひとりぼっちじゃない』『サイド バイ サイド 隣にいる人』では企画・プロデュースを務め、24年8月11日公開の監督作に『リボルバー・リリー』が控えている。
FMK(エフエム熊本)にて『月刊行定勲』(https://fmk.fm/kantoku/)が放送中(17年目)
<最新作情報>
『サイド バイ サイド 隣にいる人』(https://happinet-phantom.com/sidebyside/)
4月14日(金)より TOHOシネマズ 日比谷ほか 全国ロードショー
監督・脚本・原案:伊藤ちひろ
出演:
坂口健太郎
齋藤飛鳥 浅香航大 磯村アメリ
茅島成美 不破万作 津田寛治 井口理(King Gnu)
市川実日子
配給:ハピネットファントム・スタジオ
©2023『サイド バイ サイド』製作委員会
サイン入りポラロイド写真を抽選で3名様にプレゼント!
『行定勲さんポラロイド写真』
(注)必ずご住所をご記載の上お申し込みください。
ご意見ご感想も添えて頂ければ今後の参考にさせて頂きます。