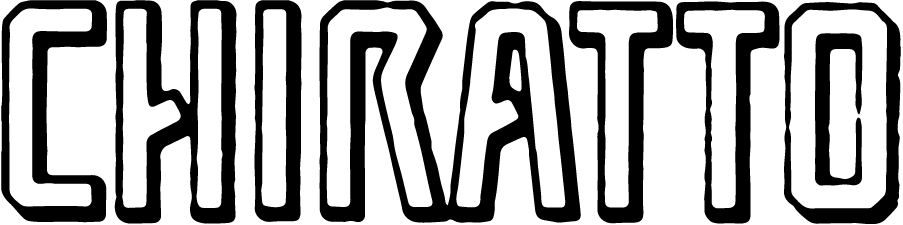第二十二回特別インタビュー いしいしんじ(小説家)【後編】

前回に続き、いしいしんじの実弟であるフォトグラファーと義妹のライターが、偶然の巡り合わせでお届けすることになった、3日間にわたる密着取材。前編は家族報のような内容もありつつ恐縮でしたが、身内の話や距離感で、“いしいしんじになるまでの石井慎二”に着目。後編は小説の書き方や、作家としてのあり方など、小説家・いしいしんじの変遷が垣間見える話に転がっていきました。
【後編】
三鷹天命反転住宅は、集合住宅というよりも遊園地のような雰囲気を醸すカラフルな建物で、大通りを挟んだところから見てもひときわ目立っていた。しんじ兄が滞在している部屋では、明日のイベントのための設営が始まっていて、フランスの国旗やらギターやらがぶら下がり、普通ではない家がさらに楽しい感じになっていた。モーグルのコースのようにデコボコの床、声が反響する球体状の部屋、ローマ円形劇場の舞台のように低い位置から周囲を見渡せるキッチン、扉で仕切られていない開放感のあるトイレ……。「死なないための家」というコンセプトの通り、暮らすことはもとより、生きることそのものを試されるような空間だ。弟の孝典は到着して早々に設営を手伝い始め、しんじ兄は住民の子どもと遊んでいる。まるで石井家の正月のような安定感のある光景だ。
しんじ兄の活動のひとつに、「その場小説」という即興演奏のように小説を書く試みがある。自分が過去に書いた小説を朗読するのはつまらないからと始めたらしいのだが、その土地、その場所、そこに集まった人たちの雰囲気を感じながら、一編の小説を書き、書くのと同時に読み上げていく。居合わせた人たちもある部分では創作に関わりながら、物語が生まれる瞬間を一緒に体験できるわけだが、子どもと遊んでいるときのしんじ兄も言葉を書き留めはしないものの、その場小説の延長のようなことをやっているように見える。
設営をしたり、子どもと遊んだりしている合間を縫って、物語を作ること、小説を書くことについて改めて聞いてみた。

気がついたら2時間半もその場小説をやっていた。
――昨晩はこの部屋でどんなふうに過ごしましたか?
いしいしんじ(以下、しんじ):泊まれるのが嬉しかったから、いろんなところで寝てみたんよ。最初にハンモックで寝て、畳の部屋の布団で寝て、デコボコの床でも寝てみたんやけど、シャワーの横の斜めになった床が意外に気持ちよかったなあ。
――こうやって日が差している時間と夜とでは、雰囲気がまた違いそうですよね。ところで、どうしてここでイベントを行うことになったのでしょう。
しんじ:もともとはここの住人の岡本くんが、「その場小説」を見に来てくれたのが最初。その場小説って文字通り、その場の雰囲気で物語が出てくることの面白さを大事にしていて、著作権がどうこうとか、書き上げたものを保存しようって考えも特になくて、言葉がばらまかれていく感じが楽しかったんよね。岡本くんもそれを面白がって、山形ビエンナーレとかにも来てくれて。今までいろんなところでやってきたんやけど、何回目かの山形ビエンナーレでやったその場小説が素晴らしかったんよ。また話が長くなんねんけど(笑)。たしか120人くらいお客さんが来てくれて、その場小説が一番最後のイベントやった。唇の形みたいな細長いギャラリーで、入った瞬間、お客さんがずらっと座っている感じが船に乗ってるみたいやなと思って、お客さんにも話に入ってもらいたくて名札をつけてもらってな。ただしさんっていうお客さんがいたら、《船が港に着いて、ただしはタラップに足をかけながら》と書いてから、「ただしさん、今日は朝ごはん何食べました?」と僕が聞いて、「ハムエッグです」って答えが返ってきたら、《今日のハムエッグはちょっと固かったなと思いながら乗船した》っていうふうに、ひとりひとりに質問しながら物語をつないでいったわけ。
全員が乗船して出港したんやけど、だんだん気配がおかしくなってきて……。あるとき、船の中のみんなが死んでいることがわかった。この船は出港したように見えて、実は海の底に沈んでたんよ。子どもたちに「どうして窓の外に鳥じゃなくて、魚がいるの?」と聞かれて、自分たちが死んでいることに気づいたお父さんやお母さんが、何も言わずに子どもを抱きしめたりして。そしたら女の子が「私たちだったら、この船をもう一度浮かべることきっとできる!」と言って、いろんなアイデアを出していくんやけど、ひとりの子が「この世で一番軽くて気持ちのいいものは歌だから、歌えばいい」ってひらめいた。それで僕がお客さんひとりひとりに好きな歌を聞いて、ある人は『いとしのエリー』を歌い、ある人は『ずいずいずっころばし』を歌って、船が徐々に浮かんでいく話になっていったんよ。そうやってまさに船が水平線に顔を出すくらいのときに、山形ビエンナーレの事務局の人がそーっと会場に入ってきて、「すいません……、みんなもう打ち上げの席で待ってるんですけど」って(笑)。1時間で終わる予定やったのに、その時点で2時間半くらい経ってて、会場の使用時間もこれ以上延ばせない。あと10分で終わってほしいってことになって、なんとか浮上するところまではこぎつけたんやけど、全員には聞かれへんかった。だからそのあと、みんなに聞いて完全にした原稿を作って、事務局を通して全員にプレゼントすることにしたんやけどね。
――そんなに壮大な話になったんですね。
しんじ:そのときの気配が僕のなかに残っていて、最初は岡本くんから三鷹天命反転住宅でその場小説をやってほしいって言われたんやけど、お客さんも10人限定やし、ほかではできないようなことがええなと思って。三鷹天命反転住宅が「死なないための家」やったら、ここに来るのは死んでしまった人でもええことになるよね。ジョン・レノンとかピカソとか清少納言とか、今はこの世にいない人たちが死なないで、みんなで一緒に住んでるアーティスト・イン・レジデンスがええんちゃうかなと思いついて。だってジョン・レノンとかって、誰の心にも生きてる人やしね。参加するお客さん全員にそういう人たちになってもらって、僕はこの住宅を設計した荒川修作になって対話をしていく。その場小説は事前に何も決めずに、言葉にするのと同時に書いていくんやけど、今回はもうちょっと設計図みたいなものを作って、お客さんと一緒に話を作っていこうと思ったんよ。
ほんでこの家の気配というか、命みたいなものを体で感じたくて、さっき話したみたいに昨日はいろんなところに寝っ転がってみた。どうしてここでは人が死なないのかっていう納得感を、自分のなかにわずかでも入れたかったんよね。寝るって、言ってみれば死ぬことでもあるから、寝っ転がって死んでみたんやけど、やっぱり死んでなくて、起きて荒川修作のDVDを観ながら、気になったこととか思いついたことをメモしてたんよ。《みんな、なんで人が戦争をするか知ってるかい? 絶望しているからだよ。何の楽しみもないからだ》みたいな言葉に感動したりして。《人間っていうのは借りもので生きているんだ。ひとつくらいはオーセンティックな本物を生きてみようと、6歳のときに思った》っていうのもめっちゃええやん(笑)。そんなわけで明日は、千利休とかジャンヌ・ダルクとかアインシュタインとかも来ると思う。

現実の出来事が、小説に対して目配せをしてくる。
――わかったような、わからないような(笑)。でも、その場小説とは違うということはわかりました。その場小説と、机に向かって書く小説は、しんじ兄さんのなかで違うものですか?
しんじ:それがね、だんだん同じような感じになってきてるんよ。そもそもその場小説っていうのは、その場でパッと思いついたこととか、起きた出来事から、反射的に書いていくもの。前に、渋谷のラブホ街にあるバーでその場小説をやったことがあるんやけど、開演15分前くらいに「ちょっとその辺を散歩してきますわ」って出ていったのね。そしたらラブホの前にちっちゃな噴水というか池があって、そこのフチを猫が歩いていて、まさかと思ったんやけど、バッシャーンって落ちてしもて(笑)。傾斜がきつくて猫が這い上がれなくなってるから、溺れてしまうと思ってズボンと靴を脱いで、助けようとしたのよ。猫ってすごいねんけど、その瞬間、エビみたいに体を折りたたんで、後ろ足で水を蹴って飛び上がって、もんどり打ちながらアスファルトに転がって、チーターみたいにすごい勢いで走っていなくなってしまった。うわー、今のは何やったんやろうって、こっちもびっくりしながらズボンと靴を履き直して会場に戻ったら、「ではいしいさん、お願いしまーす!」っていきなり言われて、《俺はラブホ街を歩いていた》と話が始まった(笑)。さっきの出来事が衝撃的やったから、いかにそれを克明に描写するかってことになってしまったんよ。今のは顕著な例やけど、震災が起きて間もない頃に別府のアートイベントに呼ばれて、元ストリップ小屋でその場小説をやったこともあったなあ。やっぱりどうしても震災の話になってしまうんやけど、そのとき置かれているシチュエーションが、直に小説になりやすいとは思う。明日のイベントでやるのはその場小説ではないけれど、水面下でいろんな物語がイントロみたいにすでに始まっていて、だんだん目に見えてきたり、聞こえてきたりしたものを形にしていく、みたいなことなんやないかな。
その書き方は連載中の『チェロ湖』もまったく一緒で、ひとつの物語を2年半も書き続けてると、やっぱりいろんな出来事が起こるわけやん。思いもかけなかったようなことが再び浮上して、40年後の登場人物の子どもに作用してしまったりとか。書いている自分がそうしようと思って意図的に動かすというよりは、ほったらかしにしてあるから、つながるものはつながるし、つながらないものはつながらない。よくよく考えてみれば、初期の『麦ふみクーツェ』とか『プラネタリウムのふたご』とかも似たような書き方ではあるんやけど、生きている時間というか実生活みたいなものも含めて、小説に関わってくるようになったのは松本に住んでいた頃からかなあ。『みずうみ』っていう小説で、最初に自分の固有名詞とかが出てきたと思うから。
――2年半かけてひとつの物語を書くのは、今までで一番長いですか?
しんじ:『ポーの話』は3年くらいかかってるかな。でもそのうちの8カ月は、何も書かずにひたすら待ってたんやけど。
――待っていた?
しんじ:うん。角田光代さんと対談したとき、その話をしたんやけどね。「起きて毎朝、机には向かうけれど、おっきい話がだんだん形になって、出てくるまで待っとこうと思って、8カ月書かなかったんです」って。そしたら「このキチガイ!」って言われた(笑)。100人くらいお客さんが入ってる公開対談やったのに。「酔っ払ってんの?」って聞いたら、「酔っ払ってないよ!」って(笑)。

――なるほど(笑)。その場小説ではなく普通に書く小説も、どう展開してラストはどうなるなど、いわゆるプロットみたいなものは最初に考えないんですか?
しんじ:『チェロ湖』は長い小説になるやろうから、『新潮』の矢野さん(編集長)と相談してあらすじってものを初めて考えてみようかなって言ったんよ。で、やってみたんやけど、考えられへんかった(笑)。やっぱりそういう書き方は向かんなあ、と。ちょっと先のことならわかるよ、もちろん。でもいろんなことが重なって、どうなっていくかっていうのは、遠すぎてわからへんの。『ごはん日記』っていう日記を毎日つけてるんやけど。今は都合でウェブサイトが止まってるんやけど、ずっと書き続けてはいて、日記みたいなもんでも書いているうちにわかることが結構あるんよね。たとえば昨日、マン・レイの展覧会を観て、彼が生きていた時代のこんなところが自分は羨ましかったんやって、書いたり話したりしてるうちにわかってくるんやけど、小説なんかはほんまにそんな感じやなあ。
『チェロ湖』は、蓄音機とかレコードが大きなテーマの小説やねんけど、たとえば僕が5年くらいずーっと探してたけど、世界中のレコード屋さんに1枚も出回らなかった、エディット・ピアフの『ミロール』っていう歌があんねん。それが出てきたってカナダのレコード屋さんから連絡があって、もちろん買いますって返事をしたんやけど、その3時間後に『ミロール』が入ったんやけど買わないか? ってブラジルのレコード屋さんからも連絡が来たんよ。もちろん全然違う出どころやねんけど、5年も探しててまったく同じ日に連絡が来るなんてことがあったら、これは小説に対しての目配せやなって思ってしまうわけ。自分の生きてる時間が、なんやチカチカ言うてるなって。そうすると、そのとき考えていたことにチカチカが加わって、小説がぐいーっと大きく進んだりするんよ。
――その場小説は最たるものですけど、そうやって即興的に書いていくとき、頭のなかがどんなふうになっているのか不思議なんですよね。どうしてこんな、曲芸みたいなことができるんだろうって。
しんじ:たとえばライブペインティングをする人が、ダ・ヴィンチとかベラスケスみたいな精密な絵を描いたりはしないやん。どっちかいうたらウィレム・デ・クーニングみたいな、アメリカの抽象表現主義っぽい絵になってしまうやろ? だけど別に、ベラスケスみたいなライブペインティングをやったっていいわけよ。丁寧にじわじわと目を描いて、塗り込んでいって、途中で終わってしまってもええと思うねん。ライブペインティングは音楽に乗って、踊るように勢いよく描くもんなんやってみんな思い込んでるみたいに、小説も机に座って書くもんなんやって思い込んでるから、その場小説もできないって思ってしまうんやないかなあ。自分としては家の中で書く小説でも、その場小説でも、そんなにすっ飛んだことをやってるつもりはなくて。目の前のことをやんねんけど、その先に何があるのか見えないぶん、どうしてもグネグネ行ってしまう。でも少しずつ掻き分けながら進んでいくと、全体が見渡せるようになってくる。だから最初の時点で、こういうことを表現しようとか、こういうテーマで書こうっていうのは何もないというか、わからない。もっと言うと、なんでこれを書いてるのかも。本を出してからのインタビューとか感想で、「この小説はこういうテーマなんですよね」って言われて、ああそうやったのかって思うことは多いんやけど。

文学や音楽や絵は、人間関係のややこしさから一番自由なもの。
午後、詩人・吉増剛造さんの個展『怪物君』のオープニングに合わせて、東麻布のギャラリー「Take Ninagawa」へ。ケイ線を細かく引いた紙に、吉本隆明氏の作品の書き写しや自身の詩が極小の文字で綴られ、その上にカラフルなドローイングが重ねられている。「全身詩人」と称される吉増さんは、マスクの上からもそれとわかる優しい笑顔を浮かべながら、ギャラリーの入り口に座っていた。
しんじ兄が敬愛し、懇意にしている人たちを通して見えてくる、理想とする作家のあり方について。

――吉増さんとは、どんなふうに知り合われたのでしょう?
しんじ:いろんなところでお会いしてるんやけど、茶道関係の本をたくさん出してる淡交社っていう京都の出版社からの依頼で、僕がさまざまな人のところに会いに行って対談をする企画があったんよ。ただ話をするだけっていうのももったいないから、お茶を点てるような感覚で、何かしら自分の好きなものでもてなそうってことになって、それやったらSP盤(蓄音機用レコード)かなと思って。レコードのことをお皿っていうし、茶道は五感で味わうものやから、音楽ってなんかちょうどええやん。ほんで、湯浅学さんとか大竹伸朗さんとか山極壽一さんとか柳美里さんとか、いろんなところに住んでいる会いたい人をあげて、吉増さんもそのひとりやったんよ。吉増さんとはそれ以前に三田文学の関係で知り合ってはいて、最初にお会いしたときから僕のことを異様に知っててくれて、どうしてですかっていうくらい褒めてくれるわけ。そのあと、東京国立近代美術館で吉増さんの大回顧展があって、初日に行くつもりやったんやけど、どうしても行けない用事ができてしまって。ほんまに残念やったんやけど、花を贈るのもなんか違う気がして、A4の紙にさっきの『怪物君』みたいにぎっしりと、吉増剛造作品を観ることがどれだけ素晴らしいことなのかを書いて、美術館にFAXしたんよ。電報でもメールでもなく、FAXがいいような気がして。しかもカラーFAX。そのときのオープニングには知り合いも何人か行ってて、吉増さんがスピーチしてるところとか、あとからいろんな写真を見せてもらったんやけど、そのA4の紙を吉増さんがずっと小脇に抱えて写ってるわけ。なんかねえ、とても律儀というか、優しい人やねん。
でな、その対談でポータブル蓄音機を持って、ご自宅に行ったの。最初は「いしいくん、この辺にお香を焚いてもいいかな? 煙って邪魔にならない?」って穏やかに話してたんやけど、音楽が鳴り出したら急に黙り込んでしまって。ポータブル蓄音機ってトランク型で、フタを開けるとターンテーブルがあるんやけど、ターンテーブルをじいっと見つめてたと思ったら、そのなかに頭をガバッと突っ込んで、「おいっ! おまえは一体どういう旅をしてここまでやってきたんだ?」って語りかけ始めて、2時間くらいずっとやってた(笑)。ときどきふっと素に戻って、「いしいくん、これって見せたことあったかな?」って言うから「なんですか?」って聞いたら、「石なんだけど、これも楽器になるんだよ」って床をガンガン叩き出してな。よく見たら床が傷だらけで、「これは武満徹にもらった石だ! 楽器だ!」って叫んでる。いいんかな、俺、こんなんひとりで見せてもらってって思ったわ(笑)。俺は吉増さんのやってることが単純に好きやけど、獣みたいな人やから、近寄ってくる人に嘘がないかどうかわかるんやと思うのね。荒川修作さんも詩人に生まれてたら、あんな感じやったんちゃうかな。さっき吉増さんに「荒川さんとは面識ありましたか?」って聞いたら、「あったよ、ケンカした」って言うてはったけど(笑)。
石井孝典(以下、孝典):鬼海弘雄さんもそうやし湯浅学さんも大竹伸朗さんも、しんじ兄ちゃんが仲よくしてる人は、お互いのことを単純に好きで、この人は自分に対して下心みたいなのが何もないってわかってるよね。吉増さんにもそれは感じた。
しんじ:みんな大先輩やし、いろんな人を見てきてるから、そういう勘が鋭いというか、すぐわかるんやないかな。文学賞の授賞式とかに行くこともあんねんけど、いろんな人がいろんなところで名刺交換とかをしてるの見ると、不思議に思うねん。受賞した人に「おめでとう」を言ったり、小説について褒めたりするために集まってる場ちゃうの? って。
孝典:まあ俺らにはわからへんけど、その人たちも仕事必死なんちゃう?
しんじ:せやなあ(笑)。でも文学とか音楽とか絵って、人間関係のややこしさから本来は一番自由なものやろ。『ある一日』って小説で織田作之助賞をとったとき、湯浅さんが授賞式に来てくれて、『毎日は一日だ』っていうオリジナルの曲を歌ってくれたやん。音楽に合わせて一日(ひとひ。息子)がぴょんぴょん飛び回ってたんやけど、あんなに楽しい文学賞の授賞式は見たことないって、いまだに言われるんよ。だからもっと面白い会にすればええのにな。そういう点でも、吉増さんのことは純粋に尊敬してる。ああいう人こそ打算なく創作に打ち込んで、すごいものを作り続けてきたんやろうし。俺なんか全然足元にも及べへんけど、心意気だけはそうありたい。

先にもらっている感激を糧に小説を書く。
――人間関係のややこしさから自由でいることと、京都で暮らしていることに何か関係はありますか? というか、東京、三崎、松本、京都など今までいろんなところで暮らしてきて、住む場所と創作の関係をどう捉えているのかなと思って。
しんじ:京都にいるからわからないことはたくさんあるし、東京にいたら、もしかしたら毎週にでも吉増さんに会いに行って、いろんなことを教えてもらったりもできるかもしれへん。でも京都にいると、ホホホ座とか100000tアローントコみたいな本屋さんやレコード屋さんと自分が、ほんまに同じ目線で、同じところで一緒にやってる実感があるんよ。京都だと、チームみたいなのをわざわざ作らんでも、その都度集まって面白いことをやっては解散して、また集まってっていうことが自然にできるんよね。東京は物理的に広すぎるし、人も多いから難しいんちゃうかな。でも住む場所には、その都度いろんな影響をもらっていると思うし、三崎も松本も家はないけど、全部まだ自分の住み場所やと思ってる。だから転々としてるんやなくて、馴染みの場所というかテリトリーが広がっているだけな気がする。
――それは東京も含めて?
しんじ:東京もそうなんやろうけど、俺が知ってたときの東京はネットがなかったし、みんなブラウン管でテレビ見てたから。人と会ってしゃべるのが普通やったし。かろうじて人と人が顔合わせて、笑ったり怒ったりしてる世の中やったからなあ。こないだある記事で読んだんやけど、今はネットの時代やから、ヨーロッパのスポーツライターはいかに即効性があって、体に副作用のない合法ドラック手に入れて、速く書くかが勝負になってるんやて。たとえばツール・ド・フランスも毎日結果とかインタビューを読めるのは、その裏でスプリンターの勝負よりも激しいライティング合戦が繰り広げられているからなんよ。受け手側としてはどこかの記事で結果を知ったら、ほかの記事を読む必要がなくなるから、誰が一番乗りで面白い記事を書けるか、ほんまに秒単位のライティングらしい。でもな、スポーツっていう体を使った勝負の魅力を、世界中に広める仕事をしている人が薬漬けって、どういうことやねんって思うよな。あれだけアンチ・ドーピングって声高に言ってるような人たちやのに。リーガルかイリーガルかなんて法律の違いだけであって、リーガルでもフィジカル的にきっとキツいものなんやろうし。そうやって便利さと引き換えにしてるものって何なんやろうって、京都にいるとより感じることはある。コロナっていうのもあるやろうけど、最近は新しい編集者と顔を合わせる機会だけでなく、電話で挨拶を交わすようなことすらなくなってたりするもんなあ。別に「京都に来いや!」って気持ちはないねんけど。
孝典:でも松本に住んでたときは、編集の人とかも喜んで足運んでたよな。
しんじ:喜んで来てくれてたよ。三崎の祭りのときもすごかったもんな。うちの兄ちゃんも泊まって、お好み焼きを焼かされてたもんなあ。みんなも「大阪の人だから、おいしく焼けるでしょ!」って(笑)。前に大竹さんと話してたとき、「いしいくんさあ、岡潔って読む?」って唐突に聞かれてな。「数学者の岡潔さん?」「そうそう、岡潔がいいこと言っててさあ。いまだに誰も、心を解明した人間はいないって。俺も、心がわからないから作品を作るんだよね」って。そうやっていろんなところを探って、自分の信じてる芸術のあり方に喝を入れるのは、さっきのスポーツライターのドーピングの話とは真逆のことで、かっこいいと思うよな。だってほんまに自分の嗅覚で探して、出会うわけやろ? 昨日、ベートーヴェンの話をしたけど、聴いてるとやっぱり自分も弾きたくなってくるんよ。うちにピアノあるし、もう習う気持ちでいるもんなあ。ほんで、じいさんになるまでに、ピアノ・ソナタ第32番を一回でも弾いてみたい。要はそういうことなんちゃう? 自分が出会って、ほんまにすごいと思ったものは、体で実感したいもんやろ。結局、自分が小説を書くのは、それだけ小説に感激した経験があるからやし、吉増さんとか大竹さんとか鬼海さんみたいなすごい人と出会って、本気で感激したことを糧に一生懸命書いてるわけで。自分からこうしたいっていうより先にもらってしまってるから、出すだけみたいな感じなんよね。
今書いているのは、熊本にまつわる100の物語。
――9月25日から熊本市現代美術館で開催される『こわいな!恐怖の美術館』展に向けて、今、準備をしているそうですね。
しんじ:『100ものがたり』っていう作品で、全部で100話書く予定やねんけど、1日3話ペースで書かないと間に合わへんから、今朝も3話書いてきたんよ。熊本は昔から不思議と縁があって、京都に住む前は引っ越し先候補のひとつでもあったくらい。熊本市現代美術館の学芸員さんとも10年くらいの付き合いやねんけど、去年久しぶりに連絡が来て、熊本地震をきっかけに「怖い」っていう感覚をアートで表現する展覧会をやろうと思って、いしいさんの小説が思い浮かんだんですって言ってくれて。なんやそれは、僕の小説を楽しんで読んでくれてるというか、深く感じ取ってくれてるんやなってすごく嬉しかったんよ。どんな形になるのか、まだ全然見えてなかったんやけど、まずは熊本に行かなあかんと思って。
学芸員さんが熊本駅に迎えに来てくれて、「阿蘇のほうに1時間半くらいドライブします」って言うねんけど、何を見に行くかは特に触れず、お互いの近況なんかを話してたんよ。そしたらまっさらな感じの高速道路に入ったから、「新しい道ですね」って言ったら、「この辺は地震で全部崩れて、こないだやっと復旧したんです」って教えてくれて。展望台みたいなところに連れて行ってくれて、谷の向こうに何かがぶら下がってる。よおく見たら、橋やった。阿蘇大橋が崩れた状態のまま遺されてたんやけど、いろんな人が新しい道路を通ってその橋を見に来てるわけ。「あー、引っかかったのねえ」って言ってるおばちゃんとかもいて、にこやかって感じでもないんやけど、満足したような様子で帰っていく。
熊本地震 震災ミュージアムっていう、もともとは大学の校舎だったところにも連れて行ってもらったんやけど、地割れした断層が遺されていたり、机がひっくり返って割れたガラスが散らばってるところもそのまま展示してはる。案内してくれた人に「ほこりとか溜まるでしょう?」って聞いたら「拭きよります」。「じゃあ、ひっくり返った机の周りとかも掃除するんですか?」「当たり前ですよ」って。なんていうか、ほんまにここの人たちは熊本の土地っていうものと通じ合ってるんやなって思ったんよ。震災を忘れてはいけないとか、そういうきれいごとではなくて、体の底からの愛情として地面とつながっている状態を保ちたいんやなって思った。展望台で会ったおばちゃんもそうやったけど、怖い気持ちと面白いとか満足っていうのは、裏腹なんやろうなあ。お化け屋敷なんかはまさにそうやし、本当にすごいものって怖かったりもするし、その逆もある。怪談にも「百物語」って言い方があるやない? だったら、熊本にまつわるいろんな話を100個書いてみようって思いついて。これが取材したときのノートで、最初は表に「熊本」って書いてたんやけど、あとから「と」を足したんよ。それで「熊」と「本」が熊本中を旅して、いろんなお話を集めてくる話になった。今、46話くらい書いたかな。この先どうなるのかは、やっぱりわからへんのやけど。

東京滞在3日目に行われたイベント「三鷹天命反転住宅 マジカル・ワンダー・ツアー『Reversible Utopia』」について、ここでは多くを語らない。言葉で説明しようとすればするほど、きっと読む人を混乱させることになるだろうから。参加した方々も、リッケンバッカーを持たされたり、着物を着せられたり、絵筆を持たされたりと混乱しながら楽しんでいた。いしいしんじは荒川氏になってしゃべり、《ぼくは荒川修作、6歳》などと短冊に書き連ね、その言葉たちが空中にゆらゆらと漂っていた。そしてさまざまな混乱・混沌を、三鷹天命反転住宅という大きな容れ物が受け止めていた。

終了後のトークショーでは、荒川氏になった時間を次のように振り返っていた。
「参加者のどなたかが『優しい荒川修作でした』と言っていたそうなんですけど、たしかに僕もそんな気がしました。人に優しくなっていくんです。決してわがままに突っ走ったり、言いっぱなしな人ではなく、自分の言動によって相手がどう輪郭を変えるのかちゃんと見ていて、その人をどこに運ぼうか絶えず考えているような人なんだと思います」
そして最後に、この言葉を裏付けるようなエピソードを披露した。
「2日前に訪れた乃木坂の画廊で聞いた話なんですけど、荒川さんはそこにいる人たちが一番してほしくないような話をして、場を凍らせる才能がすごいらしいんです。たとえば自分の個展の会場とかで、『こんな美術館、くだらないんだよ! 全部ぶっ壊して僕の建築を建てる!』と言ってしまうような。でも話があまりにもエスカレートして、スタッフが『先生、そろそろ』ってこっそり言うと、『じゃあ、これくらいにしよう』とあっさり終わってくれるらしい(笑)。なので僕も……、じゃあ今日はこのくらいで終わりにしよう」

■プロフィール
いしいしんじ
1966年大阪市生まれ。京都大学文学部卒。1996年、短篇集『とーきょーいしいあるき』(のち『東京夜話』に改題して文庫化)、2000年、初の長編小説『ぶらんこ乗り』刊行。2003年『麦ふみクーツェ』で第18回坪田譲治文学賞、2012年『ある一日』で第29回織田作之助賞、2016年『悪声』で第4回河合隼雄物語賞を受賞。近著に『げんじものがたり』。『新潮』2019年2月号から『チェロ湖』を連載中。9月25日(土)~12月5日(日)、熊本市現代美術館で開催する『こわいな!恐怖の美術館』展で、新作『100ものがたり』を発表。
取材協力:三鷹天命反転住宅 イン メモリー オブ ヘレン・ケラー
© 2005 Estate of Madeline Gins. Reproduced with permission of the Estate of Madeline Gins.
三鷹天命反転住宅クラウドファンディング実施中!(2021年12月10日まで)
https://motion-gallery.net/projects/savetherdloftsmitaka