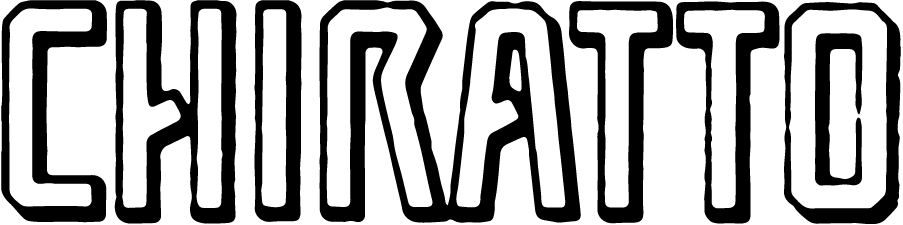第二十四回特別インタビュー 赤堀雅秋

脚本家・演出家としてずっしりと重みのある人間を描いてきた赤堀雅秋さん。一方俳優としてさまざまな場所に呼ばれる彼は、媒体を越えていつもたしかな存在感を残しています。俳優としての自分をどう捉えているのか、どんなふうに作品を作っているのか。演劇との出会いから劇団時代に獲得したこと、演出家としての転換点など、ナイロン100℃『イモンドの勝負』稽古中の赤堀さんに、たっぷり語っていただきました。

──『イモンドの勝負』の稽古まっただなかの時期に、ありがとうございます。赤堀さんはケラリーノ・サンドロヴィッチ(以下、KERA)さんの舞台にたびたび出演されている印象がありますが、今回の作品は現段階でどんな感触ですか?
KERAさんの演出を受けるのはもう舞台では7回目なんですけど、今回KERAさんは非常に実験的なナンセンス作品を試みようとしているんですよ。けれど自分はナンセンスというジャンルに対する素養がまったくないもので、最初は戸惑いしかなくて。この歳になって恥ずかしいですけど、舞台経験ゼロのイケメン俳優のように「自分が足を引っ張ってるんじゃないか」と思ったりもして。今もまだ混乱の中にいますが、とにかくやるしかないですね。
──KERA作品には慣れているように見える赤堀さんが戸惑うほどの作品……。
過去出演してきた作品にも不条理な部分はたくさんありましたけど、これまでは自分の役をどう全うするかという部分に腐心すればよかった。今回は何役も与えられたのもあって、どうしていいかわからない状況で。まだ稽古途中なので、これから先さらに役が増えていく可能性もありますね。たとえばおばあちゃん役をやるとか。自分はとくに劇団においてはボソボソした表現をしてきた人間で。演劇的な表現も極力避けてきたので、キャラクターになりきるのもまだ恥ずかしくて……。避け続けて何十年、とうとう捕まっちゃいました。若い頃ならただ恥ずかしがってテレて終わったかもしれませんけど、もう50歳ともなるとテレている場合でもないので、そんな自分も楽しみながらやろうとしています。
──赤堀さんは演劇をずっとやってこられた方ですが、演劇的な表現が好きではなかった?
若い頃は特に偏見しかなくて。40代になってからは自分とは全然違う表現をされる方の作品も斜に構えず楽しんで観られるようになりましたけど、いざ自分が役者としてやるとなるとね……。そもそも絶対にオファーはないでしょうけど、たとえばNODA・MAPは観るのは好きですし尊敬もしますけど、そこに出ろと言われても恐怖で戸惑ってしまう。
──では、今回はそれを乗り越えて、役者として新たなチャレンジをしているわけですね。
傍から見たらそんな大層なものでもないんでしょうけど(笑)。KERAさんって、無意識かもしれませんが毎回僕にハードルを作るんですよ。たとえば舞台上での濡れ場だとか、今回のようにキャラクター的な役をやるとか。今まで自分がやったことのない、絶対自分じゃやりたくないことを突きつけられたり、「お前自分の作品ではやらないだろ」という役柄を当てられることがけっこうある。だからKERA作品はつねに脂汗が出る現場なんですよね。役者なんだから、それは当たり前のようにやれよという話なんですけど。
──赤堀さんは役者として、映画、ドラマ、演劇とジャンルを越えてたくさんの作品に呼ばれていますよね。
そんなに呼ばれてる自覚はないですけど(笑)。ただ自作の場合、僕は便利なんですよ。僕くらいの年齢や立ち位置の役者さんを呼ぶと、ふつうは「もうちょっと見せ場作らないといけないかな」とか「番手をよくしないといけないかな」とか気を遣うんですよ。でも演出家の僕は役者の僕を雑に扱っても大丈夫だから。セリフがなくても文句は言わないし(笑)。
──役者としてほかの舞台に参加するとき、ご自分の中で脚本家・演出家である自分をはっきりと切り離しているものですか?
分けようとしています。それも若い頃は、自分の演出作品でないものに役者として参加したとき、どうしても偉そうに演出家目線で見てしまっている部分があって。たとえば演出家の方が役者さんにダメ出しをしている姿を観て「うーん、俺ならこうするんだけどな」とか思ったりして。もちろんそれも、いろんな価値観を知ることができたという面で、演出家の自分にとっていい勉強になったとは思うんですよ。ただ、今はもうどの現場でも、それが映像であれ舞台であれ、せっかく呼んでいただけるのであればいち役者として、他の役者さんと対等に戦えるように頑張っているつもりではありますね。
三谷幸喜作品をデッサンするように脚本を書いた
──赤堀さんは1996年に劇団THE SHAMPOO HAT(立ち上げ時はSHAMPOO HAT)を立ち上げて本格的に演劇活動を始められたと思うのですが、その前にショーレストラン、いわゆるショーパブのようなところで活動をされていたんですよね。その頃のことを詳しく知らなくて……。
知らなくていいですよ(笑)。異質なスタートですよね。当時は演劇のえの字も知らなかったですし、何かの演劇作品を観て衝撃を受けてとか、誰かに憧れてということではなく、最初の動機は本当にチャラくて。「芸能人ぽいものになれたらな」というだけの理由で客前で何かをやるという道に進んだんです。それがお笑い芸人なのか、役者なのかも自分でわかっていなかった。まさか自分がいま作家や演出家として活動しているなんて、当時は本当に夢にも思わなかったですよ。ショーパブで、お酒を飲んでいるお客さんの前で何かをやっている頃は、本当に何も考えてなかった。
──それがなぜ演劇の道に?
そのお店が潰れることになって。店には漫才をやる人とか踊ったりする人とか、30人くらい所属していたのかな。僕はどちらかというと、コントっぽいお芝居をやる部類の人間で。特段仲がよかったわけでもないですけど、一緒にお芝居をやっていた男6、7人で「じゃあ劇団でもやってみるか」という感じで始まったのが劇団THE SHAMPOO HATでした。ただ劇団といっても、僕は当時、演劇を観たことなんてなくて。旗揚げしたのが23歳くらいだったのかな。その後、ちゃんと芝居を観たのは29歳ころですから。
──劇団を立ち上げて6年後!
劇団をやっているのに、全然観に行かなかった。で、旗揚げしたものの、脚本を書ける人もいないんですよ。ためしに先輩の知り合いに脚本を書いてもらったんですけど、全然おもしろくなくて。演劇を観たこともないド素人が何を言ってるんだという話ですけど、「こんなの面白くないよ」とみんなが言い出したので、脚本なんて一度も書いたことがないのに「じゃあ俺書くよ」と手を挙げた。そこからですね。
──では他に誰もいなかったから、必要に迫られて書くことに。演劇を観たことも書いたこともない中で、どんなふうに最初の脚本を書かれたんですか?
先輩に児玉(貴志)さんという人がいて、彼はそれなりに浅く演劇を知っていたんですね。「児玉さん、どうしたらいいの? 何かない?」と聞いたら三谷幸喜さんの『東京サンシャインボーイズの罠』のビデオを観せられて。「ああ、これ面白いね」と、それを丸パクリしていました。
──それは、書いても大丈夫ですか?
全然いいですよ(笑)。パクリというかね、観ていくと芝居の骨組みがわかるわけですよね。たとえば三谷さんの芝居って、とくに初期は共通した骨組みがあって。結婚式なりお葬式なりの人が集まる状況で、疎遠になっていた昔の仲間が集まり、なにかハプニングがあって協力せざるを得なくなり、みんなが一致団結してそれぞれのキャラクターを活かして乗り越え、各々の場所に戻っていく──。
──聞いただけでいくつかの作品が思い浮かびます。
だからその骨組みを参考にしながら、自分なりに書いていったんですよね。基礎を三谷作品から勝手に学んでいった。美術学校に通ったら、まず最初にデッサンを描くじゃないですか。そんな感じで「ああ、こうやって陰影をつければいいのか」など三谷作品をデッサンのように取り入れていった。そこを入り口として作家の道に入ったというのは、自分にとっては正しいことだったのかなという気がします。最初の数作はそうやって真似しながらやって。ちゃんと自分の筆致で書けるようになったのは4作目くらいからですかね。
──全く脚本を書いたことのない状態から、最初はいわゆる習作のような形で始めて、物語を作ることができるようになったわけですね。
三谷さんにはすごく失礼な話ですけど、「僕はこういう部分はちょっと恥ずかしいかな」とか「自分だったらこうするな」というところが自分なりにブラッシュアップされてきて。あとは、当時映画をたくさん観ていたんですけど、その時期にヴィム・ヴェンダースという監督の『まわり道』という映画を観て。しょうもない男が自分探しの旅に出かけてひたすらウロウロしているだけの話なんですけど、なんかその雰囲気が好きで「あ、これやりたいな」と思ったんです。三谷さんのウェルメイドな部分とヴィム・ヴェンダースのちょっとトガった部分が混在して、20代後半くらいにやっと「自分なりの作品になってきたかな」という実感が持てるようになっていったんですよ。
──三谷さんが出発点とは意外でした。ヴィム・ヴェンダースの「ただいる」感じは今もかすかに残っている気もしますが……。
今の自分が書いているのは、あんなハードボイルドな作品ではないですけどね。その後はたとえば山田太一や向田邦子作品にも多分に影響を受けていますし。作り手ならばみんな同じだと思いますが、結局自分の中にいろんなものが混在していって、それをどう咀嚼して抽出するかということだけなんでしょうね。若い頃は、自分が何に影響を受けたかということもあまり言いたくなかった。今はもう、どうでもいいなとペラペラしゃべります(笑)。影響を受けたものはあっても作品がちゃんと自分のものになっているという自信がついたということかもしれないですね。
ミリ単位で演出をつけていた時期

──赤堀作品に登場する人たちには存在感、たしかにそこに生きている体重の重みを感じます。赤堀さんはどうやってあの物語や人々を演出しているんでしょう?
うーん、難しいですね。今言っていただいたようなことは常に考えてはいます。演出するとき、ちゃんとそこにその人が実存するような感覚を目指してはいる。まあそれも、演劇である以上嘘なんですけどね。
──そうですね。
劇団の最初の頃は、さっきも言ったように僕はいちばん演劇経験がなかったので、みんなでいろいろ言い合いながら芝居を作っていて。チラシでもしばらくは「脚本:赤堀雅秋、演出:SHAMPOO HAT」という形にしていたんですよ。「6割くらい僕が演出してるんだけどな」と悔しい気持ちはあったし、自分のエゴもあって他のメンバーが提示する演出もあまり面白いとは思えなくて。4回目くらいからみんなも「しょうがない、演出の名前も赤堀でいいか」と「作・演出:赤堀雅秋」になったんですね。そこからはもう、鬼の首をとったように一挙手一投足、先輩であろうが誰であろうが「いや右手が違う」とか「たたずまいが違う」とか言うようになって。ミリ単位でいろいろ言っていた時期もありました。
──そんな厳しすぎる演出家時代があったんですね。
細かくしつこくミリ単位で動いてもらって、何回かはそれで納得するようになったけれども、それこそ「やっぱり役が呼吸していないな」とか「たたずまいが自由じゃないな、だからそこから漏れ出す何かが生まれてこないんだな」とか思うようになるわけですよ。だとすると、こちら側が発する言葉もなにか変えなきゃいけないんだなといろいろともがいて変えていったりしてね。
──演出のやり方を試行錯誤して。
また納得しかけるんだけど、「うーん、だから何だ」という思いにとらわれて、また何かを壊して再構築する……。ずっとそうなんですけどね。今も何回転かして、自分のなかでは過渡期で。どういうものの作り方をしたら面白いのかなというのが、袋小路に入っている状況ではあるんですよ。この先もずっと延々そうなんでしょうし、おそらく作り手なんてみんな、きっと同じようなことを繰り返しているんでしょうけど。
劇団で一つひとつ獲得していったもの

劇団をやっていて有意義だったなと思うのは、誰に教わるのでもなく、本当に自分たちで模索しながらやってこられたことなんですよ。「演技ってこういうものなんじゃないか」というのをみんなで学芸会のように手作りでやってきたことが、自分の経験においてすごく大きい。ある芝居で、屋上から飛び降りようとするシーンがあったんです。その稽古をする時に、普通は稽古場で演者がそれらしく演じるじゃないですか。でも僕も本当に屋上から飛び降りようとしている人を観た経験があるわけでもないし、演者も当然やったことがない。だから、それらしくやってみてはいるけど「何か違和感があるね」となったんですよ。当時は演劇禁止の、区民集会所みたいなところを借りて稽古をしていたんですけど……。
──禁止のところで!
ちょうどその集会所が、脚本と設定が同じ、3階建ての雑居ビルにあって。「ちょっと実際にやってみようぜ」と夜、その稽古場の屋上にみんなで勝手に入ったんです。屋上の柵を越えて、へりに立つという芝居をやるために。そしたら当たり前だけど怖くて立てないんですよね。へりの立ち方自体、稽古場でやってみたのと全然違う。(立ち上がって)稽古場ではふつうに足からへりに上がれたんですけど、いざ本当のへりに登ろうとすると怖くてまず膝からしかいけないんですよ。細かい話だけど、足全体をぐっと上げられない。しかも常に、へりとは反対側に倒れ込めるような体勢になる。
──ぜんぜん違うんですね。
包丁を突きつけられたら実際にはどんな感覚になるのか、突きつけないまでも一度本物を買ってきてみようとか。重いものを持ったとき、どういう身体になるのかとか。金はなかったけど無限に時間だけはあったから、一個一個誰に聞くでもなく発見していったんです。学校で「このときはこういう動きをする」とステレオタイプのことを教わるんじゃなくて、みんなでワイワイ言いながら全部やってみたんですよ。
──メソッドを学んでみようという方向には行かず、とにかく本当の経験を重ねていった。
僕を筆頭にみんなバカだったから。僕、若い頃一度演技のワークショップに出たことがあって、そしたら「電話に出るときは右手で受話器を持って、カメラがこっちにあるから中盤から左手に持ち替える。こういう技術があるんだよ」と講師の人がしゃべっていて。いや、大事なことなんですよ? だけどそんなことをドヤ顔で語られても「で?」としか思えない。教えるべきことってそういうことなんだっけ? と思ってしまう。そのモヤモヤした気持ちがあったからいまだにあのテクニックは記憶していますけど、自分で実践したことはないですね。最初から持ち替えたほうで出ちゃう。
──たしかにそのほうがよさそうです(笑)。
そうやって誰かに上辺だけ教わってわかったような気になるんじゃなくて、みんなと「このときはこういう身体になるんだね」という経験を重ねたのが、劇団をやっていて一番よかったこと。あれはとても豊かな時間だったし、いまの自分の血肉になっている感じがします。
“伝える”意識が180度変わった経験
──自分たちで一つひとつ獲得していったことは、赤堀さんにとって演出のうえでも、演技のうえでも今なお大きな財産なんでしょうね。
そうですね。もうひとつ、30代前半の頃、劇団のほかにENBUゼミナールというのをやらせてもらって。
──役者や演出家をめざす人たちの学校ですね。そこで講師をされていた。
あの経験もまた非常に大きかった。その頃は、本当にバカの極致なんですけど、何の根拠もなく自分が世の中で一番だと思っていたんですよ。そんな状態で何も知らないくせに一丁前に講師なんてやらせてもらって。受講生も当然何も知らない若い子たちで、僕がしゃべっていることに対してみんなポカンとしてるんです。生徒たちが日本語を知らない外国人なのかというくらい言っていることが伝わってなくて、最初は「なんだこいつら、なんで俺の言ってることがわかんないんだよ」って、怒りしかなかった。でも途中から「ちょっと待てよ」と思ったんです。生徒たちに「もっとちゃんと日本語覚えてこいよ」と思っていたけど、本当はこれ、自分が外国人なんじゃないかと。
──向こうが理解できていないんじゃなくて、自分が伝えられていないのだと。
ちょうどその同時期に、グローブ座で三宅健くん主演の『殺人者』という作品を手掛けて、そこでもお客さんに伝わらないなというジレンマがあった。もちろん拙い作品だったというのが一番の要因ですが。それでも「自分が外国人なんだ」と思えるようになったらコロンブスの卵みたいに意識が180度ひっくり返って、そこから伝え方とか演出のしかたも変わり始めました。外国人の自分がなんとかわかってもらうためにボディランゲージを使ってみたり、ボキャブラリーを増やすようになったんです。劇団だけをやっているとやっぱり井の中の蛙で、お山の大将のままなんですよね。自分にとってはENBUゼミだとかグローブ座だったりとかの外の世界での経験が、価値観を変えてくれたなという自覚があります。
──劇団でずっとやっていたら気づかなかった?
そうでしょうね。本当、劇団なんてよくも悪くも新興宗教みたいな団体だから(笑)。まあ、そのまま劇団の仕事だけやっていたら、「俺、演劇やってます」みたいな、かっこいい芸術家みたいな方向に行っていたかもしれないけど。でもやっぱり世の中や人間を描く作家としては、それだけという状態は不健康ですよね。
──やっぱりいろんな人に伝えたいという気持ちがあるということでしょうか。
100%伝わる、理解してもらうことは今でも不可能だと思っているので、塩梅が難しいんですけどね。というか、100%伝わることがもしあったとしたら、それはそれで本当に危険なことじゃないですか。たとえば戦争反対というテーマがあったとして、それが100%伝わって、芝居を観たお客さんがみんな「戦争反対だ!」と涙を流しながら劇場を出るのは非常に気持ち悪い現象だと思うので。何かを啓蒙するみたいな気持ちは微塵もなくて、ちょっとかっこつけた言い方をすると、種子を残すような仕事ができたらな、と思いますね。
演劇的、映画的であることの落とし穴

──赤堀さんは役者としても脚本家としても演劇と映像両方で活躍していますし、『その夜の侍』や『葛城事件』などご自身の舞台をもとにした映画で監督も担当されています。演劇と映像の違いはどう捉えていますか?
技術的にはもちろん違いますけど、僕はあまり差異を感じていなくて。元々演劇もよくわからないままやりはじめて、今だって結局何もわからないままなんですよ。映画も全く同じで、最初自分は脚本だけでの予定だったんですけど、急遽自分が監督をやることになって、右も左もわからないなかで現場に入った。結局、自分が何者なのかという確固たるものが何もないんですよね。演劇界にいてもそうですし、映画界にいてもよくわからない立ち位置にいるなあと思っています。ただ自分の意識としては、何かを表現するということにおいては、演劇を介在しようが映画を介在しようが、基本的には何も変わらないつもりでいるんです。
──区別はない。
はい。自分が観客として演劇を観てても「ああ、これを作っている人は演劇好きなんだなあ」と思ったり、映画でも「この人は本当に映画好きなんだなあ」と感じる作品がありますけど、「だから何だ」「自分に酔ってるなあ」と思ってしまう時がある。マスターベーションを見せられてる感覚に近い。もちろん尋常ではない最高のマスターベーションなら、変な感動も生まれてきますけどね(笑)。
──それこそジャンルを区別せずに表現しているからこそなのかもしれないですね。
もちろん、演劇はさすがにもう何十年もやっているので、演劇なりの面白さ、表現のしかた、仕掛けの作りかたとか、そういうことは何度もチャレンジして何度も失敗してきました(笑)。だから演劇的、映画的であることの面白さというのもおぼろげながらにはなんとなくわかるつもりではいますけど、それは結局作り手側の自己満足のような気もして。お客さんに何かを波及するための仕掛けや遊びならいいですけど、「俺こういう仕掛けもできるんだ」「こういう表現は飽きちゃったからこういうことをやるんだ」とかされても、客からすれば知らんわという話じゃないですか。そこに偏らないようにはしているつもりです。元々素地がないからできないというのもありますけどね。
──先程からちょくちょく出てくる「だからなんだよ」という意識を、ものを作る上で常に自分に問いかけているような。
自分が観客だったら、やっぱりそう思ってしまうから。「作ってる人は楽しいんだろうな」という芸術的な舞台とか、あるじゃないですか。たとえば蜷川幸雄さんの舞台って、演劇的な仕掛けがちゃんと観客を飲み込むところまで行っている気がするけれど、そこまで波及できずに「僕はこんなこともやってるんです」で自己完結してしまっているものが多い気がして。映画でも「俺、こんなパンクなことやってます」みたいな作品って得てして「うるさいな、早く終わってほしいな」となったりするし。「演出家は第一番目の観客であるべき」という言葉を誰かから聞いた記憶があるんですけど、やっぱりそこは客観と主観のバランスというか、自分がこの作品を観てどう思うかはいつもいちばん大事にしていますね。僕にとって僕がいちばん嫌な客なので(笑)。
70歳くらいになったら作れるかもしれない作品
──最後に、赤堀さんは今後どうなっていきたいか、教えていただけますか。
全然わかんないなあ。
──もちろん、演劇は続けていかれると思いますが。
これまではいわゆる市井の人々、生活者みたいなものにスポットを当てて、ミニマムな些末な事象をどう切り取るかをずっとやってきて。今までは近視眼的にそういうものを描いてきました。それがここ5年くらい……特にシアターコクーンの『世界』という作品から、その生活を、事象ををちょっと俯瞰で描いてみたらどうかなと思いながら作るようになって。今年の春に上演した『白昼夢』で自分の中ではそれなりに面白いものが作れたという自負があるんです。だから次どうしようかな、というのがさっぱりわからなくて困っているんですよ。そばでずっと見てきた人たちは「また言ってるよ」と思うだろうけど、今ちょっと困っているところですね。
──次のステップを模索している。
そうですね。ただ、『はじめ人間ギャートルズ』のエンディングテーマ(やつらの足音のバラード)がいま、僕の心のテーマで。「♪なんにもないなんにもないまったくなんにもない」という歌詞がすごくいいなと思っていて。すごく抽象的ですけど、ああいう作品が作れたらなあと思いますね。別に原始時代の話が作りたいんじゃなくて、観念的な意味合いでね(笑)。でもまあ、これは70歳くらいにならないと無理でしょうね。

■プロフィール
赤堀雅秋(あかほり・まさあき)
1971年生、千葉県出身。劇作家、脚本家、演出家、映画監督、俳優。
劇団THE SHAMPOO HATにて作・演出・俳優の三役を担う。人間の機微を丁寧に紡ぎ、市井の人々を描くその独特な世界観は赤堀ワールドと称され、多くの支持を集めている。
劇作家、演出家として主な作品に、M&Oplays『白昼夢』(21年)コムレイドプロデュース『神の子』(19年)、シアターコクーン『美しく青く』『世界』『大逆走』『殺風景』、「オフシアター歌舞伎『女殺油地獄』」、M&Oplays『流山ブルーバード』、コムレイドプロデュース『鳥の名前』、青年座本公演『蛇』(磯村純演出)、PARCOプロデュース『LOVE30』(作・宮田慶子演出)自転車キンクリートSTORE『富士見町アパートメント』(鈴木裕美演出)、広島アステールプラザ「演劇引力廣島」公演『彼の頭上。雲たなびく』『ボーダー』などがある。劇団『姦し』の作演出も手がける。
岸田國士戯曲賞最終候補作に第51回『津田沼』、第52回『その夜の侍』、第55回『砂町の王』があり、第57回『一丁目ぞめき』にて岸田國士戯曲賞を受賞。
2012年、劇団公演『その夜の侍』の映画化にあたり自ら監督・脚本をつとめ、モントリオール国際映画祭、ロンドン映画祭に正式出品され、新藤兼人賞金賞とヨコハマ映画祭森田芳光メモリアル新人監督賞を受賞。2016年、映画2作目『葛城事件』(監督・脚本)にて、報知映画賞主演男優賞、TAMA映画賞主演男優賞 最優秀新進男優賞、ヨコハマ映画祭主演男優賞、高崎映画祭主演男優賞、東京スポーツ映画大賞主演男優賞を受賞。
また、俳優として近年の出演作は、舞台ナイロン100℃ 46thSESSION『睾丸』、『東京月光魔曲』、KERA・MAP『あれから』『龍を撫でた男』(演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチ)、『鼬』『浮標』『南部高速道路』(演出:長塚圭史)、『シダの群れ 3〜港の女歌手編〜』(作・演出:岩松了)、『オセロ』(演出:白井晃)。
映画『彼女がその名を知らない鳥たち』(監督:白石和彌)、『岸辺の旅』(監督:黒沢清)、『マイ・バック・ページ』『実験四号』(監督・山下敦弘)、『ぐるりのこと』(監督・橋口亮輔)、『てぃだかんかん』(監督:李闘士男)や、TVドラマ『集団左遷!!』『60-誤認対策室-』『監獄のお姫さま』『ヒトリシズカ』『贖罪』『モテキ』などに出演し、その活動は多岐に渡る。
ナイロン100℃ 47th SESSION 「イモンドの勝負」
【作・演出】
ケラリーノ・サンドロヴィッチ
【出演者 】
大倉孝二 /
みのすけ 犬山イヌコ 三宅弘城 峯村リエ
松永玲子 長田奈麻 廣川三憲 喜安浩平 吉増裕士 猪俣三四郎 /
赤堀雅秋 山内圭哉 池谷のぶえ
【東京公演】
2020年11月20日〜12月12日@本多劇場
【兵庫公演】
2020年12月18日19日@兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール
【広島公演】
2020年12月21日@JMSアステールプラザ大ホール
【北九州公演】
2020年12月25日26日@北九州芸術劇場中劇場
https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/nylon47th