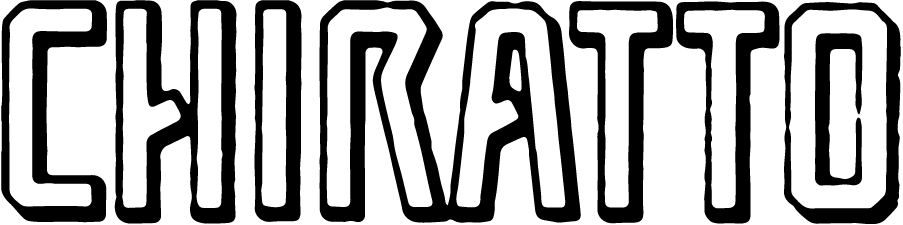第二十七回特別インタビュー せきしろ(作家・俳人)

たとえば、ありふれた景色から想像をふくらませ、読者を異次元へと連れて行くような文章。あるいは、短いことばで日常に新たな視点を放り込む自由律俳句。絶妙なおかしみと、ときに郷愁をまとうコント……。どこまでもクールな語り口で笑いを生み出す文筆家、せきしろさん。ときにライブを開催し、ゲームを生み出し、いろんなかたちの表現を世に放っています。その唯一無二の活動と作品について、お話を聞きました。
演者に背負わせすぎないための“雨の音”

――せきしろさんが作るもののなかには、思いがけないタイミングでふと美しい景色が入ることがありますよね。たとえば、コントの最中に水芭蕉の咲く尾瀬の景色の映像が流れたり、せきしろさんが主催する大喜利ライブのシンキングタイムに夏の花火の音や虫の音が流れたり……。
せきしろ:それは、まず前提に歳をとったというのがありますね。景色とか花とかに興味を持ちはじめてしまった。静かなほうがよくなっちゃって。
――だから、シンキングタイムに自然の音を使う。あの大喜利ライブ『徒手空拳』は「お題に対して3分間を使い、たった一答を出す」というものだったので、観客は3分間丸ごとその音を聞くことになりますよね。
せきしろ:そうですね。本当はあの3分間が無音でもよかったんですよ。でも雨の音とかひぐらしの声とかの環境音を流したのは、音があればそれのせいにできるからです。
――それのせいにできる?
せきしろ:実際はそんなことを言う人はいなかったですけど、演者が「この音がなければもっと集中できた、いい答えが出せた」とか言えるじゃないですか。逃げというと聞こえが悪いですけど、言い訳できるものというか、こちらが悪い感じにできる要素。
――3分間考え続けて渾身の一答を出すというストイックなライブだからこそ、そういう要素が必要だったんでしょうか。
せきしろ:これに限らず、ライブをやるときは、こういう部分はいつも作るようにしてるんですよ。演者に負わせすぎないように。観客の方が「あんなのいらないよ」と思ったとしても、その意見は裏方に来るじゃないですか。そういうものをつくっておく。
――では、バッファロー吾郎A(バッファロー吾郎)さん、上田誠(ヨーロッパ企画)さんとともに脚本を担当しているコントライブ『すいているのに相席』では、コントの合間に尾瀬の景色が流れるものは?
せきしろ:あれは単純に本当にああいうものが好きになったから(笑)。まだそういうものが好きじゃない人が見たら「なんだよこれ」と思うかもしれないけど、中には「私もこういうものを見るようになったな」と反応する人もいるかもしれない。
――そういえば『すいているのに相席』でも最初の頃は、清原和博さんの引退セレモニーの映像が流れたりしていましたね。
せきしろ:あれもいらないといえばいらないんですけど。そのとき自分が好きなものを流しているんですよ。「なんだよこれ」と演者に言われてもそれでいいし、淡々とやってくれてもいい。『相席』なんかだと、わりとみんな「そういうものだ」と思ってやってくれるから助かりますね。
ボケの少ない、ツッコミのないコント

――せきしろさんは小説とかエッセイとか、ときにはコントでも、ものすごく情緒があるものを生み出されていると思います。その一方で情緒とはかけ離れたように見える、誰も表にしないものを表にするような表現がありますよね。
せきしろ:間がないんですよね。感情が抜けているのかもしれないです。
――情緒的な文章であっても、そのときの感情とかが描かれているわけじゃなくて……。
せきしろ:そう、状況にしか興味がないんです。自分はあまり出さないんですよ。
――感情を描かないのは、あえてですか?
せきしろ:性質かもしれないですね。僕、一人称でしか文章を書けなくて。そうじゃなく書こうとしても、結局ぜんぶ自分になっちゃうんですよ。だから、恥ずかしいこととかが書けないんですよね。「自分はこんなことしないしな」とか思っちゃって。だから、自分と真逆のキャラとかも出てこない。結局何を書いても、私小説……とまでは言わないですけど、自分。
――その、自分しか出てこないというのはコントでもですか?
せきしろ:うーん、僕、会話が書けないんですよ。自分が人とあんまりしゃべらないから、わからないんですよ。会話って受け答えだから、つまらないことが挟まるじゃないですか。それがもう恥ずかしくて書けない。それで、堅苦しくなっちゃうんですよね。ただコントだと、すごく説明的なセリフを発しても問題ないじゃないですか。だから説明ゼリフは書ける。でもふつうの真面目なドラマとかは書けないですね。
――小説とコントは、書くとき区別しているものですか?
せきしろ:そんなに変わらないかもしれないですね。コントもわりと淡々としていますから。
――たしかにそうですね。でもときどき、ものすごく切ないコントがあったりして。
せきしろ:僕が書くものは圧倒的にボケが少ないですからね。あと、誰もツッコまない。みんな、ずっと好きなことを言っているだけです(笑)。大きく言えば超新塾さんと一緒ですね。みんなが順番にしゃべっている方式。
――超新塾さん(笑)。でもボケが少なくても、ツッコミがなくても、せきしろさんの書くコントには独特のおかしみがあるように思います。ご自身ではどこで笑わせようと狙っているんでしょう?
せきしろ:ボケてないところで笑うのかもしれないと思って……、自分が見せられたら笑っちゃうかもしれないな、と思いながら書いています。
――もうひとつ、たとえばコラムとかライブで発表される、表やリストなどの表現はいったい
どこから生まれているんでしょう。たとえば「ロード何章なのかがわかる早見表」とか「くるりのメンバーの人数変遷」のような……。
せきしろ:表とかリストが好きなんですよ。もともと理系だったので、表に整理するのが好きなのかもしれない。
――情緒的な文章やコントと真反対の表現だと思っていましたが、感情ではないものという点では同じなのかもしれないですね。
せきしろ:そうですね、そこに感情は一切ないです。マニュアルに近いのかな。電化製品のマニュアルで「電源が入らないときは?」とかいうのがあるじゃないですか。「コンセントが抜けていませんか?」とか。あれが元なのかな。
――マニュアルをじっくり読むタイプですか?
せきしろ:子供の頃とか、よく読んでました。……しなくていいことをする、ということかもしれないです。結局、僕はしなくていいことしかしてないのかもしれないですね。
上京しないと手に入らないもの

――せきしろさんは、若い頃芸人をめざして上京されたそうですね。でもお笑いの養成所がまだなくて、なりかたがわからないうちにものを書くほうに行かれたと。
せきしろ:養成所が当時大阪にはあったんですけど、東京にはなかったんですよね。見つけられなかった。
――このままものを書いて、作り手側として生きていく、と決意したのはいつ頃ですか?
せきしろ:全然、決めてないですよ。
――今も?
せきしろ:はい。今でもできることなら就職したいです。就職しておけばよかった、失敗しましたね(笑)。うん、なにかになろうと決めたことはないですね。芸人になりたいなという気持ちはあったけど、「絶対芸人になろう」というよりは、ただ上京したいということだったのかもしれない。上京しないと手に入らないものが、当時はいっぱいあったんですよ。レコードにしても、舞台を観るにしても、映画でも。そっちのほうが大きかった。
――なるほど。上京の理由としての芸人志望だったわけですね。
せきしろ:僕の10代、20代の頃は、カルチャーが今よりもぐちゃぐちゃしていた、いろんなものが分かれていなかった時代でもあって。たとえば竹中直人さんって演劇の人でもあるけど、お笑いもやっていたりした。ミュージシャンだけどMCができる人とかもいましたし。だから、そういうカルチャー全体に触れたいというか、そういう感覚があったんだと思います。
――当時、せきしろさんが憧れていた人は?
せきしろ:とんねるずさんです。『夕焼けニャンニャン』くらいのとんねるずさんって、わりとなんでもOKみたいな感じにしてくれていた存在だったんですよ。言動もそうだし、お笑いなのにレコードを出したりもしていたし。「じゃあ自分も」みたいな気持ちを与えてくれたんですよね。
――では、自然に、流れるままに書くほうに行っていたわけですね。いま、書くことはつらいですか? 楽しいですか?
せきしろ:書きたいことがあるときは全然つらくないですよ。ただ、物語を書いているとすぐ寝ちゃうんですよ。僕、ものを書くときは横になりながらiPhoneで書いているので。
――iPhoneで。小説のように長いものでもですか?
せきしろ:はい、なんでも。
――横になっている体制は、具体的には仰向けですか? うつぶせですか?
せきしろ:わりと仰向けで、手でiPhoneを持って書いてます。途中で寝ちゃって、顔にiPhoneが落ちてきて終わりです(笑)。直しはパソコンでするんですけど。
――へー!
せきしろ:最終的にはプリントアウトをしてチェックしないと、モニターで見ていてもミスに気づけないので。iPhoneでプロット的な感じでガーッと書いて、それをパソコンで整える感じです。
――自由律俳句も?
せきしろ:そうですね。
――自由律俳句は、せきしろさんのライフワークのひとつのように思いますが。好きですか?
せきしろ:作るのは好きですよ。
――どういう部分がいちばんの魅力ですか?
せきしろ:やりたいことがぜんぶ入っている感じがしますね。景色でも、情緒でも。
アドバイスを自分のものにした人が売れていった

――せきしろさんは、たとえば又吉直樹さんがまだ今ほど知られていない頃に一緒にライブをされたり、自由律俳句の本を共著で出したりもされていますよね。他にもいろんな芸人さんと一緒にライブを開催されたり、ご自分のイベントに呼んだりされている。才能ある人をそのままにしておけないという面があるように思いますが。
せきしろ:そんな大層なものではないですけど。ただ、「あなたはこういう感じだから、こうしたほうが売れる」とか「こうしたほうがいい」とか人に言うのは得意なんですよ。だから、伝えられる人には伝える。ただ、自分にはそれができないんですけどね。
――それを聞いて、成長していく人たちがいる。
せきしろ:たぶんですけど、僕がいわゆるお笑いのセオリーみたいなものの中にないことを言っているときがあって。それを面白がってくれる人たちがいるんですよ。で、それを自分の中で一回咀嚼して、自分なりの形に変えた人たちが、結局売れた気がしますね。もちろん本人がもともと持っているものがあって、努力があってのことですけど。山ちゃん(南海キャンディーズ山里亮太)にしろ、又吉さんにしろ、僕と一緒にいたときに話したこととかを取り入れつつ自分のものにしてくれているのを見ると、すごいなあと思います。
――なるほど、そのままではなくて、吸収して自分のものにする。
せきしろ:自分も影響を受けたとき、そうするようにしています。
――ちょっと角度が違うかもしれませんが、せきしろさんはパンクがお好きだと話されることがありますよね。そういう影響が、つくるものに出ていたりもしますか?
せきしろ:パンクからは「とりあえずやる」ということを学んだ気がしますね。中学生のとき、初めてパンクを聞いて「これでいいんだな、とりあえずやればいいんだ」と思った。とんねるずを見たときもそれは思いました。「そこにフリがないからダメだよ」とか「ツッコんでないからダメだよ」みたいなことを言ってくる人もいるけど、それは置いといて、とりあえずやればいいと思ってるところはありますね。結局それがうまくいかずに今になっているのかもしれませんけど……。
――そんなことはないです!
せきしろ:自己肯定感が異様に低くて。誰も自分に興味がないだろうと思っているし、自分のことなんか好きな人はいないだろうと思ってしまうんですよね。だから、告知も苦手で。「こいつ何告知してるんだよ」とか思われるかも、と思っちゃって。
――そんなことは思わないですよ(笑)。せきしろさんを慕う人も多いではないですか。ハガキ
職人出身の方とか、作家の方とか。
せきしろ:まあ自己肯定感の低さの裏返しで、頼まれるとうれしくなってやってしまうんですよね。「ネタを書いてほしい」とか言われると、金銭面は放っておいて受けちゃう。本当はもうちょっと考えたほうがいいんでしょうけど、たぶんずっとこのままだと思います。
これからは未来のために

――コントライブ『すいているのに相席』をはじめとして、せきしろさんはバッファロー吾郎Aさんと一緒にライブなどをやられることが多いですが、改めて魅力はどんなところにありますか?
せきしろ:バッファロー吾郎A先生、というかバッファロー吾郎のコントを初めて見たときも、衝撃でした。セオリーに当てはまらないというか、さっきの話じゃないですが音楽のジャンルでいうとパンクに近かった。「こんなにも思ったことを自由にやっていいんだ」という感覚。だからずっと一緒にやりたいなと思っていたんですよ。長年の思いをようやくちゃんと形にしたのが『相席』ですね。
――今後も『相席』は続けますか?
せきしろ:具体的には決まっていないですけど、たぶんやると思います。
――楽しみです。さいごに、今後の展望を教えてください。
せきしろ:なんだろう……。僕、なんか言っていたことありましたっけ?
――以前、「絵本を描きたい」とおっしゃっていたことがありました。
せきしろ:あ、そうですね、子どものためになることがしたいです。いま、真逆のところにいるんですけど。ライブをやると最前列は40代の男子で埋まりますけど(笑)。なにか、未来のためになるようなことができればいいなと思います。
■プロフィール
せきしろ
1970年北海道生まれ。文筆家。主な著書に、『去年ルノアールで』『海辺の週刊大衆』、『1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった』『たとえる技術』『その落とし物は誰かの形見かもしれない』などがある。また、又吉直樹氏との共著『カキフライが無いなら来なかった』『まさかジープで来るとは』『蕎麦湯が来ない』西加奈子氏との共著『ダイオウイカは知らないでしょう』では、それぞれ自由律俳句と短歌に挑んでいる。「劇団せきしろ」「すいているのに相席」では脚本家としての一面も持ち、多岐にわたる活動で注目を集め続けている。